源氏物語を引用した別文学や映像以外の文化作品
- 2021/04/10 17:29:57
投稿者:maekoo
源氏物語は、後世、鎌倉・室町時代を中心に、和歌で言えば源氏取りや本歌取りの受容史があり、文学では様々な亜流やエッセンスを取り入れた多くの物語文学や擬作が創作され、能・猿楽をはじめとする脚本や演劇が沢山出現しています。
それは江戸時代の文学や歌舞伎等の演劇にも影響を与えており源氏物語の奥深さと作品としての完成度の高さを再認識させてくれます。
ここでは源氏物語の「関連図書」「疑作や亜流・創作」「映像作品」「原文」「藤原定家」以外の引用作品や意匠作品・多作品での発見等を出し合い交流できればと思います。
逆に上記の「〇〇〇」の内容はその該当する掲示板に投稿して下さると他の皆さんが検索する時便利だと思います。
意外な発見が見つかるかも(^^)/



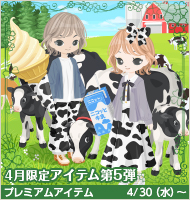











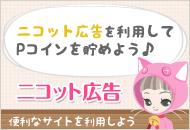
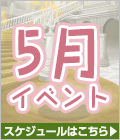








1995年12月20日初版発行 婦人画報社
源氏物語を扱った主な能の演目について、原点である源氏物語の引用巻及びそのあらすじや内容の紹介と、能で扱われている描き方やシテ方と地謡の謡も紹介してくれています。
あらすじや内容紹介は文学的な書き方で大変楽しめます。
能の紹介も、舞台設定や謡の意味、面の扱いや表現も紹介しており、中世の仏教観に裏打ちされた作品世界の紹介も深く、源氏物語も能も楽しめる贅沢な内容です。
夕顔との出会いを描いた「半蔀」、死して恋の煩悩に苦しむ夕顔を描いた「夕顔」、六条御息所の解脱を描いた「葵上」、六条御息所の哀しい恋情の回想を描いた「野宮」、流浪までの回顧と須磨での浄化を描いた「須磨源氏」、光源氏と明石の君の喜びの再会を描いた「住吉詣」、恋に翻弄される玉鬘の哀しい心の闇を描いた「玉葛」、夕霧と落葉の宮の切ない哀愁を描いた「落葉」、二つの愛に翻弄され迷い苦しむ姿を描いた「浮舟」、物語と作者の供養を願い源氏物語への愛を描いた「源氏供養」の10作品を紹介しています。
この中の何作かの哀しい物語は、仏道に導かれ救われていくと言う内容になっていて、室町時代の仏教観が表出しています。
光源氏が関わった女人との関係でハッピーエンドは無く、人間の哀しくも愛おしい情念のあわれさを、平安時代の雅な「色好み」から、室町時代の「幽玄」に昇華させ、芸術として発展した事が読み取れます。
源氏物語との距離が近かった時代の享受史が伺え知れて大変勉強になりました。
源氏物語が好きで能も好きな人は必携の書と言えます。
巻末の堀上謙氏の曲目解説は能としての内容を俯瞰するのにもってこいの資料です。
出雲阿国がモデルかな?
昭和61年4月27日発行 朝日新聞社
庶民に特にスポットが当たりだしたのは今昔物語以降でそれまでの王朝文学内の庶民についてはなかなか知る事が出来ません。
「小右記」や様々な日記文学で一部読み取れるのですが、全体として貴族と庶民の接点があまり無い事や文献に残らない事もあるかと思います。
鎌倉室町時代にかけては職人歌合等の文献により、その庶民の姿が解析する事が出来、その職能民を分析する事でおのずと先の時代の庶民の姿を読み取る事が出来ます。
このムック本は面白い週刊百科が多い朝日新聞社が発行した日本の歴史シリーズで内容もマニアックです。
この巻以外にも徳政令や法・悪党・占いや夢判断等を扱った巻も有り、庶民や思想史・習俗史を知る上で大変参考になります。
さて内容ですが、表題の様に遊女(白拍子・傀儡含む)の成立史や権力者との関りを含む歴史的役割、神聖なものから蔑視・賤視を受けるものへ激変して行った時代的流れや状況も知る事が出来ます。
太古から鎌倉時代前期までは聖なるものとしての神職や舞姫が半面売色を行っており、おおらかな時代と言え、官位と遊女の系統とは無縁だった事も知れます。
節会や五節舞等の舞姫供出も費用と人員不足から遊女が参仕した事も興味深いです。
つまり遊女の芸は大変高度で洗練されていた事が判ります。
後鳥羽院には白拍子腹の皇子が多く、親王が何人もいますし、特に深く寵幸した白拍子「亀菊」は隠岐まで院に仕えています。
ムック本の良い所は安価でいながらカラー写真や図がふんだんに掲載出来る所で、ここでも貴重な「洛中洛外図」や「職人歌合」の綺麗なカラー写真図が見れます。
千秋万歳楽の「蓮如上人子守唄」も紹介されていて庶民の威勢の良い商売の様子や辻子君(遊女)の客との謎かけ問答の駆け引きが具体的に描写されて面白いです。
この時代商売は一定料金でなく当事者間の駆け引きが重要でいかに洒落たやり取りが出来るかも重要だったそうです。(男女の和歌のやりとりや歌合せの様な感じ)
色街がその時代の文化発祥の源泉にもなっており、その時代時代の習俗を知る事でその時代の空気が読み取れ古典文学を愉しむ深みが増します。
これからも色々多角的に読み解いていきたいと思います
職人歌合 網野善彦:著 2001年4月10日初版 リキエスタの会
歴史上の職能民や職人研究の第一人者で日本中世史の専門家である網野教授の名著で元は岩波書店で発行された古典講読シリーズの一冊で平凡社からも出版されています。
リキエスタの会は岩波書店・晶文社・筑摩書房・白水社・平凡社・みすず書房6つの出版社が参加しオン・デマンド出版という形で発行をしている団体(発行元)です。
職人歌合の文献から様々な文献や研究を基に、他の国の職人図も紹介しながら、あまり日の目を見ない一般の職人たちに光を当てていて源氏物語等王朝文学を読むうえでも時代や習俗・風習・慣例が垣間見えその時代と世界を深める事が出来ます。
以下論じている内容・・・
貴族や僧侶が和歌の詠者である事、職能民は律令国家では官僚に組織し育成し技術を伝授していた事(陰陽師・絵師等々)、平安時代では双六や囲碁等の賭け事や賄賂や盗みを一種の芸能とする捉え方が有った事、和歌読みの左方・右片が職業でも左右方があり組織も違っていた事(左官と言う言葉も壁塗りの左方惣官から来ているのではと推測しています)、平安時代から鎌倉時代には無から何者かを生み出す職能民を神人(じにん)と呼んで材料採集の為に通行税の免除や特権を与えられていた時代もある事、神人の金融活動は神に対する返礼として利息をとっていて返さないと神罰・仏罰が下る為安定した金融形態となっていた事、平安時代の女房が一定の文化水準と裁縫や有識故実を弁えた女官として位置しており後宮での女流文化が発展し、そこから職業としての遊女が派生した事(後鳥羽上皇の例のように女官と遊女の境界線は低かった様です)、鎌倉時代の高利貸しには女性の金貸しが多くいた事(病草子の富を得て太った女の図)、職人歌合の画中詞の面白さも論じておられます。
江戸時代髪結いは橋の近くに構え橋の消防や見張りをしていた事や百姓と農民の違い等面白い話も沢山載っています。
職能民の問題は日本文化論や日本社会論を論じる上で重要な位置を占めている事が判る名著です。
この本を読んだうえで古典文学を読むと又違った面が見えより深める事が出来るでしょう!
原文読解:樋口秀雄 解説:石山洋
職人歌合せとは民衆に関心を持った貴族がその職種の人物になぞらえて和歌を詠み、其々の職業で歌合せをする趣向の高尚なあそびです。
大抵絵巻や画帳に成っており、様々な博物館でも偶に展示されておりその時代の一般的な職業や使われていた道具が垣間見えて興味深いです。
時代が進むにつれてその職業の衣装や形態の変化も絵から知る事が面白いです。
この本は江戸科学古典叢書全8巻のひとつで、知る人ぞ知る「七十一番職人歌合」の職人の歌合せ絵図と詞書からなる絵巻と、狩野吉信筆の美しい職人が働く絵図である「職人尽絵」、浮世絵の「彩画職人部類」を愉しめます。
職人達の生き生きとした絵が満載で観ていても楽しく史料的価値も高いですが残念ながらすべてモノクロです。(オールカラーの前田育徳会尊経閣文庫所蔵七十一番職人歌合の豪華大型本も出ていますが大変高価です)
たとえば「七十一番職人歌合」18番にはまんぢううり(饅頭売り)VSほうろみそうり(法論味噌売り)の歌合せが載っており其々二首和歌を詠み合い優劣を判者が述べます。
又、絵図の売り手が「今日は売れ行きが悪かった」「こちらも今朝から全然だ」みたいな会話が載っていて楽しいです。
他にも7番、山崎の油売りが「昨日からいまだ山ざきにもかへらぬ」と嘆いていると、もちゐうり(餅売り)が「あたたかなるもちまいれ」と優しいんだか商魂逞しいのかユーモラスなやりとりが見れます。(この場面は山崎の大山崎歴史資料館で展示されていて油売りの紹介もされています)
この「七十一番職人歌合」には源氏物語の場面や和歌から引用した歌も多く判者もその様な分析をしています。
又、源氏物語研究家であった藤原定家の和歌も多々引用されており色々探してみるのも楽しいです。
崩し字の原文を解りやすく現代の言葉に表示し直して下さっていて現代語訳ではありませんが読み易いです。
他の歌合作品も源氏物語を引用しているものが多いようで発見されたらここで紹介してください(^^)/