源氏物語の擬作や亜流・創作についての紹介や感想
- 2021/03/21 18:11:09
お薦め本が沢山なので、源氏物語の亜流や擬作、そして近現代の創作小説について深めれればと思い改めて上げました
源氏物語好きにとっては亜流や擬作、創作小説は世界が膨らんでいて楽しいですよね
現代語訳も実際原文を表現する上で今の言葉に直しているので創作ともいえるかもしれません
でも愚作はいらないですね
小生も色々読んで楽しみたいと思っています
既に紹介して下さっている書き込み等もありますがまとまっていた方が良いかと思い新規の方も居られるかもしれませんので内容が合致していれば重複していても自由に書き込み下さい
まずは紹介
「源氏物語 山路の露 本位田重美 1970.1.1第1刷発行 笠間叢書」
関西学院大教授本位田先生が詳しく論じて下さっています
刊本と写本の原文が掲載され冒頭が解説の読み易い本です
源氏物語夢の浮橋以後の浮舟と薫のその後を描いた内容で源氏物語に造詣が深い平安末期から鎌倉期の建礼門院右京太夫の作ではないかと言われている擬作です
その後薫の指示で小君が何度も訪問し遂に浮舟と対面し浮舟から母への手紙を受け取ったり薫の妻の二の宮が懐妊したりと色々ありますが結局浮舟は志しを貫き精進すると言う話の様です
じゃあそのままで良かったのではと思いがちですが、源氏物語に造詣の深い右京太夫の自分の中で納得させる意味もあったのではと言う仮説と、室町時代の「源氏小鏡」に山路の露の記載がある様に発表が遅かったのは父である藤原伊行が自分の和歌を公表しない性格で後に定家が発掘する様な家風が災いしていたのではと論じておられます
作者が確定しているわけではありませんが、なかなか面白い論文でした
皆さんも紹介や感想よろしく願います
図書紹介に乗せたものはこちらに移しておきます















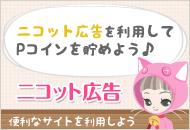












「若菜」を描いた3巻から13年、待ちに待った平安推理絵巻四部作最終巻!
能楽等の「源氏供養」のエッセンスと、作者別人説の有る宇治十帖を巧く融合させ、その頃の大事件「刀伊の入寇」をも練り込んで、筑紫と都との物語の進め方や登場人物達の関りが見事な最終巻にふさわしい大団円!
香子(紫式部)や阿手木・成長した賢子らも登場し又退場して行く!
新旧入り乱れて宇治の男女の物語を描いた源氏物語に結実して行くシナリオが物語世界を巧く膨らませ、そしてその表現が美しく哀しい!
何故源氏物語が読み継がれるのかをも創作として享受出来る!
様々な古典を昭和っぽい独自の意訳で艶っぽく訳したシリーズの源氏物語で昭和31年7月31日発行となっている変奏源氏物語!
桐壺から藤裏葉までのエピソードを光や紫の上・夕霧・玉鬘等々の様々な登場人物との愛憎と喜び悲しみを艶笑風に短く端的に著しておりクスクス笑いながらスラスラと読めます。
文芸作品と言うより大衆小説と言った感のある「太陽の季節」や「なッちょらんッ」「チェッ」等の言葉も出て来る昭和臭プンプンの面白源氏物語です!
糸綴じ風の表紙カバーもなかなか粋です。
源氏物語研究の息抜きにぴったりです!
物理化学を専攻しながら国文学者でもあった教授岡田氏のユニークで妖艶な時代ミステリー小説の単行本未収録作品を多く含む氏のエッセイも含む集大成本!
宇治十帖を題材とした薫と匂宮二人の香りをキーポイントとした連続殺人事件の紫式部と清少納言の推理合戦である表題作は氏の初長編であり源氏物語のエッセンスが散りばめられつつ現代的な推理が面白い!
「新釈雨月物語」は雨月物語を時代や解釈を変えながら怪しげでエロス溢れる怪奇幻想小説に仕上げた5編を愉しめます!
妖しく悲しい「新お伽草子竹取物語」、鼠小僧次郎吉の「変身術」、妖しくユニークな「異説浅草寺縁起」「艶説清少納言」、光源氏を題材にした妖艶で悲しい「コイの味」、様々な学説を散りばめながら謎の多い部分の物語を紡いだ「六条の御息所誕生」は後半氏の論的表出もあり面白い!
巻末の杉江松恋氏の解説は源氏物語に関わるオイディプス関係論や貴種流離譚論、丸谷才一氏の「恋と女の日本文学」にも触れ、実は柏木事件と宇治物語は光源氏と内大臣(頭中将)の逆転劇である分析が面白かったです!
「薫大将と匂の宮」は単体で書籍化されていますが、こちらの書籍が色々読めてお得です!
江國香織・角田光代・金原ひとみ・桐野夏生・小池昌代・島田雅彦・日和聡子・町田康・松浦理英子
文庫版 2011年5月1日初版発行 新潮文庫
源氏物語の帚木・夕顔・若紫・末摘花・葵・須磨・蛍・柏木・浮舟を題材に九作家が競演したオムニバスアンソロジー作品集!
正に源氏物語の変奏曲!
原作では想像の域の女三宮や浮舟等登場人物達の深層の精神世界を文学的に膨らませ告白させる事で読者の新たな想像と共鳴を掻き立ててくれます!
「若紫」や「葵」等現代の物語に置き換える事でその帖の持つ登場人物達の想いや願いをもクロスオーバーさせています!
様々な文学賞をとっている個性溢れる気鋭の作家達の料理する源氏物語を堪能して下さい!
新たな源氏物語世界が広がる事でしょう!
小生は新装版ではなく2018年6月15日初版の文庫版!
ついに道長の想いや知略も表出し、それを玉鬘篇と若菜上下とクロスオーバーする面白き3巻目!
雅な殿上人達の暮らしを支える時代の底辺で生きる人々の暮らしと想いが生々しく表現され様々な事件や史実・原典との絡みとその結末が見事で読後感は最高です!
前2巻の様々なエピソードが結実し源氏物語世界を史実を織り交ぜながら膨らませその謎にも迫る原作ファンも楽しめる王朝推理絵巻です!
道長の有名な「この世をば・・・」の和歌の月と、香子(紫式部)の道長の晩年を予知する月の満ち欠けの儚さの表現、そして若菜上の栄華と若菜下の対比的表現が見事で源氏物語の精神世界とその時代の宮廷の人間模様を視覚化出来る面白いシリーズで源氏物語マニアには特にお勧め!
あとがきで有る様に宇治10帖の続編がいつか書き上げられる事を楽しみにしたいと思います!
小生は新装版ではなく2015年7月17日初版の文庫版!
千年の黙の続編だが内容は紫式部日記を膨らませた王朝推理ミステリーで、これまでの登場人物も成長した形で生き生きと登場しワクドキです!
新たな登場人物も紫式部と関わる有名どころが沢山出て来て平安好きにはたまりません!
巻末にはきちんと参考文献も記載され、あとがきで作者が言う様にこの時代のゴシップを題材に巧く格調高い小説として膨らませた様を感じます!
細谷氏の解説も作者の伏線の張り方の見事さと和泉式部等の個性ある登場人物の生かし方も絶賛な作品です!
少し現代風な表現もありますが、この時代の人々の生活や想いが、様々な出来事や事件が絡み合い解けていく中でリアルな映像として浮かび上がってくる作品です!
特に一条帝の定子一族の哀しさが巧く作品に表わされていて平安時代好き・平安文学好きな人は楽しめる作品です!
光源氏でなく宇治十帖の薫と匂宮を主人公(薫が主体)に設定し平安京を舞台に様々な事件で現れる悪霊や物の怪達に対し、凄腕没落陰陽師の力を借りながら対峙し事件を解決していくダークな雰囲気を醸した三巻に及ぶ連作小説。
薫が凄く良い人に描かれていて個人的には不満だが、今に通じる人間の複雑な心理も描いており悩みや苦しみから解放される姿に感銘を受ける面白さがある!
壱巻
薫の出生の秘密や匂宮の性格等原作の面白い所を巧く生かして中身の深い人間模様を描いており原作ファンも愉しめます!
所々源氏物語初心者でも判る原作エピソードや有識故実の説明的話も違和感なく物語に溶け込んでいます。
現代的言い回しもありますが「妖説」の名の通り怪しげな物語も楽しめるエンターテイメントな小説です!
弐巻
平安京を舞台に様々な奇怪で妖しい死霊や術に対し、凄腕没落陰陽師(その祖父が良い味出してる)の力を借りながら陰陽道の術や機転で解決していく妖説な源氏物語の続編!
登場人物の悲しい過去と対峙し奇跡を起こす「蛇酒」、薫の意外な人物から知る光源氏の闇と因果応報「藤壺」、平安時代の暗い現実世界と薫と八の宮の出逢いを描く「宇治の闇」、賭博が大流行したこの時代に、博徒たる匂宮が行った雙六(すごろく)大勝負の顛末「魔の刻」と、どれも其々切り口が違っていて、平安時代の闇も描いており面白い痛快創作小説です!
参巻
平安時代のしかも源氏物語の薫と匂宮の人物設計を飛躍させ魑魅魍魎と陰陽術が交錯する妖しく痛快な創作小説の完結編!
あとがきで作者が述べている様に原作の橋姫~椎本巻のエピソードを膨らませ薫と匂宮の友情を軸にとても怪しげで面白い物語にしています!
陰陽師の術力で柏木に逢い実父の想いと対峙する事で母である三宮への蟠りが消えたり、その他にも色々と飛躍はしていますが、仏教への信心・大君との恋・出生の秘密等の原作の内容を巧みに昇華させており、怪しげな物語と共に愉しめます!
又、作品内には原作で詠まれた和歌も散りばめられていて原作ファンも楽しめます!
小生は新装版ではなく2015年7月17日初版の文庫版!
千年の黙の続編だが内容は紫式部日記を膨らませた王朝推理ミステリーで、これまでの登場人物も成長した形で生き生きと登場しワクドキです!
新たな登場人物も紫式部と関わる有名どころが沢山出て来て平安好きにはたまりません!
巻末にはきちんと参考文献も記載され、あとがきで作者が言う様にこの時代のゴシップを題材に巧く格調高い小説として膨らませた様を感じます!
細谷氏の解説も作者の伏線の張り方の見事さと和泉式部等の個性ある登場人物の生かし方も絶賛な作品です!
少し現代風な表現もありますが、この時代の人々の生活や想いが、様々な出来事や事件が絡み合い解けていく中でリアルな映像として浮かび上がってくる作品です!
特に一条帝の定子一族の哀しさが巧く作品に表わされていて平安時代好き・平安文学好きな人は楽しめる作品です!
1996年10月11日初版第1刷 笠間索引叢書 笠間書院
源氏物語夢浮橋の鎌倉時代に創られた擬古文の続編「山路の露」の本位田氏蔵本と東海大学蔵本を本文とし対校として承応板本を右に付し、読み易くする為かなや常用漢字濁点句読点等を付しています。
又、自立語・助詞・助動詞の総索引は言葉の研究にはうってつけです。 巻末の文章に関する論は本作の源氏物語の時代との文章表現の違い(名詞より動詞が多い等々)、あえてその時代に似せようとしている文章表現の指摘や解説があり興味深いです!
作者ではないかと言われている「建礼門院右京大夫集」からも例も取り上げ研究には欠かせない書籍です。
2003年刊行の作品の文庫版は2009年6月12日初版 東京創元社
第13回鮎川哲也賞受賞の王朝推理小説で森谷明子氏のデビュー作!
しっかりと平安時代の有識故実と、道長を巡る時代背景を描いていて、源氏物語原作ファンやその時代のファンも愉しめるミステリーエンタテイメント王朝作品です!
宮中の様々な出来事を題材に、「かかやく日の宮」「雲隠」等の謎に迫ったり、重陽の節会等々の儀式や、式部の呼び名の変化や、耳はさみ等の庶民の姿や女房の生活をもリアルに描いています!
式部の夫の藤原宣孝とのあったかい愛情あるやりとりや会話、藤原実資の、らしい関わり方等々も含め、源氏物語と平安時代をしっていると更に、3篇全て愉しめます!
サントリーミステリー大賞読者賞を受賞した源氏物語と紫式部を素材にしたエロチックでグロテスクな表現のスリラー要素の強い小説です!
紫式部と源氏物語の登場人物が同じ世界に存在しているところから吹っ飛んでいますが設定等違和感なく読み進められます。
紫式部と頭中将が殺人事件を追い推理するサスペンスミステリーで、源氏物語の中の桐壺更衣から葵上までの死を、新しい視点で殺人事件として巧く創作しています。
謎が謎を生み犯人を追う仕立てがハラハラドキドキします!
源氏物語の人物造形を巧みに活用し人の欲望の哀しさをも表現している様に思います。
源氏物語を知っていると更に愉しめるミステリーです!
逆にコアなファンはキャラのイメージが↓かも!
女性週刊誌風に源氏物語をまとめた源氏物語を解りやすくまとめた面白い本(雑誌?)です。
見出しが「光源氏、火遊びの「方違え不倫」!?」「見た!平安のロミオとジュリエット」「玉鬘驚愕レポート!」「ブリブリ三の宮にブーイングの嵐」等々正に女性週刊誌、内容も源氏物語の筋に沿っていて写真やイラストも凝っており、スクープ満載です(笑)
元々恋愛沙汰や政治的な失脚・返咲き等てんこ盛りの物語なので、美味い所に目を付けた書籍だと思います。
広告も凝っていて、物語内の儀式や調度、楽器・香等の広告が笑えます。
様々な登場人物へのインタビューや手記も、その人物の個性を表わしていて面白いですし、架空の案内やお知らせ等パロディも効いています。
裏表紙には日ペンの美子ちゃんのパロディの紫の式部ちゃんのカラー広告も有り笑えます。
全体源氏物語の内容や筋にもあっており、源氏物語を多角的に捉える良い参考書ともなります。
A5新装版も有る様ですが希少です。
続編的な宇治十帖編もありますがネットでもなかなか手に入れる事が出来ません。
下記、源氏物語の偽作以外にも、江戸時代中期成立らしい菅原道真の流罪の様を描きそれっぽく創作された「菅家須磨記」、鎌倉時代成立らしい老尼となった清少納言の旅行を描いた「清少納言松島日記」は割と清少納言を研究された部分が多い創作、江戸時代成立の軍記「吾妻鑑」を基本に源平合戦の様々な軍記をはめ込んだ「盛長私記(抄)」は今回の本書巻末の解説でも論を立てるほど、偽書ながら広く愛読されたそうです。
藤原為家の側室・阿仏尼によって記された紀行文日記「十六夜日記」を大幅に書き換えた室町時代成立らしい「阿仏東下り」、江戸時代初期成立の吉田兼好伝記のひとつで徒然草からの抜粋が多々ある「兼好諸国物語(抄)」等も愉しめます。
責任編集:千本英史 2004年8月31日初版1刷発行 現代思潮新社
古典文学の偽書7作を原文と脚注で読める面白い本です。
各書冒頭に概要・成立・諸本の解題があり参考になります。
付属のブックガイドに、偽書とは、日本書紀に代表される様な歴史書や古今集・伊勢物語・源氏物語等の本文(正典・古典)を注釈や解釈を不断に行い奇妙な由緒来歴を盛り込みアンソロジーとしての作品を創り上げたもので、その作品への愛情と自分の理解との試しとしての部分(本居宣長の「手枕」)等と、内容を創作する事で王朝の正当性を左右しようとする意図(中国の魏普南北朝や日本の南北朝時代)等があるとあります。
付属の月報には源氏物語研究者の三田村雅子教授の「偽書の中の源氏物語」と題する寄稿もあり大変参考になりました。
鎌倉時代成立ではないかと言われている夢浮橋の続編「山路の露」は、文体も表現も本文(正典)を引き継いでおり様々な本文に登場した人物や出来事が巧く引き継がれており、和歌も詠みぶりが原作らしい味を出しており、源氏物語への深い愛と研究熱心さが溢れていて源氏物語愛好家に好意的に享受されたのではないかと思います。
しかし結局、浮舟と母との再会や薫との再会はあるものの関係は進展する事無く原作の抑制された愛を描いて終わります。
室町時代成立と言われる「雲隠六帖」は、雲隠の後と夢浮橋の後を描いていますが浮舟はまったく脇役で、光源氏とその周辺皇族及び匂宮の王権を描いた政治的な物語で「山路の露」も参考にしている趣がありますが文学的な匂いは薄いです。
紫上が様々な形で現れ匂帝の中宮(中の君)が紫上の面影に似ていた等の意味づけ等新たな形代物語を呈しています。
「山路の露」が雅やかで文学的なのに比して「雲隠六帖」は王権確信の為の材料としての源氏物語解釈としてとれます。
就職試験を58社続けて落ち彼女にも振られた二流大学出身の主人公が、ひょんな事から平安時代のしかも「源氏物語」の世界に次元移動タイムスリップし、アルバイト先で配られた『源氏物語』のあらすじ本を活用して凄腕陰陽師として、その世界で自分の存在価値を見出し成長するユーモアとペーソスに満ち溢れた小説です
光源氏という超一流の弟に愛情を持ちながらも劣等感を持つ朱雀帝に己を重ね、帝とその母である弘徽殿女御の右大臣派に肩入れして行きます
この弘徽殿女御の描き方が素晴らしく、源氏物語を元に創作された様々な小説や映画・漫画等の描き方・扱い方に苦々しい思いをして来た弘徽殿女御ファンにとっては爽快な扱い方です
さながら現代のキャリアウーマンの様な、いやそれ以上な強さと野心を持ち、しかし魅力に溢れた人物像に描いていて大変楽しく読めました
その弘徽殿女御に気に入られ徐々に自信を得て重要な場面で物語に関わっていく事で「自分」を獲得して行く主人公が圧巻です
平安時代の習俗や風習・自然の美しさや情感等も、日々の何気ない生活を克明に描く事でその時代を読みながら体感する事が出来、源氏物語が好きな人にとっては平安時代や源氏物語の世界のイメージを深める事が出来ます
あらすじ的な内容や習俗についても源氏物語の筋に沿って進む為、主人公と一緒に源氏物語の面白さを知る事が出来ます
源氏物語の描く生きる意味や無常・哀しさ・喜び・愛おしさが現代人である主人公の目を通じて散りばめられており、笑いあり歴史ありペーソスありのエンターテイメント作品となっています
内館牧子氏の小説家としての力量をとても感じました
小生は久々に小説を読んで泣きました!
源氏物語を描いた小説や漫画の中でも現在一番の作品となりました!
巻末にはあとがきと参考文献、文庫版には加えて内館牧子氏の恩師の仁平道明東北大学名誉教授の素晴らしい解説文が寄稿されています
「新・紫式部日記」で日経小説大賞を受賞した作者の新作
「夢浮橋」に続く幻の一帖を巡り様々な思惑や謀略が渦巻く中その時代の有名どころが数多登場する史実を織り交ぜながら創作された王朝文学ミステリー小説で大変面白いです
主人公はあの更級日記の菅原孝標の次女・菅原孝標女(むすめ)で源氏五十五帖探索の旅での苦労や人との縁を通じて成長し源氏物語好きの若き乙女から凛とした作家として「夜半の寝覚」に繋がって行くストーリーが秀逸です
登場人物も紫式部の娘の賢子や一条帝と定子の娘宮修子内親王も登場し平安時代好きにはたまらない設定です
源氏物語・更級日記・御堂関白記等のこの時代の物語や日記を知っていればとても面白く読めます
山本淳子教授の「源氏物語の時代―一条天皇と后たちのものがたり」等の本で、この時代特に一条天皇と定子そして藤原道長の関係性や伊周事件等々の様々な史実を知っておれば更に深~く楽しめます!
平安時代の史料や史実・その時代の文学や習俗をしっかり調べたうえで、それをベースにして籐式部(紫式部)が関わった人々との人間模様や、源氏物語執筆の元になった様々なエピソードを散りばめながら、読み応えのある小説として創作した宮廷物語としても楽しめる日経小説大賞を受賞の作品です。
藤原道長や彰子との関りがドラマチックで、一条帝の時代やエピソードと源氏物語世界を知っていると意外な展開に心地よい想像や読書の愉しさを味わえます!
石山寺がこの物語の中で重要な位置を占めており表紙カバーに名品である石山寺所蔵土佐光起筆「紫式部図」を配しているのも本の品位を上げていて成功しています。
源氏物語を愛する人は更に人間ドラマとして深められ、とっても愉しく読める創作小説です。