〜 Caffe de OTTAVA 〜 1
- 2019/10/04 13:01:21
投稿者:エフェメラル
OTTAVAには 2014年から続くメルマガがあります
現在のメルマガは写真入になりましたが お知らせだけになり面白みがありませんが 過去のメルマガにはプレゼンターさんのコラムが載っていました
メールの整理も兼ねて こちらには今読んでも面白いと思われるお話を 暇な時に少しずつ転記していこうと思います
メルマガの号数は上になるほど新しくなりますが コラムの文字数が多いので読みやすいように 一つのコラムは上から順番に読めるようにしています
また罫線の種類で 書かれたプレゼンターさんの区別がつくようにしています
本田聖嗣さん
********************************************
高野麻衣さん
==================================
森雄一さん
----------------------------------------------------------------
林田直樹さん
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ゲレン大嶋さん
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
古いコラムになりますが 楽しんでいただけたら幸いです
*こちらの掲示板は大変申し訳ありませんが コメントなしでお願いします
記事について お話したい時は「お話しましょう♪ (雑談板)」を使ってください



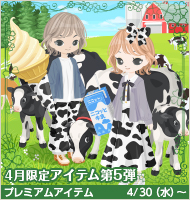











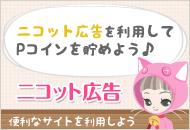
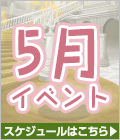








2015.03.18号
********************************************
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 by 本田聖嗣
第8回目 「楽譜を書く場所は選べ?」
このコラムは、「生放送ではお届けできないユーモア」などを書いてゆこうと当初思って書き始めたのですが、
どうも最近、真面目に書きすぎているような気がしてきました。なので、今回は少し気分転換を。
クラシック音楽において、存在感があるのは、やっぱり作曲家で、古い時代は、それらのたいていの人が優秀な演奏家や
指揮者を兼ねていたはずですし、近代以降では、作曲もする優秀な演奏家・・もたくさんいるのですが、
やはり「作曲家優位」は変わらないようです。それだけ、作曲という行為は創造性のある仕事です。
コレクションの多いことで知られるロンドンの大英博物館には、クラシックの有名作曲家の自筆譜がいくつも所蔵されていて、
私も現地で見て感激しましたが、そこにそのうち「カラヤンの指揮棒」とか「ミケランジェリのピアノ」が展示される・・
とはちょっと考えにくいので、これから先も、クラシック音楽界のお宝、といえば、有名作曲家の自筆譜、ということになりそうです。
ベートーヴェンは、クラシック音楽を代表する作曲家ですから、彼の自筆譜は、世界各地の美術館などの重要所蔵品になっていますが、
その特徴は、なんといっても「悪筆」なこと。ぐちゃぐちゃに書いて読みにくいところもあれば、いったん書いたものを
乱暴に消した個所もあり、筆跡が「殴り書き」に近いために、アクセント記号(意味:その音だけ大きく)なのだか、
その長い形であるディミヌエンド(意味:だんだん小さく)なんだか判別困難なもの、繰り返しを書くときに省略したと思しき
なぞの空白、など、楽譜編集者泣かせの自筆譜がたくさん残っています。
良く、「天才モーツアルトは、頭の中ですでに音楽が完璧に出来上がっているため、自筆譜はいつも清書したかのようにきれいで完璧だ」
といわれるのですが、モーツアルトはともかく、ベートーヴェンの楽譜に比べたら、誰の楽譜だって「清書したようにきれい」に見えます。
でも、耳の疾患で聴力を失いつつも、理想の高い市民作曲家として作品を量産し続けたベートーヴェンの情熱には、頭がさがります。
映画「敬愛なるベートーヴェン」の中に、「俺は神の音楽が聞こえているんだ。それを楽譜に書かなきゃならん、それが俺の使命なんだ。」
というセリフが出てきますが、ほぼそんな気持ちだったと、思わせるような、自筆譜の「殴り書き」具合です。
その情熱あふれるベートーヴェンは、思いついたらすぐ作曲するということをしていたために、時として、
「紙以外のものに楽譜を書く」癖がありました。片付けの苦手な男やもめ一人暮らし、ということもあったのでしょうか、
楽想がわくと、手当たり次第に楽譜を書いていったため、家(といっても借家です!)の中すべてに楽譜を書きつけていった、とも伝えられ、
それが原因で大家ともめて、引っ越しを余儀なくされた・・らしいのです。ありそうな話です。
でも・・そんな「家中に楽譜を書くベートーヴェン」でも、ただ1か所、楽譜を書きつけなかった箇所があるのです。
それは玄関の扉。
友人たちが、「ベートーヴェン、君の素晴らしい音楽を手元に置いておきたいから、何か、自筆の楽譜が書いてあるものをくれないかい?」といった時に、
作曲中で上の空だった彼は、「いいから、なんでも持って行ってくれ!」と適当に答えたために、なんと楽譜が書かれていた玄関の扉を持って行ってしまい、
さすがに不用心極まりない部屋と成り果てたため、それ以降、玄関の扉にだけは決して楽譜を書かなかった・・・という話が伝わっています。
半分は創作かもしれませんが、紙の五線紙以外にたくさん「楽譜」を残したベートーヴェンですから、半分は、本当の話です。
でも、博物館に「ベートーヴェンが楽譜を書きつけたアパートの壁の一部」が展示されることも、なさそうです。
********************************************
第8回「いとしきロココ」 高野麻衣
2月にスタートした国立新美術館「ルーヴル美術館展」。すでに2回も訪れてしまいました。
副題は「日常を描く——風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄」。16世紀から19世紀半ばまでのヨーロッパの人々の暮らしを覗き見るような展覧会です。
眺めていると、どうしても女性の肖像に惹かれる私。たとえばフランソワ・ブーシェの名作『オダリスク』。
薔薇色の肌とブルーグレーのシーツ、ロイヤルブルーの掛布のコントラストが夢のように美しい。
絨毯や調度のカラリングも、そのまま部屋に置きたいようなスタイリング。
エロティック、不道徳という異性の観点でばかり語られがちなロココの風俗画ですが、女子的にはいとおしいことこの上ありません。
クープランやマラン・マレの音源をふんだんに使った音声ガイドはもちろん、ミュージアムショップでも散財してしまいそうなのでご注意を!
芸術は日常であり、日常こそが芸術。こういうロココ的空間をこそ愛していきたいと、あらためて。
http://www.ntv.co.jp/louvre2015/
==================================
※古い記事ですがリンクしてある国立新美術館「ルーヴル美術館展」のHPが今でも見られましたので載せてみました
この美術展は私も見に行ったような気がします
2015.03.11号
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
「人生、ほぼ音楽」 ゲレン大嶋
第7回「音楽の力」
当時の自分のブログを見ると、2011年の3月9日に、私は、まだ活動を始めて間もなかったココムジカの4回目のライヴを、
4月10日に行うことを告知する記事を投稿しています。その2日後、あの大震災が発生しました。
エンターテインメント系のイベントが次々と中止になる中、葛藤もありましたが、チャリティー・ライヴにすれば、
お客さんも来る気持ちになってくれるのではないか?と思い、3月19日に改めてその旨を告知しました。
その結果、4月のライヴには、被災地出身の方、親戚やお友達が被災したという方も含めて、小さなお店に入り切れないくらいの
みなさんに集まっていただき、おそらくお客さんもそうだったと思うのですが、我々演奏する側も、いつもとは少し違う気持ちで、
音楽があることの意味をしみじみと感じながら、特別な夜を過ごすことができたのです。
その後も、「できることを」と思い、小さな規模ではありますが、チャリティー・ライヴを重ねていき、
また、レコーディングしたばかりのココムジカの音源をチャリティー・コンピレーション・アルバムに提供するといったことを続けました。
一方、テレビでは、有名芸能人や有名歌手などが被災地を訪れしている場面がひんぱんに放送されていて、姿を見せるだけで、
想像もできないくらいつらい状況にあるはずの被災者のみなさんを笑顔にしてしまう彼らの存在は、それだけで価値があると思いました。
私も、以前何度かお世話になった被災地のコンサート・ホールのみなさんや、訪れる度に毎度おいしいお料理を振る舞ってもらった
民宿の女将の無事が確認できてから、彼らのもとに音楽を届けたいという気持ちが湧きあがりましたが、
誰も知らないココムジカが、誰も知らないオリジナル曲を演奏したところで、被災者のみなさんの笑顔にはつながらないのでは・・・
という躊躇がありました。
しかし、しばらくすると、ミュージシャンや音楽関係者のSNSで
「ミュージシャンのみなさん、とにかく演奏しに行くことです。被災地には音楽が必要です」といった内容のメッセージが飛び交うようになり、
その言葉に後押しされるようにフリー・ライヴをしに行くことにしたのです。
そして、2012年の1月、現地でボランティア活動を行っていた知人たちの協力もあり、まだまだ震災の爪痕も生々しい
宮城県の七ヶ浜町と石巻市で小さなライヴを行うことができました。
実際に被災地の状況を目の当たりにすると、今ここで演奏をすることに意味があるのだろうか・・・と、
また不安が襲ってきたのですが、とにかく普段通りのライヴをしようと心に決め、そして、いざ演奏を始めると、
小さなお子さんから大人まで、みなさんがみるみる笑顔になっていったのです。
ほとんどの人たちが一度も聴いたことすらなかったはずの私たちの曲なのに。
音楽の目に見えない力を感じることは、音楽を愛している人なら、きっと人生の中で幾度となくあると思います。
私ももちろん、一音楽ファンとして、そして音楽家として、そんな不思議な力に動かされてきたのですが、
この時のライヴでは、それまでに感じてきたものとはまた違った力を感じることができた気がしました。
音楽を届けるつもりで行ったのに、こちらの方が大きなものをもらって帰ってきたのです。
音楽って素晴らしいですよね。これからもOTTAVAの放送を通じて、その力をリスナーのみなさんと共有して行きたいです。
そして、また東北にも演奏しに行きたいと思っています。東北のみなさん、その時にお会いできれば!
2015年3月11日
ゲレン大嶋
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
2015.03.04号
---------------------------------------------------------------
進化する音楽 音を楽しむって素晴らしい
第七回「ゲーム音楽について2」
前々回のメルマガで、ゲーム音楽について書きました。
そして、ゲーム音楽をオーケストラで奏でるコンサートがあることについても記しましたが、覚えてますか?
一体、どんなものか気になったので、取材してきました。
2月7日(土)、五反田のゆうぽうとで行われた、JAGMOによる「The Legend of RPG 伝説の交響楽団」という名のコンサート。
JAGMOは、「ジャパン・ゲームミュージック・オーケストラ」の略で、その名の通り、ゲーム音楽を専門に演奏するオーケストラです。
音楽監督を務め、指揮も担当するのは吉田誠さん。今年のLFJにはクラリネット奏者として出演するイケメン音楽家です。
間に休憩を挟む、第1部から第5部まで、2時間ほどの演奏はとても素晴らしく、すべてのプログラムがゲーム、ゲーム、ゲーム。
満員のお客さんの面々をみると、おそらくクラシック音楽にはあまり縁のないような若者ばかり。
そんな彼らがこのコンサートに足を運ぶのは、それぞれが愛するゲームの音楽を、オーケストラで奏でられるから。
ポケットモンスターの冒険曲メドレーから始まり、ポケットモンスター戦闘曲メドレーと続きます。
私も多少、ポケモンはやったことがあるので、聞こえてくるメロディにいきなり心が躍りました。
概して、短い楽曲ばかりなので、それをいかにアレンジして、メドレーとしてつなげていくのは、大変な作業だと思いますが、
それをやり遂げるのは、編曲者がすばらしい面々なのでしょう。プログラムを見ると、編曲者が9人もいました。
「クロノ・トリガー」、「キングダームハーツ?」、「ロマンシング・サガ3」、「ファイナルファンタジー」と、
やったことがなくても、一つや二つ、名前は聞いたがことがあるでしょう。
全般通して、打楽器と管楽器の存在感が際立ってました。そもそもRPGの楽曲は力強くドラマチックなものばかりで、
インパクトを出すにはこれらの楽器が適任ということなのでしょう。
今回は2日間の公演でしたが、「The Legend of RPG」は1年かけて続けられたシリーズ公演で、その締めくくりとなったのが本公演。
これまで、ドラゴンクエストを取り上げたり、ドヴォルザークのようなクラシックの楽曲も演奏に加えたり、編成も室内楽、
管楽器主体のものだったり、聞く者を飽きさせない工夫も毎回みられます。
JAGMO所属のアーティストは概して若く、そんな若き有能なアーティストをリクルートするのは、JAGMO代表の泉志谷忠和氏。
ゲームをプレイしている世代のお客さんが多いのだから、演奏する側も同世代にしたいというこだわりがあるようです。
次回公演は7月。「伝説の戦闘組曲」というタイトルが発表されていますが、どんな選曲になるのか、そしてJAGMOの今後の目標など、
近く、番組ゲストとして泉志谷さんをお招きしたいと思っています。
ちなみに、今回、コンサートを拝見して、会場でいただく資料の中に小さな冊子があり、それはなんとゲーム音楽コンサート情報のフリーペーパーでした。
こんなものがあったのか!JAGMO以外にも、ゲーム音楽を奏でる団体はあるのです。吹奏楽のシエナ・ウィンド・オーケストラって有名ですものね。
彼らは3月から6月まで、全国を回ってファイナルファンタジーを演奏するようです。
また、ゴールデンウィークに、東京・八王子では、4年に1度のゲーム音楽フェスまであります。
東でLFJ、西でゲーム音楽フェス「4 starオーケストラ2015」。
今年は、西にもちょっと行ってみようかな。
----------------------------------------------------------------
「ナクソス名盤落穂拾い」第7回 林田直樹
いひひひ…じゃなかった、ゴホン。
ジキル林田です。
三寒四温のこの季節、時おり春の日差しのうららかに感じられる今日この頃、皆様方にはおかれましては、
ご機嫌麗しゅうお過ごしのことと存じ上げます。
あの「変な曲大好き」とかいう輩がインフルエンザだか花粉症だかで寝ている間に、この私が当コーナーを、
清く正しく美しい音楽の広場として、再生させたいと思っております。
やはり音楽はまっすぐが一番!
まっすぐといえばバッハ。
いつもキリリと清らかな空気を運んでくれるバッハの音楽は、やはり、私ジキル林田がご紹介させていただきたい必須アイテムと申せましょう。
昨年秋に、私のセレクションによるCD「朝バッハ」の中に、実は当初1曲でも入れたいと思って候補に考えていたのが、
ギターやオーケストラやピアノなどのさまざまな編曲版のバッハでした。
結局は諸般の事情から選に洩れましたが、その中でも特にイチオシとしてやはりご紹介しておきたいのがこのCD。
ナクソスの姉妹レーベル、マルコ・ポーロから出ているものです。
●J.S.バッハ=マルケヴィッチ:音楽の捧げもの
クリストファー・リンドン=ジー指揮 アーネム・フィルハーモニー管弦楽団
http://ml.naxos.jp/album/8.225120
昨今の古楽器演奏とは一線を画す、重厚で渋く、けれどもストコフスキーのように重々しくなく、
ヴェーベルンほど尖りすぎてもおらず、バランスよく格調高い響き。
20世紀の洗練されたオーケストレーションによるバッハを満喫できます。
オーケストラの隅々まで知り尽くしていたマルケヴィッチだからこそ成し得た素晴らしい編曲だと思います。
イーゴリ・マルケヴィッチ(1912-83)は、20世紀を代表する個性的な名指揮者の一人で、特に作曲の才能がありました。
9歳でコルトーに学び、14歳で偉大な音楽教師ナディア・ブーランジェに学び、興行師セルゲイ・ディアギレフにも一目置かれていたほど。
今後彼の仕事は再評価が進んでいくことでしょう。
そもそも、どんなアレンジだって、どんな楽器だって、バッハの「音楽の捧げもの」は特別すてきな名曲だと思います。
徹底的に繰り返され展開されるハ短調の「王の主題」はプロイセンのフリードリヒ大王から与えられたもので、
バッハの作曲技法によって高められたその威厳と神秘性は比類がありません。
「捧げもの」という考え方も美しい。
競争とか収奪とか搾取ではなく、心の恵みとなるものを、誰かに捧げようとすること——この精神的態度を私たちは見習いたいものです。
闇の中の一条の光のように、このバッハがみなさんの心に届きますように。
やはりクラシック音楽は真面目だからこそ素晴らしい。
曲がった心よ、立ち去れ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015.02.25号
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 by 本田聖嗣
第7回目 「誤植の増殖」
今回は、フランス語のダブルミーニングについて書こうと思っていたのですが、また別の脱線を
したくなりました。というのも、先日、演奏家が演奏する現代の作品・・もちろん作曲家は存命です・・・
を楽譜を見ながら聴く機会があったのですが、楽譜と違う音や、2倍のリズムで弾いているところがあったので、
疑問に思って、演奏終了後、演奏家に聞いてみたのです。
すると、「その楽譜には誤植が多いんです」とのこと。楽譜はきれいに印刷されたものでしたが、演奏家によると、
もともとは手書きの楽譜かスケッチのようなものしか存在せず、それを、誰かが清書という名の「楽譜ソフトウエア入力」
をしたらしい、そこで、入力ミスが起こったのではないか・・とのこと。
一方で、その曲は、ある楽器奏者たちが、たくさん演奏するために、演奏そのものが知れ渡っていて、
その演奏家は作曲者とは面識がないにもかかわらず、楽譜のミスを指摘することができる・・という経緯のようでした。
いずれも、現代の作曲家と演奏家のため、実名が出せずに、ややこしい記述で申し訳ありません。
つまりは、おそらく、清書、というか入力したひとが、楽器の演奏経験または、音楽の知識に乏しく、
「ただ写す」という作業だけをやったつもりが、かなり矛盾をはらんだ楽譜を作ってしまった、ということのようです。
クラシック音楽とされるものについて、特に演奏家は、「作曲家の意図に沿うように楽譜に忠実に演奏すること」
を求められますが、実は、このように、そもそも楽譜がいい加減、という例は枚挙にいとまがありません。
殴り書きの悪筆で有名だったベートーヴェンの楽譜では、多々あり、それを後世の人が丹念に分析して、
これだという「清書楽譜」をつくりあげてきた、という歴史もありますし、楽譜を書くのが面倒だったドビュッシーなどは、
新番組OTTAVA PHONICAでも取り上げていますが、極初期の録音である「ピアノ・ロール」という機械で、自作の演奏を残していますので、
楽譜上では「どーも遅すぎておかしい」と疑われる個所が、実際には本人が2倍の速度で弾いていた・・
つまり記譜上のミス・・と判明したところもあります。
後世のわれわれが自信をもって判断することもできますが、そういったものの一切ない、もっと古い作曲家の作品などでは、
楽譜の正誤を判断するのは、至難の業です。
存命の作曲家の決して長くない作品でさえ、上記のように、致命的な記譜上のエラーが何か所も発生してしまうのに、
もともと長い曲の多いクラシック音楽の楽譜では、一体いくつあるのか・・と思うと、時に、楽譜が信用できなくなる場合もあります。
たとえば、ショパン。彼の場合は、「原典版」が複数ある場合もあります。
現代でも、楽譜によって音が違うところがあり、そのどれもが正しいのです。
その背景は、こうです。楽譜出版、というのは、作曲家が、出版社に自筆譜を売って、収入を得ていたため、
ショパンはフランスとドイツの別の出版社にそれぞれ同じ曲の自筆譜を売ったのだが、その時期がずれていたために、
その間に、手を加えてしまって、「異なる自筆譜」が存在することになった・・というものです。
手を加えたら、前のヴァージョンも変えればいいのですが、上記のように、出版社に売った時点で作曲家の役割は終わり、
という時代でしたので、あとは出版社の意向次第なのです。
ショパンを責めるわけにはいきません。彼は「決して国に帰ることができないフランスに暮らす亡命ポーランド人音楽家」
だったのです。旅先で頼りになるものは、やっぱりお金。国をまたいで、複数の出版社に売らなければならなかったショパンの状況は
十分理解できますし、時間があったら、少しでも、よくするために手を加えてしまう、というのは、むしろショパンの誠実さなわけです。
複数の楽譜を開いて、「ここ音が違うんだけどなあ・・・」と思いながら、ショパン作品を演奏するのに困るとき、
私は、そんなショパンの境遇に、いつも思いを馳せてしまいます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2015.02.18号
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
「人生、ほぼ音楽」 ゲレン大嶋
第6回「八重山と台湾をつなぐ古の歌」
沖縄民謡を演奏するのに欠かせない楽器といえば「三線」ですよね。
でも、三線の元になった中国の楽器「三弦」が琉球に伝わったのは、14世紀から15世紀頃。
では、それより前の時代の琉球諸島には「民謡」がなかったのでしょうか?
いやいや、そんなはずはありません。当時ももちろん歌はあって、ただし弦楽器はなかったので、
無伴奏ないし、手拍子足拍子や打楽器などを交えて歌っていたのでしょう。
話は少し飛びますが、琉球諸島の南西部に位置する宮古諸島や、石垣島を中心とした八重山諸島は、
琉球国統一よりはるか前の時代には、沖縄島周辺とはやや異なる文化圏を形成していたと考えられて
います。
考古学者たちの研究によると、さらにさかのぼっていわゆる先史時代の宮古・八重山の文化は、
沖縄島周辺のものより、むしろ台湾島のそれに近かったとされているのです。
では、その時代の台湾島の住民たちとはどんな人たちだったのか?それは、現在も独自の文化を
継承している先住民のみなさんでした。
20年ほど前、90年代の半ばに、台湾の先住民「アミ族」の農民のディファンという老人と仲間たちの
伝統歌が、世界的に注目を集めたことがありました(エニグマの大ヒット曲『Return To Innocence』
に彼の歌声がフィーチャーされたのがきっかけでした。といえば、「ああ!」とおわかりになる人も
多いのでは?)。
当時、そのディファンを中心としたアミ族の農民コーラス隊が来日して、生で彼らのアカペラを
聴いた時、その歌声と曲の素晴らしさに受けた衝撃は、今でも鮮明に覚えています。
そして、最近、台湾の別の先住民「パイワン族」の、今度は老人ではなく、少年少女コーラス隊が
歌う伝統歌を聴いて、またまた大きな衝撃を受けたのです。
これは、ハワイ出身の凄腕ミュージシャン、ダニエル・ホーのプロデュースで、彼が伝統歌に
ピアノやギターなどによる最小限の伴奏を加えてレコーディングしたCD『TO & FROM THE HEART /
Taiwu Children's Ancient Ballads Troupe & Daniel Ho』を聴いてのことでした。
このパイワン族の伝統歌のメロディーやハーモニーには、例えるなら、花々や動物たちの色や形状、
あるいは、星空の配置といった「大自然のデザイン」が持つ、人知を超えた美しさのような、
「原初的で根源的な美」があると感じたのです。
そして、もうひとつ、私はこのCDを聴いて嬉しい発見をしました。
この作品に収録されているパイワン族の伝統歌のうちの1曲『YUQAI』が、八重山民謡の名曲
『月ぬ美しゃ』にとてもよく似ていることです。
この2曲を並べて聴けば、両者の関係性を否定するのには無理があると、誰もが感じると思います。
詠み人知らずの『月ぬ美しゃ』がいつどのように生まれたものなのかを突きとめるのは難しいこと
ですが、私は以前から、この、どうも三線で伴奏することを前提にはしていないようなメロディーは、
琉球での三線の成立よりずっと前から存在するものなのではないかと想像していました
(ひょっとしたらこのことはすでに音楽史上の事実となっているかもしれませんが)。
そして、今回、パイワン族の『YUQAI』を聴いて、本来無伴奏で歌われるこの曲こそが、やはり同じく
きっと元々は無伴奏で歌われていた『月ぬ美しゃ』の「元歌」であると確信し(順番が逆の可能性もありますが)、
同時に、古の時代の台湾島の文化と八重山諸島の文化の深いつながりを伝えてくれているものである
と強く思ったのです。音楽に国境なんてありませんよね。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
☆〜 おしゃべりなOTTAVA 〜☆
2015.02.11号
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
普段ではちょっと聞きにくい、プレゼンターへの質問をたくさんご応募いただき、
誕生したコーナー、題して「おしゃべりなOTTAVA」のお時間でございます!!
皆さまからいただいた質問をなるべくたくさん生かしたい!!と欲張った結果、
とんでもなくボリューミーな内容になってしまいました(A;´ 3`)
というわけで、おしゃべりなOTTAVAのスタートです〜(○´∀`)ノ゛
それでは、まずは6人のプレゼンター全員へインタビューしてみたいと思います♪
Q.スタジオに着いてから放送時間になるまで皆さんがしていることはなんですか?
本田☆ Facebookを書いたり、曲を選んだり、いただいたメッセージを印刷して目を通したり、
自分のPCを起動してTwitterに書き込んだり、かなりめまぐるしく動いています。
斎藤☆ 水筒に入れてきたコーヒーを飲みながら、届いているメールを読む。
ゲレン☆ メイクをし、衣装を着て、OTTAVAプレゼンターに変身します。もとい。主に選曲ですが、
リスナーのみなさんからのメールを読ませていただいたり、放送中にお腹が鳴らないように軽い食事
をしたりもしています。
森☆ ひたすら準備。Facebookやメールチェック。たった1時間しか準備時間がないので淡々と
やってます。TBS時代は早めに入ってだらだらスタッフとお話ししてました。今度のスタジオでは
何しよう。楽器でもやって肩慣らしするか。
林田☆ 選曲。
高野☆ 林田さんと打合せ
*** スタジオ入りされた瞬間から、お仕事モードに切り替わるのですね!!***
ちなみに、斎藤さん愛用の水筒は、かなーり年季が入っています。お気に入りのパートナーのようです♪
※2020年1月現在 OTTAVAに高野さんはプレゼンターとしてはいらっしゃいません
情報も当事のものですので ご了承ください
本田☆ あまりイメージしていませんでした。音楽に関することはかなりやるだろう、と思っていたので、
音楽家をイメージしていましたが。
斎藤☆ 落ち着いた、物静かな大人(なれなかった)
ゲレン☆「小さい頃」というのを仮に9歳までとすると、それまでにに思う将来像というのは、
「プロ野球の選手」とか「電車の運転手」といった「職業」ではないでしょうか?
「どんな風な大人になりたいか」というようことを考え始めたのは、10代も半ばにさしかかってから
だったと思うのですが、その頃には、偽善的なものに対する強い反発心を持っていました。
なので、偽善のない大人になりたいと思っていた、と言えるかもしれません。
森☆ 早く年をとりたかった。(40代があこがれで、まさに今が理想とする年齢かな)。
自分の父親のようにはなりたくなかったですね。男の子の父親を見る目ってこんなもんでしょう。
でも、気付けばやっぱり父親のようになっちゃってます(うざいという意味で)
林田☆ 木枯し紋次郎みたいに諸国を放浪する人になりたかった。
高野☆ プリンセスのような女性。
*** 高野さんってば可愛すぎます!!***
なんて言い訳しますか?
本田☆ すいません、かくかくしかじかで遅刻しました、ごめんなさい。と普通にお詫びして
始めるでしょう。
斎藤☆ ジョン・ケージの「60分00秒」をお送りしました!
ゲレン☆ そういう悪夢を今までに何度見てきたことか・・・。自宅でCDを聴きながら寝てしまい、
音が止まったところで、寝ぼけて「放送が無音になってしまった!」と思い、慌てて飛び起きて、
その場には無い「エアー・フェーダー」(フェーダーとはスタジオのミキサーに付いている曲を出す
つまみのこと)を電光石火のスピードで上げる動作を、空中でしてしまったことすらあります。
それはさておき、1時間遅刻してしまったら・・・そうですね、それまでの1時間にノン・ストップで
かかっていた曲をまとめて紹介して、何事もなかったかのようにしれっと番組を進行しちゃおうかな。
森☆ 番組のオープニングは、ベートーヴェンの第九をフルで聞いていただきました(汗)
林田☆ 震災の時以外は遅刻したことないので、想像がつきません。正直に詫びるだけです。
高野☆ ごめんなさい!
*** ゲレンさん!!その場に立ち会いたかったです(笑)***
お聞かせください。
本田☆ 物心ついたころには、ピアノを始めていたので、始まりはよく覚えていません。
音楽が好きそうだと両親がピアノを始めさせてくれたのですが、2番目の先生が、作曲科のご出身で、
楽しかったので、やめないで続いたようです。自分で音楽をピアノとは別に聞くようになったのは、
中学頃からでしょうか。
斎藤☆ 子供のころからラジオが好きだったみたいです。この世界に入るきっかけは大学2年生の時、
ラジオの制作会社のアルバイトを始めたのがきっかけ。すっかり制作現場が面白くなって、学校を出ても
就職せずにラジオの仕事を続けていて・・・・・・・今に至る。音楽は真面目に勉強していた時期もありますが、
基本的には素人です。
ゲレン☆ 父親が膨大な数のクラシックのLPを持っている、いわゆるコレクターで、小さい頃から私の家ではいつも
クラシック音楽が流れていました。また、担任の先生がカーペンターズを聴かせてくれたのも強く印象に残っています。
自発的に音楽と向き合うようになったのは、年上でミュージシャンの従弟がザ・ビートルズを教えてくれてからでした。
それから、ラジオから流れてきた喜納昌吉&チャンプルーズの『ハイサイおじさん』に衝撃を受けたことも、
現在の私の音楽に大きな影響を与えていると思います。中学生の時には初めてのギターを手にして「耳コピ」での練習を重ね、
高校生になると自分で曲を作るようになりました。最初は、イギリスやアメリカのロックやポップスをお手本に
したような曲を試作していましたが、もっと自分らしい表現ができないものかと思い始めていた頃(今から四半世紀ほど前)
に手にしたのが三線でした。始めのうちは沖縄民謡のCDを聴いてコピーすることでおおまかな奏法を身につけたのですが、
すぐに「この魅力的な響きの楽器を生かしつつ、自分ならではの音楽を作りたい」と考えるようになりました。
それ以来、TINGARAやチュラマナといったユニットでの試行錯誤を経て、ようやく現在のcoco←musikaの音楽に至りました。
その後、タレント事務所に所属して(正確にはスクール生)、2000年4月よりタレント活動に入りました。
基本はラジオDJなので、オーディション受けて落ちて、たまに受かっての繰り返し。何とか生き延びてます。
林田☆ 音楽は完全に趣味で、ピアノも独学。一番弾けた頃はショパンの葬送行進曲とか、ラフマニノフの
嬰ハ短調の前奏曲とか、ブラームスの作品117の間奏曲くらいまで。あとはシューベルトやシューマンの
歌曲のピアノパートだけを好んで弾いていました。いまは全然弾けませんが。
私にとってクラシック音楽とは、人に隠れてこっそり楽しむ自分だけの世界でした。なぜなら、
クラシックを聴いているというと一般の学校では変人扱いされたからです。
またクラオタの集まりは苦手だったので、そっち系のサークルには行きませんでした。むしろ音楽と
隣接する分野の勉強ばかりしていました。文学とか歴史とか演劇とか美術とか。この世界の仕事を
するようになったきっかけは、1987年に音楽之友社に運よく就職することができたからです。
楽譜や単行本、音楽雑誌の編集にたずさわってきたことが今につながっています。
高野☆ 7歳のクリスマスにモーツァルトに出会い、恋に落ち、おねだりしてピアノと声楽を習いました。
CDやコンサートも少しずつたくさん聴きました。十代のころにはその背景の歴史が大好きになり、書くほうが
得意だったので史学科へ進学しました。卒業後は化粧品メーカーに就職しましたが、ラ・フォル・ジュルネに出会って
音楽業界へ舞い戻り(?)ました。
*** 林田さんの歌曲の伴奏...なんだか新しい世界が見えちゃいそうです♪声楽科出身の小林より ***
本田☆ 英語とフランス語は、実用になっているので、次はドイツ語かな・・とおもっています。
一応、ドイツ語と中国語とロシア語とイタリア語とスペイン語なぜかアラビア語は、N○Kのテキストを買って、
思いついたときに、勉強していますが、1日坊主です。
それでも、TBS時代のOTTAVAルームにメキシコの方がいらっしゃったときは、挨拶ぐらいはスペイン語でできました。
ドイツ語は芸大で専攻していたので、読んだり文法は知っているので、話せるようになりたいのです。
斎藤☆ もちろんイタリア語。コトバが歌っている感じがしますよね?
ゲレン☆ 最近では、日本語も怪しくなってきているので(特に固有名詞や漢字の忘却・・・)、外国語の習得どころではありませんが、
ブラジル音楽が大好きなので、ポルトガル語ができればな、とは思います。でも、現実的にはやっぱり英語ですかね。
森☆ 外国語は興味なし。あえて言えば出身地の北海道弁。中途半端に話せますが・・・・
かつて政府観光局に勤めていて、外国に行って日本の宣伝をするんだと意気込んでましたが、いざ働いてみると
日本がより素晴らしい国であることに気付き、日本で骨を埋めようと思った次第です。
林田☆ フランス語。響きが好きだから。
高野☆ フランス語です。音楽のように聴いているだけでうっとりするから。
*** 本田さんは多彩な才能をお持ちですね。社内では時折、本田先生によるPC講座が開かれたりするんですよ! ***
高野さん♪( ´艸`)
Q.モーツァルト好きな高野さんですが、高野さん的なモーツァルト・ベスト3はどの曲ですか?
●とてもとても迷いますが、「恋とはどんなものかしら」と「アヴェ・ヴェルム・コルプス」とヴァイオリン・ソナタのK.371。
Q.5人の他の男性プレゼンターのなかで、理想の上司にしたいのは?
●上司といえばGMでしょうか。でもお話していてくつろげます。
Q.5人の他の男性プレゼンターのなかで、恋人にしたいのは?
●みなさんです。
Q.5人の他の男性プレゼンターのなかで、お父さんにしたいのは?
●みなさんお若いのでお父さんはないですが…やっぱり林田さんはファミリー感(?)があります。師匠かな。
Q.高野さんは、月〜金の各プレゼンターさんの中で、誰が一番好きですか?あるいは、嫌いですか?またその理由も教えてください。
なんて、答えられないですよね?ということで、各プレゼンターさんの寸評お願いします。
●林田さん→熱血師匠!本田さん→趣味あいすぎです(ダジャレ以外)ゲレンさん→またのみましょう♪(メッセージ?)
森さん→いい声でアドバイスされたい!GM→変わらないでくださいね(笑)
*GM=斎藤茂さんの事です
Q.サイトーレッドは斎藤さんですか?(笑)
●違いますよ、あんな素敵な人!
Q.サイトーブラックは斎藤さんですか?(笑)
●違いますよ、あんなヤツ!
Q.斎藤さんの私生活が分かりません?ご結婚は、されているのですか?お子さんは、いらっしゃるのですか?
●マンションの25階にひとり暮らし、外車を3台持っています。4人の子供がいて、住宅ローンに追われています、
って、全部ウソ。自分の話しをしないのには、理由があるのですが・・・それは近々「Salone」で
Q.GMのお仕事を教えて下さい。
●「私は会社の何でも屋。♪la la la la,la la la la・・・・・
Q.クラリネットは、今でも演奏されているのですか?
●最後に吹いたのは20年前です。また再開したいです。
Q.好きなプロ野球チームは?
●子供のころ、若松選手(のちに監督)が家の前(札幌です)をランニングしていたのをよく見ていて、そんな彼がプロ野球に進んで、首位打者をとったりして、
あこがれの人になりました。そんなわけでスワローズ。以前はよくガラガラの外野スタンドで、ビールを飲んでいたんですよ。
30年くらい前ですけど。
Q.変な曲推進委員会?委員長の林田さんが、今までに「これは変だ!!やばい!!」と強く思った曲ベスト3は何ですか?理由も教えて下さい。
●「曲じゃなくて作曲家でいいですか。1)ジェズアルド 2)ワーグナー 3)スクリャービン 3者とも、善悪の彼岸を越えているから。
Q.日曜日のDOMENICAを聴いていると、高野さんがいてとても楽しそうです。他の4人の男性プレゼンターより得したなぁ、と感じますか?
●もちろん。でも得している分、番組を面白くしていかなくてはいけない責任の重さも感じます。
Q.今、一番インタービューしたい作曲家・演奏家はどなたですか?
●作曲家に限ると、シルヴェストロフとサーリアホとラウタヴァーラとミュライユ。
本当はブーレーズなんだけど、もう年だし難しいかな。そうそう、あとシチェドリン!
Q.森さんが考える「ロックなクラシック作曲家」ベスト3は誰ですか?
●生き方がロックなのはベートーヴェン。楽曲がロックなのはワーグナー。
ロックアーティストに愛されていると思うのはモーツアルトってとこで。順位はつけません。
Q.ロックになったクラシック。森さんが、カバーしたいクラシック曲もしくは、カバーしたクラシックは、なんですか?
●もし楽器演奏できるとするのなら、グリーグの「ホルベアの時代」とマイヤーズの「カヴァティーナ」。
Q.大好きな星座は、なんですか?その理由は?
●おうし座。自分の星座だし、肉眼で見えるすばるはすばるらしい(素晴らしい)。年中見えるカシオペア座もいいですね。
双眼鏡で見ると5つの星の周辺にはたくさん小さい星が見えるのですよ。本当に癒されます。
Q.好きなプロ野球チームは?
●星野仙一が好きなので、彼が所属していた球団が基本。ただ、ビジネス面で考えると巨人。(場内MCやってました)。
最後に巨人戦の場内MCをやったのは3年くらい前かな。沢村や菅野が東京ドームデビューを果たした日も担当していて、
グランドで選手呼び込みをやった時は感動したな。やっぱり思い入れがあります。
Q.Saloneの生放送のある金曜日、どんなスケジュールで動いていらっしゃるのでしょうか?食事や睡眠はとっておられるのでしょうか?
聞いた話によると、金曜日は午前2時(!)に起きて、山梨の放送局の朝のラジオ番組のDJをなさっているとか。
ラジオ番組が終わってから東京に戻っていらして、午後には目白のスタジオに入られて準備なさって…
Saloneの時間中に眠くなってしまわれないのだろうか?と余計な心配をしております。
●放送中は眠くなりません。心配ありがとう。もちろん終われば超脱力です。
Q.「今度、ココムジカで演奏してみたい」クラシックの曲は何かありますか?
●OTTAVAリスナーのみなさんへの感謝の気持ちを込めて制作したクラシックのカヴァー・アルバム
『La Musique Classique francaise』で、ラヴェルの『ピアノ協奏曲 ト長調〜第2楽章』を始めとする大好きなクラシックの名曲を奏でてみて、
大きな刺激を受けました。いい機会があればまたトライしてみるかもしれません。
ただ、ココムジカの活動において、私は、曲を自分で作ることを大切にしているので、基本的には
今後もオリジナル曲を中心に演奏していきます。
Q.我が家では、3匹の猫がいます。ウラン、チャトラン、クロちゃんと云います。ゲレンさんの猫ちゃんのお名前は?
●ギャング(♂)とタヌ(♀)です。ダサイ名前を付けてしまって申し訳ないのですが、2匹とも大したいたずらもせず、
愛想もよく、とてもいい子たちです。
Q.おすすめのお酒は?
●盛、焼酎、ウイスキー、ラム、ワイン、日本酒、etc.・・・お酒ならだいたいなんでも好きなので、挙げるとキリがないのですが、
最近よく飲んでいるのは、宮古島の泡盛「多良川」と、シチリア原産の葡萄「ネロ・ダーヴォラ」のワイン。
「多良川」は、リーズナブルな価格帯でいながら、香りとコクは高級泡盛並。とってもおいしいですよ。
「ネロ・ダーヴォラ」は、しっかりした味のお肉料理の最高のパートナー。オーガニックのものが特におススメです。
本田さん♪ヾ(≧∀≦*)ノ〃
Q.本田さんお薦めの今すぐ使える「クラシック駄洒落」ベスト3を教えて下さい。
例:「マスネを聴いてますね。」
●今すぐ使えないダジャレばかり、羅列してみます。いずれも考えるダジャレです。
実際に「今すぐ使える」というようなダジャレは、脊髄反射で出てくるので、じっくり考えても、思い浮かばないんです。
考えると、単純な語呂合わせではつまらなくなってしまうので・・・
・クラリネットをえんそする。(ヒント:Cl)
・一覧表、商標張紙、誇大、蜂屋鳥庵。 リスト、ラベル、コダーイ、ハチャトリアン、など漢字で書く作曲家シリーズ。
・食堂「飯庵」のメニュー 「焼き鳥のカタログ」「ラーメンの幻影」・・これは芸大の学園祭の模擬店で、
作曲家の模擬店がメシアン、という名前だったので、私が考えてあげたメニュー。却下されましたが。
ピアノ科は「バックハウス」というよくわかんない名前でした。いまでも、同じ名前で出ているはずです。
Q.目白のOTTAVAスタジオは、ご自宅から近いようですが、自転車で来られているのですか?
●寒いとき、自転車では、凍ってしまいそうですから、やめてます。
Q.野球をされていたそうですが、ポジションはどこですか?
●一応、ピアノをやっていたので、本式にチームに入っていたわけではありません。がピッチングは得意でした。
Q.好きなプロ野球チームは?
●西武ライオンズ。最近弱くて困ってます。上記のように地元なので。セリーグでは巨人以外。
Q.これまでに一番緊張した演奏はどんなシチュエーションでしたか?
●やっぱり入試でしょうかねえ。落ちられない、というプレッシャーがあったので、芸大やパリ音楽院では緊張しました。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
2015.02.04号
----------------------------------------------------------------
進化する音楽 〜音を楽しむって素晴らしい〜
第六回「駅で聞くクラシック」
首都圏では、自動車やバスよりも鉄道を使うことが多いと思います。満員の通勤・通学電車に揺られ、帰りもしかり。
ぎゅうぎゅう詰めの車内にはうんざりしますが、ふと聞こえてくるメロディに癒されることもあります。発車メロディです。
無味乾燥な発車ベルがけたたましく鳴り響くのは昔の話し。
現在は、都市部に限らず、ユニークな発車メロディを取り入れているところは多いです。
有名なところでは、山手線・高田馬場駅の鉄腕アトム。同じく山手線・恵比寿駅はヱビスビールのCM曲(第3の男)。
西武鉄道は沿線にアニメ制作会社やアニメ作家も多く住むことから、銀河鉄道999や機動戦士ガンダムのテーマ曲なんかも流れています。
駅ごとにメロディが異なるなんて、ちょっと昔では考えられなかったですが、自然にいろんな音楽が身近に聞こえるようになるなんて
素敵ですよね。
では、クラシックのメロディが聞ける駅を探してみましょう。ホルストの組曲「惑星」?木星が聞こえてくるのは、
中央本線・甲府駅。
いかにも旅するぞという感じがして、通勤・通学も楽しくなりそうです。
モーツアルトが聞けるのが、常磐線の土浦駅。きらきら星変奏曲が流れます。
甲府と土浦では実際に聞いたことがあります。昼間の土浦で、きらきら星は結構、衝撃的でした。
電話の待ち受けメロディにもクラシックが使われている例は多いですね。ある役所に取材の問い合わせをした際、
例の如く、いろんな部署にたらい回しにされてイライラしそうでしたが、それを救ってくれたのが、待ち受けで流れた、エルガーの愛の挨拶でした。
他にも、同じ常磐線・いわき駅でも、シューベルトの「ます」、「楽興の時」、それにメンデルスゾーンの「春の歌」
が流れるというから驚き。一つの駅で3種類のクラシック。
駅長さんからのオーダーでしょうか。「ます」が聞こえてきたら駆け込み乗車が減るような気がしてしまいます。
発車メロディはそもそも、電車が発車するための合図なので、ジリリリという普通のベルでもいいのでしょうが、
駆け込み乗車を減らすための工夫だと聞いたことがあります。
ジリリリ・・・・だけだと、その音がいつまで続くか分からない。だから利用者は急いでしまうのでしょう。
でも、耳なじみのあるメロディだったら、初めて聞いたとしても「ここまでは大丈夫」とか、「もうすぐ出そうだから一本あとにしよう」
などと、その先が見越せるような気がします。
その土地出身のアーティストとして、有名曲を採用する例があったり、企業やお祭りのPRのために一定の時期、
別の発車メロディに切り替わったり、また、それらの発車メロディが1枚のCDになって市販されることもあります。
たまにテレビの撮影かと思ってしまうような豪華な録音セットをかかえて、発車メロディを録音している「音鉄」を見ることもありますが、
人って面白いですよね。10人いれば、その数だけ趣味やこだわりがある。
鉄道ファンでクラシック好きもいるわけで、そんなみなさんの音鉄ぶりも興味があります。
いつか、発車メロディになっているクラシックのコンピレーションCDも出してみようかしら。
----------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ナクソス名盤落穂拾い」第6回 林田直樹
近ごろ、このOTTAVAメルマガで、私の名を騙って「変な曲大好き」云々とかいう、けしからん
悪趣味を推進している不届き者がいるそうだが、嘆かわしいことだ…。
…失礼、申し遅れました。
私、ジキル林田と申します。
折り目正しく、まっすぐで純粋な精神こそ、もっとも私の心惹かれる音楽美にほかなりません。
そしてクラシック音楽には、あの大指揮者ブルーノ・ワルターも言ったように、
人を良い方向へと導く「道徳的な力」があるのです。
さて、今回の私からのオススメはこれです。
ハイドン:ミサ曲集 3 - ミサ曲第6番「聖ニコライ・ミサ」/第11番「ネルソン・ミサ」
(トリニティ合唱団/レーベル・バロック管/バーディック)
http://ml.naxos.jp/album/8.572123
まっすぐといえばハイドン。ハイドンといえばまっすぐ。
私、直樹というくらいですから、まっすぐなものは何でも大好きなので、
このコーナーでは何回でもハイドンは取り上げようと思っているくらいです。
やはり、キリリと姿勢を正すとき、清らかな空気を胸いっぱい吸い込むとき、気持ちがいいでは
ないですか!
このCDは、ナクソスの数ある名盤の中でも特に評価の高い、ハイドンの「ミサ曲全集」の分売からの
1枚。特にお聴きいただきたいのは「ネルソン・ミサ」(深き悲しみのミサ)です。
この曲の背景には雇用主とのトラブルがあったとか、戦争の時代があったとか、言われていますが、
劇的で暗く壮麗なこの曲調は、あらゆる時代において、苦悩を抱えた人々にとって、心を寄せてくれる
名作だと思います。
オーウェン・バーディック指揮のオリジナル楽器オーケストラと合唱団も力強く繊細。
そして何よりも、ニューヨーク・トリニティ教会の豊麗な響きが素晴らしい。
演奏会場もまた、楽器なのです。
ハイドンというとまず交響曲、弦楽四重奏曲の父として知られます。他に協奏曲やピアノ・ソナタにおいても、
その後の音楽形式の「基礎を作った」人物といえるでしょう。いわばファウンダー。
破壊するのは簡単ですが、その後もずっと残る基礎を打ち立てるのは、本当に大変なこと。
そしてずっと偉大なことだと思います。
あるウィーンの高名な音楽学者が言っていました。
ハイドンを軽く見ている人は、自分は何もわかっていないということを認めているようなものだと…。
どんなに複雑怪奇な現代音楽を知っていても、ロマン派が立派に演奏できても、ハイドンを大切にしないようでは、
自らの未熟を暴露しているようなものだというのです。
いつかの放送でも話しましたが、ハイドンとは料理に例えるなら、だし汁のようなものだと私は思っています。
究極の単純さにして、洗練なのです。これができなければ他の料理はできない。
静物画ともちょっと似ていますね。
ああいう基礎ができないと、前衛絵画も描けないのと同じで。
一見地味なハイドンですが、当時ハイドンほどヨーロッパ中から尊敬されていた作曲家はおらず、
あの征服者ナポレオンでさえ、ウィーンを占領した際は、病中のハイドンに気遣って護衛の兵をつけ、
ハイドン邸の前にはわらを敷き詰めて、馬車の音が楽聖の安眠を妨げないよう配慮したと伝えられます。
そしてナポレオンがパリで暗殺者に襲撃された際、ナポレオンが行こうとしていたのは
ハイドンの楽曲が演奏されるコンサートだったというエピソードもあります。
モーツァルトやベートーヴェンの陰につい隠れがちですが、実は彼らもハイドンの大きな背中を見ながら成長してきたのです。
「パパ・ハイドン」。
そのパパとは、頼れる偉大な優しい音楽上の父親という、心からの尊敬の呼び名だと思うのです。
私は、いつも心乱れたときは、ハイドンに戻るようにしています。
またハイドンについては、このページで書かせてくださいね。
ああ、それにしてもあの「変な曲大好き推進委員会・委員長」とやら…。
何とか矯正してやらなければ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
==================================
第6回「『ディオールと私』と音楽」 高野麻衣
映画『ディオールと私』試写を観ました。
ラフ・シモンズが「クリスチャン・ディオール」の新デザイナーに就任し、最初のコレクションを
発表するまでの8週間を追うドキュメンタリー。
完璧を追い求めるがゆえ君主のように振舞うデザイナーと、それを理解しながらも反撥する
職人たち。緊張と不安。しかしやがて、花々に包まれた歓喜の時がやってきます。
不協和音からすべてが調和して高まっていくフィナーレに、号泣せずにはいられませんでした。
こんなにも美しく劇的な現実があるなんて!
また、音楽がいいのです。音楽監督はマイケル・ガルべ。作曲と編曲はチェリストのハヤン・キム。
ラヴェルやThe XXといった挿入曲は、デザイナーのこだわりでもあるのだとか。
ナレーションがディオール本人、という設定もたまりません。
昨年末、銀座で行われていた「エスプリ・ディオール」展でも感じたのですが、
彼の精神——花のような女性と、絵画や音楽や、すべての美しいものへの愛はいまも確実に
息づいているのです。
すばらしい仕事映画であり、音楽映画。3月、Bunkamuraル・シネマにて公開。
==================================
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 by 本田聖嗣
第6回目 「同じ曲でも題名が変わります。」
前回は、ドビュッシーの「亜麻色の髪の乙女」の「亜麻色」が美しいか、美しくないか、
という解釈の対立を書きましたが、クラシック音楽における題名なんて、実にいい加減なもの
なんです・・・といいたくなることがままあります。
クラシック音楽、というものが、作曲家が絶対権力をふるうようになって以降
(それがベートーヴェンだなんて言っていませんよ・・・)、非常に厳密に、楽譜に忠実に
演奏されねばならず、作品番号も正しくあらねばならず、題名を変えるなんてとんでもない・・
という風潮ができました。
そのため、放送などをやっていると、曲をお届けするときに、勘違いや言い間違いが許されない
雰囲気で、それが、クラシックが堅苦しい音楽、とされる一因になっているように感じます。
でも、クラシックだって、昔は即興がメインでしたし、題名や作品番号だって、変化する・・
というかテキトーな部分も多いので、そんなに、杓子定規に構える必要はないと思います。
私は、クラシック業界の人間なので、時々、その業界の人から、「OTTAVAは曲を短くぶった切って
けしからん」といわれることがあるのですが、それが全くのナンセンスなのと一緒です。
後世から見ると、クラシック作曲家の名作は、完璧に完成して、不可侵のように見えますが、
作曲家が生きている時は、彼らだって試行錯誤しています。また、外部的要因によって曲の形態が
変わる・・・現在の音楽であるポップスなどでは当たり前ですが、クラシックだって事情は同じ
でした。
作曲家が亡くなっているため、「本人に確かめる」ということがクラシックだと不可能の場合が
多いので、どうしても自筆譜やオリジナルにこだわる「原典主義」とならざるを得ないのですが、
そこで時々問題が起きるのは、やはり、原典にブレがあった場合です。
プロコフィエフの有名な曲に、多くのCMにも使われた曲ですが、バレエ「ロミオとジュリエット」
から、「モンタギュー家とキャピュレット家」というものがあります。
通常は、この題名でよばれますが、「騎士たちの踊り」と表現される場合もあります。(OTTAVAの
アーカイブでもそうなっているものがあります。)
バレエとして上演されなかったため、しびれを切らしたプロコフィエフは形を変えて、
管弦楽組曲にしたり、10の小品を抜き出してピアノソロにしたり、と「別ヴァージョン」を
作ったからなのです。編成を変えて曲も微妙に変えてあるため、曲の題名も少しずつ変化したり・・
事実上「同じ曲」であるにもかかわらず、こういった事態が起こることもあります。
一方、オペラのアリアなどは、器楽のように個別には題名を持ちません。
しかし、有名なアリアなどは、それだけ取り出して演奏されることもあるため、やはり曲名を
必要とします。多くの場合は、そのアリアの出だしの部分の歌詞などを題名とすることが多いの
ですが、別の部分をとる場合もあります。
OTTAVAの「第2の開局記念ガラコンサート」で、テノールの与儀巧さんが素晴らしい喉で披露して
くださった、プッチーニのオペラ「トスカ」第1幕の、カヴァラドッシの最初のアリア・・
私が最も好きなアリアなのですが・・・も、プログラムでは「妙なる調和」とされていましたが、
ある時は最初の歌詞をとって「絵筆を持て」と表記される場合もあります。
これは全く同じ曲が、別の題名で呼ばれる場合です。
例を挙げていけば、きりがありませんが・・・クラシック音楽は、題名表記においても、
古いものなので、実は相当いい加減・・なことも多いのです。
OTTAVA saloneの先週の放送でもお話ししましたが、実は「いい加減さ」というのは、
文化的には、ある程度必要なことで、「クラシックだから!」といって、やたらと厳格になるのは、
音楽の幅を狭めることになるような気がします。
日本では、ドイツ系音楽がもてはやされることが多いため、厳格さがより求められているような
気がしますが、クラシックはもともとラテンの国であるイタリアの発祥、そして、いい加減な
ことでは、イタリアにひけをとらないフランスでも盛んになりました。
私の愛する「どこかちゃらんぽらんなフランス」のお話も、いずれ、書きたいと思います。
********************************************
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
「人生、ほぼ音楽」 ゲレン大嶋
第5回「ポピュラー・ミュージックとして聴くヴィラ=ロボス」
先週の「番組に連動したプレゼンターからのオススメ」でも紹介したのですが、OTTAVAリスナーの
みなさんの中でヴィラ=ロボス・ファンの人、そして、ブラジル・ポップス好きの人にどうしても
聴いて欲しいので、もう一度このアルバムのお話をさせてもらいます。
昨年末、たまたまネットで発見し、即購入。届いてすぐ開封し、CDプレーヤーに入れた瞬間から
めくるめく音世界にグイグイ引き込まれ、そのまま5回繰り返しフルで聴いた
『Um Olhar Sobre Villa-Lobos』(Mario Adnet)。
2012年にリリースされたこのアルバムは、ブラジルのベテラン・シンガーソングライターで
アレンジャー、プロデューサーのマリオ・アヂネーが、ヴィラ=ロボスの数々の名曲を
ポピュラー・ミュージックのアプローチでアレンジし、名ヴォーカリスト(エドゥ・ロボ、
ミルトン・ナシメント他)やトップ・ミュージシャンたち(ヤマンドゥ・コスタ他)とともに
演奏した作品です。
これまで私は、OTTAVAでヴィラ=ロボスについて短く紹介する時に「クラシック音楽の中に
ブラジルのポピュラー・ミュージックのエッセンスを取り込んだ作品を書いた作曲家」と言って
きましたが、このアルバムを聴いて、これは間違いで、本来は「ブラジルのポピュラー・
ミュージックをクラシックのスタイルで表現した作曲家」という言い方が正しかったのではないか、
と感じました。
聴き込むほどに、ヴィラ=ロボスが持っていただろう、母国のポップスへの深い愛と高い誇りが
ひしひしと伝わってきたのです。
一方で、このアルバムは、19世紀の終盤から20世紀の中盤にかけて形成され広まっていった、
ショーロやサンバ、ボサノヴァ、そして、それらをベースにした現代のブラジル・ポップスが
豊かな実りを得られた大きな要因のひとつが、「クラシック」の作曲家であるヴィラ=ロボスが
「ポピュラー・ミュージック」に多くの肥料を与えたことであった事実も示唆しています。
実際、彼の「インスト曲」に同時代の詩人が歌詞を付けたものも多くあり、こういった曲たちは、
古くからポップスのシンガーたちに歌われてきました。
また、この作品からは、ボサノヴァの巨人アントニオ・カルロス・ジョビンを始め、
シコ・ブアルキやカエターノ・ヴェローゾといったブラジル・ポップスの偉大なアーティストたちが、
ヴィラ=ロボスからどれだけ大きな影響を受けてきたかという「歴史」も感じることができます。
ヴィラ=ロボスの名曲をブラジル・ポップスとして現代に蘇らせたこのアルバムは、全ての
ヴィラ=ロボス・ファン、そして、ブラジル・ポップス・ファン絶対必聴の超名盤です。
日本国内盤は発売されていないので、その内入手困難になることが予想されます。
ご興味のある方はお早目にどうぞ。
※こちらをチェック! http://ottava.jp/presenter/recommended.php
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
*記事が2015年と古いので たぶんこの上のリンクは無効になっていると思いますが原文のまま載せておきます
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.15 ★ 2015.01.014号
----------------------------------------------------------------
第五回「ゲーム音楽について」森 雄一
年末や年度末になると、ゲーム商戦が本格化します。かつて、ニンテンドーDSが入手困難に
なったことがありました。転売屋がオークションサイトでのうのうと売りさばいているのを見て
腹がたったものですが、人は切羽詰まると、手に入れることが大切と、値段関係なく購入して
しまうものですね。同じことが妖怪ウォッチ製品にも起こっているようですが・・・・・
さて、家庭用ゲーム機の苦戦が報じられています。
一方、スマホでのゲームが活況を呈しているように、これまでゲームとは無縁だった女性陣を
中心に、電車の中でもカフェでも、スマホ上を指でグリグリ動かしている人を多く見かけます。
ゲーム好きのモーリーとしては、ゲーム人口が増える意味では嬉しいのですが、イヤホンつけて
ない人が気になります。というのは、ゲームには効果音なり、BGMなり、音楽がつきものだから
なのです。せっかくゲームするのなら音楽も楽しまなきゃ。
RPGでアイテムを見つけた時や、シミュレーションで作戦実行中など、アクションを取ると効果音が
流れます。マリオのゲームでコインを入手する際の「チャリン」とや、バイオハザードで敵を
撃った時の「バキュン」音、メタルギアシリーズで敵に見つかった時の「ブリリリッ(笑)」
といったものがそうですね。
一方、ゲームのオープニング画面で流れる、いわゆるテーマソングについてはいかがでしょう。
ドラゴンクエスト、モンスターハンターなど、オーケストラで演奏される壮大なテーマ曲に、
ゲーマーは心を引き締め、「よし、やるぞ!」となるわけですが、シリーズ物は特にこのような
ゲーム音楽や効果音が非常に重要な要素になっています。
冒険心を高め、恐怖感を盛り上げ、悲しみに浸る主人公に共感する・・・・
現在、トヨタの、ある車種のCMソングにモンスターハンターのテーマ曲が流れているのをご存知
ですか。知らない人にはちょっとした違和感を感じるかもしれませんが、シリーズ累計2,800万本を
売っているソフトだけに、ご存知の方の方が多いかもしれません。
私はCMを見て「おおっ!」と思ったものです。トヨタはかつて初音ミクの楽曲もCMソングに
採用していて、世界のトップメーカーなのに挑戦的な広告を打ってくるので、個人的には
イメージが非常にいいです。
映画音楽もそうですが、テーマ曲は本物のオーケストラでの演奏が多いように思えます。
中には、前回のメルマガでも触れたDTMで作られているものもあるようです。
かつての、コンピューターっぽい音楽が単音で流れるものから、現在のように進化しているの
ですから、ゲーム音楽の歴史を見るだけでも奥深さが見て取れます。
私の知り合いの、ある女性シンガーソングライターはゲーム好きで、昔、インタビューをした時に、
将来の夢はゲーム音楽を作ることとおっしゃっていました。
作曲者からすれば、誰が歌おうと、どこで流れようと、その音楽を聞いて心が動かされることが
大切なわけで、それがゲームであっても変わらないということのようですね。
大ヒットするゲームの中には、ゲームのサントラが発売されることも多いです。
CD売り上げランキング上位に入るようなものはありませんが、一部のユーザーには好評で、
自分で動画を作成する際の効果音などに利用する人もいます。
オーケストラによる、ゲーム音楽のコンサートもたびたび開かれています。
ゲーム販売に合わせたものが多いですが、特にモンスターハンターのコンサートは人気が高く、
チケットはあっという間に売り切れてしまいます。
一体、どのような人が、どのように楽しむのでしょうか。さすがにスーツやドレスを着ることは
ないでしょうが、演奏者のみなさんにしてみれば、ゲームや映画音楽であっても、クラシック同様、
しっかり練習して、お客さんが楽しんでもらえるよう、感情を込めて演奏されるのでしょうね。
一度、その雰囲気を楽しんでみたいものです。
と、こんなコラムを書いていたら、ゲーム音楽専門のオーケストラがあることを知りました。
そして年明け2月にはコンサートがあるようで、やはり需要はあるということですね。
ちなみに、公演はJAGMO(ジャパン・ゲームミュージック・オーケストラ)による、2月7日、8日、
ゆうぽうとホールで行われるもの。ちょっとこれ、取材してきます。
----------------------------------------------------------------
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.15 ★ 2015.01.014号
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ナクソス名盤落穂拾い」第5回
みなさ〜ん、2015年になってからちゃんと変な曲聴きましたか〜?
変な曲大好き!推進委員会・委員長の林田直樹です。
最近、プロデューサーのこういち君が、私のことをときどき変な目で見るんです。
どうやら、ニコニコ動画限定の番組に、私を登場させたいと思っているみたいで…。
でも、
変な曲大好き!推進委員会の委員長のことを、
変な目で見るだなんて、これでこういち君も、
変なプロデューサーの仲間入りですね。なんつって。
そう、
変な人でなければ、クラシック音楽放送なんて、つとまるわけありません!
さて、私が今回おすすめする変な曲いっぱいのアルバムはこちら。
●ヴァレーズ:アルカナ(奥義)/オクタンドル(八雄しべの花)/オフランド(捧げ物)/
アンテグラル(積分)/砂漠(ポーランド国立放送響/リンドン=ジー)
http://ml.naxos.jp/album/8.554820
みなさん、打楽器はお好きですか〜?
もちろん大好きですよね!(と勝手に決めつける)
特にオーケストラで、マーラーとかストラヴィンスキーとかで、
ティンパニや大太鼓がドカドカ鳴っていると、もうロックでロックでわくわくしちゃいますよね〜。
ときどきムチのピシーッ!という音が鳴ったりして。
あん。気持ちいい。
この血沸き肉躍るパーカッションの世界を、もっとアヴァンギャルドに、めちゃくちゃに、
へんてこりんに葛藤させたら、エドガー・ヴァレーズ(1883-1965)になるのです。
ストラヴィンスキーの「春の祭典」が好きなら、ヴァレーズも大丈夫!
私はヴァレーズの音楽は、オーケストラの「はらわた」だと思っています。
ぐちゃぐちゃな感じが美しい。かっこいい。
打楽器フェチには相性抜群!
このCDの中のオススメは「砂漠」。ぜひこの曲から聴いてみてください。
まるで工事現場の音プラス、機械でできた巨大怪獣がのた打ち回っているみたいで、
最高にイケているノイジーで変態な世界ですよ。
頭の中に棒を突っ込んでかき回してもらっているみたいに気持ちいい。
ヴァレーズを聴いていると、思わずこんな言葉が口からもれそうです。
「もっと…ぐちゃぐちゃに…してください」
言えるかな〜?
難易度高いですねえ。
でも、みんな一緒なら大丈夫。
さあ、勇気を出して。
「もっと…ぐちゃぐちゃに…してください」
小さい声でもいいですから。
そっけなく言わないでね、色っぽく。
ヴァレーズの美には色気があるんだから。
誰もいないところで、口のなかでつぶやく練習をしてくださいね〜。
きっとあなたの中の何かが変わりますよ。うふふふふ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.14 ★ 2015.01.07号
********************************************
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 by 本田聖嗣
第5回目 「亜麻色の真相?!」
前回は、ラヴェルの水の戯れ、にまつわる翻訳のお話でした。
今回は、ラヴェルと同じくフランスを代表する作曲家、ドビュッシーに登場してもらいましょう。
フランスのクラシック音楽、といったらこの時代を指す、というぐらい、たくさんの作曲家が
活躍した19世紀後半から20世紀のフランスの近代音楽ですが、その音楽は、
文学と一体不可分でした。ドイツのロマン派音楽も、文学と密接に結びついているように、
フランスの近代の音楽も、「言葉」を重要視しています。
それはよく言われるように、パリなどの「サロン」で、異分野の芸術家が交流したことも、
一つの理由です。
ドビュッシーは、中でも、言葉に対して鋭敏な感覚を持っていました。
しかし、あくまで、言葉は音楽より前に出ることはなく、インスピレーションを詩や文学から
受けても、最終的には、音だけが描く、芸術の世界を想定していたようです。
その証拠に、20世紀になってからの作品、私が最初にCDレコーディングに選んだ、
ピアノのための前奏曲集 第1巻・第2巻は、各曲に題名がついているものの、
楽譜の曲頭には書かれておらず、音符が全て終わった各曲の末尾に、カッコ()をつけて、
ごく控えめに、書いてあるのです。
あたかも、題名で曲に先入観を持たないで・・・と言わんばかりです。
有名な「月の光」を含むベルガマスク組曲のような初期作品では、題名が普通に
最初に書いてあるので、進化したドビュッシーは、言葉と音楽の関係をどのように考えるように
なったか・・の貴重なヒントになります。
ところで、その前奏曲第1巻の中に、「月の光」と並ぶぐらい有名な「亜麻色の髪の乙女」
という曲があります。2分に満たない短い曲ですが、素敵な旋律で、人気の高い曲です。
この曲の原題は、「La fille aux cheveux de lin 」というものですが、ここで問題があります。
「lin」ってどんな色?ということです。一般的には、金髪の一種・・のように(特に英語では)
解釈されているのを見かけますが、フランス人でも、lin は Blonde(これはこのまんま
ブロンドで日本語としても通じますね)とは違うといいます。
そして、より亜麻布、に近い色だとすると・・・正直・・あまりきれいな色ではないのです。
なので、フランスのある演奏家・作曲家の解釈では、「lin」色の髪の毛を持ち、
「美しくない」と悩んでいる少女に向かって、ドビュッシー自身が、「そんなことないよ、
あなたは、心が美しいので、そのままが美しいのだ」と慰めている曲なのだ、ということなのです。
あくまでも、亜麻色とブロンドは違う、という解釈ですね。一方で、もちろん、亜麻色を
広義の金髪に含めて、美しい少女をそのまま描いた、というごく一般的な解釈をする演奏家も
もちろんいます。
私は、この曲を演奏していると、そのどちらも納得してしまうのです。
結構女性好きで、前妻をピストル自殺に追い込んでいるドビュッシーのことですから、
純粋に美しい女性を描いた曲を作曲するのも不自然ではありませんし、一方で、「子供の領分」
などで見せる、彼の子供に対するやさしさが「あえてブロンドでない少女」に注がれる眼差し
として、これまた自然な感じもするのです。
真相は、もちろん、ドビュッシー自身に聞かないとわからない・・わけですから、
後世のわれわれがとやかく言ってもしょうがないのですが、そんなわけで、私は、つねに、
「両方の意味がある」気持ちを持って演奏しています。
そして、その「ダブルミーニング(2つの意味がある)」ということになると、フランスには、
実に様々な文学作品や詩があるので、音楽も、当然、そのややこしさを内包したままなのです。
長くなりましたので、また別の回に書きたいと思います。
********************************************
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.14 ★ 2015.01.07号
==================================
第5回「ダ・ヴィンチのラヴソング」 高野麻衣
新春初のOTTAVA Domenicaのテーマは「2015年にやりたい∞のこと」。
ウィンナ・ワルツの華やかな気分の中で、シュトラウス2世『こうもり』とシャンパン消費量の
甘い関係(?)などおしゃべりしつつ、林田さんセレクトによる音楽シーンの話題をお伝え
しました。
私からは、音楽とともに楽しみたい展覧会の話題を。
ビッグ4(ルーヴル美術館、大英博物館、ワシントン・ナショナル・ギャラリー、プラド美術館)
の来日も見逃せませんが、高野セレクトの注目はこんなかんじでした。
◆グエルチーノ展(3/3〜国立西洋美術館)
◆ボッティチェリとルネサンス展(3/21〜Bunkamuraザ・ミュージアム)
◆レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展(5/26〜東京富士美術館)
音楽は西山まりえさんの新譜から、ダ・ヴィンチが作曲したラヴソングを。
彼の多才ぶりはネッサンスの天才だから、ではなく、芸術家ならば自然な欲求だったんじゃ
ないかな、と私は思います。今年もたくさんの音楽や美術、本、そして歴史や日常のキラキラを
分かちあえたら幸せです。
==================================
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.13 ★ 2014.12.24号
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
「人生、ほぼ音楽」 ゲレン大嶋
第4回「あけましておめでとうございます!?」
今日は、12月24日。明日のクリスマスは、みなさんご存知の通り、イエス・キリストの誕生日。
キリスト教のお祝いの日です。
そして、今夜はクリスマス・イヴ。教会の暦では日没をもって一日の終わりとするので、
24日の日が暮れたらもう翌日=キリストの誕生日ということになります。
なので、ここからお祝いを始めるのがクリスマス・イヴなんですね。
しかし。実はキリストの誕生日に関しては諸説あって、正確なところはわかっていない
のだそうです。では、なぜ12月25日とされているのでしょうか?
これは冬至と深い関係があると言われています。
冬至は、一年で昼の長さが最も短くて夜が一番長い日。
今年は、一昨日12月22日でした。そして、冬至というと、寒い、そして、ここからさらに
本格的に寒くなっていく、というイメージが先立つんですけれども、同時に、この日を境に、
夏至から少しずつ短くなってきていた日照時間が再び長くなり始めるので、再生の時という
意味合いも持っているんですね。
北半球の世界各地には、この日を、太陽の復活、陽気の回復の日として祝う行事が色々あります。
かつてのヨーロッパでは、農耕の守護神のお祭りが行われ、ここ日本には、弘法大師が村を巡る
という言い伝えが各地に残っています。
そう、諸説あったキリストの誕生日を12月25日にしたのは、ヨーロッパの冬至のお祝いと
キリスト生誕のお祝いを重ね合わせたからだったんですね。
そして、かつては、世界各地で(ここ日本でも)、冬至が新しい年のスタートの日とされて
いたようですが、どうでしょう、この「再生の日」を「元日」とする方が自然ですよね?
ということで、一足早く・・・あけましておめでとうございます。
新しい年もOTTAVAから流れ出す音楽とともに素敵な時間を過ごしていただけますように。
よろしくお願いします!
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.12 ★ 2014.12.17号
----------------------------------------------------------------
進化する音楽 〜音を楽しむって素晴らしい〜
第四回「DTMの面白さ」 森雄一
DTM、Desk Top Musicというのをご存知でしょうか。
直訳すれば、机上の音楽ということになりますが、パソコン上で専用のソフトウェアを
使った音楽制作のことです。DTMの魅力は誰でも楽曲を作れるということ。
作ってみようという情熱と時間があれば、ひとまず思ったような楽曲は作れるはずです。
ソフトの種類もいろいろあり、無料のものからプロ仕様の高額のものまでピンキリ。
無料ソフトの代表は、Garageband(マック)。楽器ごとにメロディやドラムパターンなどを
入力し、それを同時に演奏させることにより楽曲に仕上げていくというものです。
そのような面倒くさいことをしなくても、楽器一つがあれば、弾き語りで楽曲は仕上がります。
でも、これにドラムを入れてみたい、ベースラインをこだわってみたい、間奏にキーボードをと、
アイディアが生まれれば、それを形にするのはアナログでは難しいものです。
でも、DTMであればそれを可能にします。
これらは「打ち込み」と呼ばれるやり方で、機械的な響きから、演奏者の感情が入っていない
こともあって嫌う方もいるでしょう。
でも、今はこういった自作の音楽を動画サイトにアップすることにより、曲の善し悪しで
視聴者が増え、それがプロの目に留まって世界が変わることもあるのです。
第一回目のコラムでも紹介した初音ミクがそれで、初音ミクはあくまでも音声合成ソフト。
メロディを入力し、それに合わせた歌詞を入力すると初音ミクの声で歌ってもらえるのです。
つまり、DTMで楽曲を作り、それに初音ミクの歌をミックスすると、机上ですべてのパートを
作ってしまうことができます。ボーカルが入ると、それは立派な音楽です。
プロの「P」を目指す人の中には中学生や高校生といった若者も多く、彼らにとってパソコン操作は
朝飯前。後は楽曲制作能力を上げていけば夢を実現させることもできるかもしれません。
経済面では、無料の楽曲制作ソフトを使い、自身のボーカルで歌えば、ほとんどお金を
かけることなく大きな利益を得られるかもしれないのです。でも、これは究極の過程であって、
本気になればなるほど、ある程度のお金はかかってきます。
ただラジオから流れてくる音楽を聞いて満足できるのであればそれでいいでしょう。
レンタルCDを借りまくってライブラリーを作るのもいいかもしれません。
でも、音楽は聞けば聞くほどハマっていくもので、コンサートに足しげく通ったり、
やがて楽曲を作りたいと思う人も出てくると思います。昔は相当高いハードルがありましたが、
今は違います。レコード会社も次世代のスターを常に探しています。
今はCDセールスが振るわない時代です。でも、店頭でパッケージを買い求めなくても手元で
ダウンロードできたり、動画サイトで人気が出てメジャーデビュー、ラジオで流れなくても
カラオケで大ヒットということもあります。
「千本桜」って曲、知ってますか?カラオケランキングでは常に上位の曲ですが、
ラジオで流れることはほとんどありません。
一方で、この曲のインストゥルメンタルはトヨタのCMで採用されています。
「千本桜」の世界観はユニークで、小説化や舞台化もされ、元々はDTMから生まれている点も
見逃せません。
----------------------------------------------------------------
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.12 ★ 2014.12.17号
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ナクソス名盤落穂拾い」第4回
むふふふふ。お待たせしました。
変な曲大好き!推進委員会・委員長の林田直樹です。
最近このコラムの人気もじわじわと高まっておりまして、
いっそのこと、特別枠で番組化しちゃったらどうかという声も出ているくらいです。
そしたら、私も声の色を替えて、スネークマンショーみたいに別キャラになって、
真夜中に変態チックな声で変態的なクラシック番組をやってみようかと…。
(ああ、でもそんなことしたら音楽評論家生命が…もう二度とまともに戻れない…笑)
「変な曲推進委員会」の第1回秘密集会をOTTAVA主催で開くべきだという主張も出ています。
あそこは地下室で、危ない雰囲気満点ですからね〜。
そしたら、集まった人全員は黒いもの着用ルールで、入口ではサングラスを配って、
徹底的にダークで気持ち悪い音楽ばかりを、ニヤニヤしながら聴く。
そこでは皆さんちゃんと「もっと激しく…もっと熱く…」と全員で唱えるのですよ(笑)。
面白いアイディアがあったら教えてくださいね〜!
先行予約したら何人くらい集まるかなあ。
ま、そんな妄想はさておき、今回も、みなさんを危険極まりない、ヤバくて、不健全な、
クラシック音楽の世界へと誘惑いたしますですよ!
さて私が今回おすすめする変な曲いっぱいのアルバムはこちら。
●周龍:SU/ピアノゴング/台北鼓/野草/タイグ・ライム/陳怡:モノローグ/
中国古代舞曲(北京ニュー・ミュージック・アンサンブル)
http://ml.naxos.jp/album/8.570604
ちょっと中華風味で攻めてみました。
4000年の歴史を持つ、何でも食べちゃう奥深い中国ですから、音楽もとんでもなく変なものが
いっぱいあります。
とにかく1曲目から聴いてみて!
中国の伝統を継承した音楽ならではの、チョー変な音が飛び出してきますから。
私にはみなさんの表情がもう目に浮かびますよ。
「これは…!」
「…気持ちいい…たまらない!」
初めての体験を、理屈抜きに「気持ちいい」と感じることなんです。
理論なんか別に知らなくたっていいんです。
さあ、みんなでもう一度!
「…気持ちいい!…たまらない!」
言えましたか〜?
ちゃんと色っぽく、ため息交じりに、口に出してくださいよ〜(笑)
実はこれ、TBS=OTTAVAが始まってしばらくの頃、私がよく番組で紹介していた音源で、いつも
好評でした。紹介するのは久しぶり。
周龍(チョウ・ロン)は、1953年北京生まれの中国出身のアメリカの作曲家で、文化大革命の
時代にはトラクターの運転手をして農作業に従事しながらピアノを学んだそうです。
そして、コロムビア大学に留学して、周文中(チョウ・ウェンチュン、米国と中国の架け橋と
なった作曲家・教育者。バーンスタインとも交流があった)らに師事しました。
いまや中国を代表する現代の作曲家の一人となったチョウ・ロンは、米国籍も取得し、最近では
チェリスト、ヨーヨー・マのシルクロード・プロジェクトにも参加、ボストン・オペラではオペラ
「白蛇夫人」を委嘱され初演しました。2011年にはピューリツァー賞を受けています。
チョウ・ロンの、この色っぽくて曲がりくねった作品、現代音楽のエッセンスがお洒落に加わって
いて、誘惑度がとても高いです。変わった打楽器の響きもいっぱいで、何よりもかっこいい。
一緒に入っている陳怡(チェン・イ)という人の妖艶な作品ともども、ぜひあなたの変な曲コレク
ションに加えてあげてください。
やっぱ中国の文化ってすごいな〜。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.11 ★ 2014.12.10号
********************************************
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 by 本田聖嗣
第4回目 「エステ荘で戯れてはいけないか?」
前回は、ガラ・コンサートの譜めくりの話になってしまいましたが、クラシック楽曲における
翻訳の話題に戻ります。
翻訳は、必ずしも誤訳ではなくても、いろいろ難しいモンダイをはらんでいます。
戯曲・詩歌・小説、などの文学だと、言葉が最も重要ですから、翻訳の問題は、掘り下げて
議論されたり、多数の研究者・翻訳家によって、異なる翻訳が出版されていたりしますが、
クラシック音楽の題名等は、そこまで、突き詰めて考えられない・・というか、
言葉は置いておいて音楽を聴いてよ・・ということになってしまうのではないかなあ・・・
と楽譜を見て感じるときもあります。
明治期に、文学などと一緒に輸入されてきた西洋音楽ことクラシック音楽は、
文語が似合います。
口語的表現があふれている現代でも、クラシック音楽の題名は、文語的な表現が多いですね。
フランスを代表するピアノ音楽、と言ってもよい、ラヴェルのピアノ作品「水の戯れ」
という題名も、古風な香りがします。・・そういえば、ラヴェル自身に「古風なメヌエット」
という作品がありますが、彼は、遠い過去のフランス文化などに敬意を払った人で、
他にも「クープランの墓」のように、ハッキリと題名でいにしえの時代へのリスペクトを
表現していますから、こういった文語的翻訳がしっくりきます。
「水の戯れ」の原題は“Jeux d’eau”ジュドーと読みます・・で、そのまま直訳すると
「水の遊び」となります。Jeuxは英語のplayにあたる単語で、遊び、のほかに演奏、
という意味もあるところも同じです。
ちなみに、ラヴェルに匹敵するフランスを代表する作曲家、ドビュッシーにもそのまま
「Jeux」という管弦楽曲がありますが、こちらは日本で、「遊戯」と訳されます。
遊び・・・ではなく「戯れ」と訳したのは、とても、名訳だと思います。
単なる子供の遊戯、的なイメージから、戯れ、とすることで、大人のエレガンスさえ感じさせます。
しかし、ここに問題が発生するのです。
Jeux d’eau を辞書で引くと、「噴水」という意味があるのです。いや、正直にいうと、
その意味しかありません。ジャガイモ、という単語がなく「大地のリンゴ」という言い方しか
しないフランス語では、「噴水」も1語の単語では存在せず、「水の戯れ」という表現を
使うわけです。
と、ここまでなら、ラヴェルの曲に限っては、「噴水」より「水の戯れ」のほうが詩的で
いいではないか、という結論でいいのかもしれませんが、同じクラシックの曲目、
しかもパリで活躍したフランツ・リストのピアノ曲で、「エステ荘の噴水」という曲が
存在するわけです。
ドイツ系ハンガリー人のリストは、さまざまな言語で自作の題名をつけていますが、
エステ荘の噴水に限ってはフランス語、そして、そう、その原題は、
“Les Jeux d'Eaux a la Villa d'Este”なのです。
こうなると、なぜ、リスト作曲「エステ荘の水の戯れ」ではなく、ラヴェル作曲「噴水」
でもないのか、ということを考えてしまいます。
実は、ラヴェルは、リストのまさにこの曲を意識して、Jeux d’eau を書いていると
いわれており、題名の中には、そのリスペクト・・が含まれていると考えるのが当然でしょう。
そうすると、リストとラヴェルの作品の日本語題名からでは、関連が見えず、
残念なことになります。ラヴェル作品の題名の翻訳が詩的な名訳だけに、さらに一層、
もったいないわけです。
ラヴェル作曲「噴水」だと、なんだか味気ないので、むしろ、リストの作品のほうを
「エステ荘の庭の水の戯れ」とかなんとか、もう少し素敵な題名にしてあげられないかなあ・・
と楽譜(ピアニストが使う楽譜は原典版が多いので、題名は、大体原語表記なのです)を
眺めながら、いつもため息をついてしまいます。
まあ、それも一瞬で、ビートルズをもじって、「ヘイ、ジュドー」とダジャレを心の中で
言ってから、弾き始める・・というのがいつものパターンなんですが。
********************************************
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.11 ★ 2014.12.10号
==================================
第4回「女王陛下とクリスマス」 高野麻衣
12月のこの時期は、幸福感に満ちたホリデイ。私は幼い頃からヨーロッパ文化と
その土台であるキリスト教会に夢中だったので、聖書やクリスマスについての本を読んだり、
映画をみたりするのがいまでも大好きです。
「小公女セーラが屋根裏部屋に用意してもらったクリスマス・プディングってなあに?」
「若草物語の四姉妹が声を合わせるのは、何番の賛美歌?」
そういう少女でした。
クラシック音楽も盛り上がる時期。
今年はOTTAVA Domenicaで存分にご紹介できるので、幸福感も倍増中です。
いよいよ今週末は、横浜美術館で行われる「ホイッスラーと音楽と19世紀ロンドンがわかる
横浜アートツアー」(http://www.girlsartalk.com/top-page/4317)。
展覧会と国際音楽祭NIPPONによるコンサートの“引率者”である私は、お茶会でお話する
「ヴィクトリア女王」や「クリスタル・パレス」、「ダンディ」といった単語にわくわくする
日々です。
女王陛下の英国で、ロンドナーたちがどんな文化生活を送っていたのか?
ホイッスラーはシャーロック・ホームズのようにコンサート通いをしていたのか?
気になるあれこれを、皆さまと一緒に分かちあえたら幸いです。
==================================
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.10 ★ 2014.12.3号
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
「人生、ほぼ音楽」 ゲレン大嶋
第3回「風土と音楽〜北欧のクラシックを冬のサウンド・トラックに」
沖縄の音楽に惚れ込んで、その背景にある「何か」を求めて島へと旅をし、その結果、
音楽だけでなく、彼の地独特の様々な文化や、自然、人が大好きになって、三線弾きとなった私。
これまでに何度となく「沖縄に住んでいるんですよね?」とか「長い間住んでいたんですよね?」
などと聞かれてきました。もちろん「移住」という言葉が脳裏をかすめたこともあります。
でも、あえて私は生まれ育った東京多摩地区のそばを離れることなく暮らしてきました。
そこには、沖縄の、音楽に、三線に、魅了された、東京生まれ東京育ちの私が、自分なりの
三線音楽を作りたいという思いがあり、そして、そのためには、この場所にとどまるべきだと
考えてきたからです。
9月に1週間ほどライヴのために沖縄に滞在しましたが、島に入ってから3、4日が経って、
ふと気が付くと、頭の中に流れてくる即興のメロディ(鼻歌のようなもの)が、とても沖縄の
香りの強いものになっていました。
それだけ沖縄の空気は濃密で、この地の風土と音楽のつながりがとても強く深いのだと改めて
感じ、もし私が沖縄に住んでいたら、私の生み出す音楽も、全然違うものになっていたのだろうな、と思わされました。
沖縄に住むことなくここまで生きてきた今の私の曲は、当然沖縄音楽へのリスペクトを
含みながらも、どこかで多摩地区の香りを放っているのではないか?と思うのです。
もちろん、音楽の空気感を形成するエッセンスは他にもたくさんあります。例えば、
大きな要素のひとつとして時代性というのもあげられますが、やはり私は、その前に風土性が
あると思うのです。
と、長くなりましたが、ここまでは前置き。ここからが本題です。
今日12月3日は、ノルウェーの作曲家クリスティアン・シンディング(1941年没)と
スウェーデンの作曲家ヴィルヘルム・ペッテション=ベリエル(1942年没)の命日です。
シンディングは『春のささやき』で知られていますよね。
長い間ドイツで活動して、作風もドイツ・ロマン派の流れを汲むと言われていますが、
やっぱり彼の曲からはノルウェー的な情緒が感じられます。
ペッテション=ベリエルは、母国の山岳地イェムトランドを愛して、この地の自然に
インスピレーションを受けた作品を書きました。そう、北欧の作曲家たちの作品からも、
とても強い風土性を感じますよね。ちょっとステレオ・タイプですが、彼らの音楽を
聴いていると、北欧の大自然が織りなす神秘的な情景や冷たくて澄み切った空気といったものが
イメージされます。
そして、そんな北欧音楽は、彼の地ほどではないですけれども、やはりとっても寒〜くなる
ここ日本の冬にもよく似合うと思うのです。そこで、どうでしょう、北欧のクラシック音楽を
冬のサウンド・トラックにしてみる、というのは?
ご存じの通り北欧は、グリーグやシベリウス、今日が命日のシンディングや
ペッテション=ベリエル、他にも素晴らしい作曲家たちをたくさん生み出してきました。
番組でも、特に冬の間は、彼らの作品を多めにお送りしていこうと思いますので、ぜひお聴き
いただいて、お気に入りの曲を見つけてください。そして、ご自宅で北欧の作曲家の作品集を
かけて窓の外をのぞくと、そこには白銀の森や湖、フィヨルドのパノラマが広がっているかも??
よかったらお試しを。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.9 ★ 2014.11.26号
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ナクソス名盤落穂拾い」第3回
うふふふふ。お待たせしました〜。
ご機嫌いかがですか〜?
変な曲大好き!推進委員会委員長の林田直樹です。
さあ今回も、みなさんを危険極まりない、ヤバくて、不健全な、クラシック音楽の世界へと
誘惑いたしますよ!
まずは、変な曲がますます好きになる魔法の呪文を唱える練習からまいりましょう。
小さな声で結構ですので、ぜひ音読してみてくださいね! では。
「もっと激しく…もっと熱く…」
さあ言えたかな〜?
口の中で、色っぽく、ささやく位でいいんです。心を込めてもう一度!
「もっと激しく…もっと熱く…」
どうです、気分が高まって来たでしょう?
こういう心構えが、名演奏を呼び寄せるのです(これ少しマジ)。
でもこのアモローソな呪文、こっそり一人でやってくださいね。
誰かに聞かれて、誤解されるといけませんから(笑)。
さて私が今回おすすめする変な曲いっぱいのアルバムはこちらです。
●ラング:ピアス/ヘロイン/不正、嘘つき、盗み/祈る方法/結婚(リアル・クヮイエット)
http://ml.naxos.jp/album/8.559615
もはやナクソスを代表する名盤の一つといってもさしつかえないでしょう。
とにかく危険で、色っぽくて、倒錯的で、ロックしています(2曲目はルー・リードの曲です)。
悪と犯罪の香りがします。爛れています。
ぐさぐさと心に突き刺すような、革フェチな音がします。肌が露出しています。
これもクラシックなのかと思うほど。
いや…クラシックが安全で、禁欲的で、おとなしいものだというのは間違いです。
ヤバくなければクラシックではない!
ぜひ心がささくれだったときに、傷ついたときに、たとえば2曲目の「ヘロイン」を
聴いてみてください。
チェロとヴォーカルによる、耽美的で孤独な響きによって、あなたの瞳がトローンと
翳りのある色を帯びてくるのを感じるはずです。
デイヴィッド・ラングは1957年生まれのアメリカの作曲家。
ミニマル・ミュージックの手法と、ロック的なセンスを融合した作風が特徴で、ルネサンス音楽の
影響を受けた合唱音楽なんかも得意です。
繰り返しばかりで、ものすごくシンプルに見えるこうした音楽には、必ず一定の批判がつきまとい
ます。単純すぎるじゃないかと。
けれど私が思うのは、有名なフィリップ・グラスもそうですが、こうしたミニマリズム的
(反復ばかりを特徴とする)な音楽の一部は、実は、ある情緒の周りを——まるで蝋燭の火の
回りを飛ぶ蛾のように——えんえんと同じ感情や観念につきまとわれている、一種の病的な
精神状態を表現しているのだと思います。
そういう音楽を聴くことは、強烈なセラピー、治癒のためでもあるのです。
それには、グイーンと光線を照射するみたいに、一定の時間が必要。
だから繰り返しが多いのです。
病んでいない人なんかいません。心は不調をきたして当たり前なのです。
ラングの音楽は、静かさと、その背後に隠されたナイフとが、同居しています。
そこにある種、現代的な生々しさと、不思議な癒しのマジックがあると思います。
あ。いけね。マジになっちゃった。
さあ〜もう一回、呪文を唱えてみましょうか。色っぽくお願いしますよ。
ぜひぜひ口に出して。熱い吐息と一緒なら完璧です。さ!
「もっと激しく…もっと熱く…」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------
進化する音楽 音を楽しむって素晴らしい
第三回「応援する力 Part 2」 森雄一
スクールアイドルが学校の危機を救うラブライブ。アニメキャラクターが
その名前でコンサートを行い、会場を埋め尽くすファン・ラブライバーは熱狂する。
最初のコラムで触れた初音ミク同様、ファンはその可能性に狂喜乱舞します。
自分が応援する人(キャラクター)が大きく成長する。
誰もがアイドルに夢中になる時期がありますが、いわばそれと同じです。
形は若干、変わってきていますが、基本的には「応援する」というアクションです。
ラブライブの中心的キャラクター、2年生の高坂穂乃果は思ったことを即、実行するので、
まわりは振り回されっぱなし。スクールアイドルグループの発起人です。
幼なじみの南ことりは、彼らが通う音ノ木坂学院の理事長の娘で、自らの行動力のなさから、
穂乃果に頼りっぱなし。
一方、やはり幼なじみの園田海未は、穂乃果やことりと違ってしっかり者で、
弓道を愛する大和撫子。無理やり付き合わされるアイドルに反発しながらも、
9人をしっかりまとめていきます。
1年生の小泉花陽は、子どもの頃からアイドルを夢見ていたものの、人見知りで声が小さく、
自信が持てない乙女。花陽の親友、星空凛はボーイッシュで運動神経がいいので、ダンスが得意。
花陽のメンバー入りを後押ししました。
☆ OTTAVAメルマガ通信Vol.9 ★ 2014.11.26号
----------------------------------------------------------------
進化する音楽 音を楽しむって素晴らしい
第三回「応援する力 Part 2」
スクールアイドルが学校の危機を救うラブライブ。アニメキャラクターが
その名前でコンサートを行い、会場を埋め尽くすファン・ラブライバーは熱狂する。
最初のコラムで触れた初音ミク同様、ファンはその可能性に狂喜乱舞します。
自分が応援する人(キャラクター)が大きく成長する。
誰もがアイドルに夢中になる時期がありますが、いわばそれと同じです。
形は若干、変わってきていますが、基本的には「応援する」というアクションです。
ラブライブの中心的キャラクター、2年生の高坂穂乃果は思ったことを即、実行するので、
まわりは振り回されっぱなし。スクールアイドルグループの発起人です。
幼なじみの南ことりは、彼らが通う音ノ木坂学院の理事長の娘で、自らの行動力のなさから、
穂乃果に頼りっぱなし。
一方、やはり幼なじみの園田海未は、穂乃果やことりと違ってしっかり者で、
弓道を愛する大和撫子。無理やり付き合わされるアイドルに反発しながらも、
9人をしっかりまとめていきます。
1年生の小泉花陽は、子どもの頃からアイドルを夢見ていたものの、人見知りで声が小さく、
自信が持てない乙女。花陽の親友、星空凛はボーイッシュで運動神経がいいので、ダンスが得意。
花陽のメンバー入りを後押ししました。
同じ1年生の西木野真姫は、医者の家系なので音楽の道に進むことに抵抗があるものの、
作曲の才能があるので、グループのすべての楽曲を手がけています。
3年生の矢澤にこは、学院のアイドル研究部部長。たった1人で部活をしていましたが、
穂乃果以下、部員が増えて実は名前の通りニコニコなのです。
同じ3年生の東條希は、グループ名「μ(ミューズ)」の名付け親。μの活躍をタロットで占う
スピリチュアルな生徒会副会長。
そして、生徒会長の絢瀬絵里は幼い頃からダンスが得意なお姉さんタイプ。
学園の危機に際して、スクールアイドルに反対するものの、穂乃果から勧誘され、自分が本当に
やりたかったことに目覚めます。
9人全員タイプが違うところが大きなポイント。視聴者は自分と似ているキャラクターを見つけ、
違うタイプを受け入れる過程をストーリー中に見つけます。
数多い楽曲の中にもその様子が表現され、歌詞を追っていくと、彼らの成長の様子が
見て取れるのです。
動画サイトでラブライブを検索すると、世界各国のラブライバーが「踊ってみた」を
アップしています。
自分も真似てみたくなるコンテンツ。今はこういった楽曲が愛されているようです。
動画サイトの「演奏してみた」では、クラシックにトライしているものも多いですが、
踊りが入ると視聴者が増えるのが自然です。これを見て、私もやってみようと次々に
ファンが増えるのも現代風。
アイドルはもちろん、芸能人はファンに支えられていますが、AKB48が成功している様子を
見ても分かるように、応援したくなるコンテンツにするのはなかなか大変。
メディアミックスで人気を拡大してきたラブライブは今後も成長していくことでしょう。
あなたが応援してくれるOTTAVA、私たちはその応援の力で今、成長しているのです。
OTTAVAの男性プレゼンターでグループを結成するとしたら、どんなグループ名がいいのでしょうか(笑)。
というか、そもそも何やるの?
----------------------------------------------------------------
☆OTTAVAメルマガ通信Vol.8★ 2014.11.19号
********************************************
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 by 本田聖嗣
第3回目 「楽譜と譜めくりとめくりめくられ物語」
このコラムでは、楽譜・翻訳にまつわることを、書いてきましたが、先日、OTTAVAの
第2の開局記念コンサートに出演させていただき、そこでは、連弾・伴奏・・2台ピアノと
いろいろな演奏曲目があったので、今回は、本筋を少し離れて、演奏の現場での「譜めくり問題」について、書きたいと思います。
クラシックの演奏家は、楽譜をつかいます。音楽とは、即興性も重要な要素ですから、
楽譜は「1部分」であるべきなのですが、ことクラシックに於いては、ベートーヴェン以降、
作曲家の権力が拡大したので(?!)、現代でも、なるべく、楽譜に忠実に再現する音楽が
もとめられます。もともと、ヨーロッパ発祥の音楽が世界を席巻したのも、この「楽譜」という
優れたシステムがあったからこそ、ともいえます。
ピアノや他の楽器でも、ソロリサイタルのときなどは、暗譜、といって楽譜を置かないで
演奏することもありますが、自分以外の演奏者がいるとき、つまり2人以上の室内楽では、
相手のパートを見ることも必要なため、楽譜を用意するのが普通です。
そして、奏者は両手を使って演奏に専念するため、楽譜を、必要な瞬間にめくることができない、
というところから、「譜めくり問題」がおこるのです。
OTTAVA saloneの火曜日にご質問いただいたので、放送の中でお答えしたのですが、
ガラコンサートでは、福間さんは、2台ピアノのとき、ドイツで購入したという、
「タブレット+楽譜表示ソフト+足踏み式楽譜めくりスイッチ」を使っていました。
いまや、タブレットで楽譜を表示して、演奏中見ながら使う奏者は珍しくありませんが、
紙と同じように、タッチスクリーンにタッチしてめくるパターンが多く、
手が使えないピアニスト用の、ペダル式譜めくり装置は、私も初めて見たので、
大変興味深かったです。もし、バッテリー不足や、画面表示エラーなどの、不具合が起きたら
どうしよう・・と心配してしまうのですが、福間さんは、もうすっかり日常のツールとして
使いこなされていました。
一方、私は、ミュージカルのお二人、オペラのお二人、そして、福間さんとの連弾、
ラフマニノフの2台ピアノ作品と演奏させていただいたのですが、それぞれ、
最初のフィガロの結婚序曲の連弾は、上のパートを弾く福間さんが譜めくりを担当し、
ミュージカルの曲は自分で譜めくりを、オペラの楽譜と、2台ピアノは、譜めくりの方に
お願いする、という方法をとりました。
それぞれ、いろいろな工夫と背景があります。基本的には、譜めくりは少ない方が良いので、
楽譜の方を編集して、めくり回数が少ないように設定します。ミュージカルの歌や、
オペラのアリアは、それほど長いものが多くないので、出来れば見開き・・譜めくり無しの楽譜を
作るのですが、一筋縄ではいきません。楽譜は、音楽のタイミングと連動しているので、
「そこでは、めくりたくない!」ということもあります。
世の中に流通している楽譜は、ちゃんとした編集者の手を経ていることが多いので、なるべく、
めくりやすいタイミングで、ページのボトムに来るようになっているのですが、作品によっては、
仕方なく、めくりのポイントになるべく切りたくない、音楽的に重要な場所が来たりするのです。
また、自分でめくる場合は、当然、片手が空いている場所でめくるので、楽譜の実際の
めくりポイントとは違うパッセージで、めくっておいて、後は記憶で弾くか、次ページに
前ページの一部分を貼り付けたり、楽譜の上下を切って、1ページを二回に分けてめくったり、
とおよそ本などでは考えられない作業をするのです。両手が常にふさがっていることの多い
ピアニストの、それは独特な工夫です。
そうやって、自分で最大限めくりやすく、かつ、めくりの回数を少なくするのですが、
長大な曲が多いクラシックでは、譜めくりの方をお願いすることも、多くあります。
そうすると、その方との息の合わせ方、も重要になってきます。
実際、私は、優秀な「譜めくりスト」でもあるのですが、他の方の演奏している楽譜をめくる、
というのは、常に先を見ている演奏家の意図をくみ取って・・
もちろん、それは楽曲のテンポにより、常に変化します・・・ベストのタイミングで、素早く、
かつ見やすいようにめくる、という芸術的な作業なのです。
譜めくりはするのも、されるのも、以上のように色々な要素が絡むことですが、
それを一挙に解決するかもしれない、電子デバイスの発展もこれからますます進むことでしょう。
私も、タブレット+足踏み譜めくり装置の導入を、いつにしようか?とチラと考え始めています。
********************************************
☆OTTAVAメルマガ通信Vol.8★ 2014.11.19号
==================================
第3回「貴婦人と一角獣とデュファイ」 高野麻衣
デュファイは、タピスリー『貴婦人と一角獣』と同時代の16世紀フランスで活躍した
天才シンガー・ソングライター。ブルゴーニュ宮廷のきらびやかな貴族趣味にのっとりながらも、
現代の私たちにも通じるような甘やかでせつないメロディをたくさん残しました。
しかも、演奏はアンサンブル・ユニコーンとあって、この展覧会*のために制作されたかのような
音楽だったのです。
展覧会では、いつも解説文とにらめっこしてしまう、というひとも多いかと思います。
音声ガイドがあれば、解説を耳(聴覚)で補う分、目(視覚)をぞんぶんに美術品にそそぐこ
とができる。洗練されたナレーションと選び抜かれた音楽が流れれば、空間全体が巨大な
プラネタリウムのよう! ミュージアム・コンサートは数多くありますが、美術鑑賞そのものを
スペクタクルにしてしまう、あの体験にまさる感動を受けたことはありません。こういう潮流が
もっともっと広がるように、音楽の側からどんどん働きかけていきたい。
アートとともにうっとりする時間のための音楽をキュレーションしていきたい。
それがわたしの願いです。
*2013年夏に開催された「貴婦人と一角獣」展(国立新美術館)。
音楽にはデュファイのシャンソン集(http://ml.naxos.jp/album/8.553458)が使用された。
==================================
途中が抜けていると気になると思いますので載せることにしました
OTTAVAメルマガ通信Vol.7 2014.11.12号
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
「人生、ほぼ音楽」 ゲレン大嶋
第2回「音が音楽として響く場所」
11月7日金曜日、めぐろパーシモンホールで開催された
「OTTAVA第2の開局記念ガラ・コンサート〜クラシック・モダン・ナイト」、
とてもいい夜になりました。近くから遠くから足を運んで下さったみなさん、
会場には来られなかったけれどもコンサートの成功を祈ってくださったみなさん、
このお祝いの夜を盛り上げるべく素晴らしい演奏を披露してくださったアーティストの
みなさん、コンサート・スタッフのみなさん、改めてありがとうございました。
演目も、正統派クラシックから、ミュージカルの名曲、現代の楽曲、風変わりな(?)
三線音楽まで幅広いジャンルのものが出そろって、OTTAVAらしさが感じられる楽しいものでした。
会場の雰囲気もとってもよかったですね。音が出ているのはステージの上なのですが、
その音が「音楽として響いている場所」は、客席のみなさんの頭上に広がる空間なのだ、
そんな印象を受けました。大きなホールがまるで小さなライヴ・カフェのように感じられ、
その親密な空間で、演奏家とお客さんが、一緒に素敵な音楽を囲んで、豊かで幸せな
ひとときを作ることができたのです。これは、OTTAVAとリスナーのみなさんとの
「有機的な関係」が生んだ「小さな奇跡」だと思います。
個人的には、舞台裏でも楽しいことがありました。
私は、本田聖嗣さんとココムジカ以外の演奏家のみなさんとは初めてお会いしたのですが、
ソプラノの鷲尾麻衣さんは、本田さんから「ゲレンが鷲尾さんの近所に住んでいて
その界隈でよくお酒を飲んでいる」という情報を聞きつけて話しかけてきてくださって、
ご近所飲み会へ向けての計画が進行中?そして、沖縄出身、テノールの与儀巧さんも
ココムジカの音楽に興味を持ってくださって、「近々一緒に泡盛を飲みましょう!」と
盛り上がっています。音楽とお酒が結ぶ縁から、また新しい何かが生まれると嬉しいですね。
唯一の心残りは終演後。ホワイエでサイン会をしながら、リスナーのみなさんとお話し
するのを楽しみにしていたのですが、あまりに盛りだくさんの内容だったので
コンサートの進行が遅れてしまい、ほとんど時間が取れませんでした・・・。ごめんなさい。
それでも、何人かのリスナーの方と直接お話しすることができて、また、みなさんの
歓喜にあふれたお顔を間近に見ることができ、とても嬉しかったです。
同時に、もっともっとみなさんに喜んでいただけるOTTAVAになっていかなければ!
と思いを新たにしました。
みなさん、心から感謝します。ありがとうございました!
そして、これからもOTTAVAをよろしくお願いします!
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
OTTAVAメルマガ通信Vol.6 2014.11.5号
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ナクソス名盤落穂拾い」第2回
ど〜も〜。
みなさん、ちゃんと変な曲聴いてますか〜!?
OTTAVA「変な曲大好き」推進委員会委員長の林田直樹です。
きょうは、まずは変わった曲を聴いて驚いたときのリアクションの練習から
まいりましょう。
1) まず大きく息を吸います。たっぷりと胸の奥まで!
2) 目をカッと見開きます。
3) 腹に力を入れて!
4) 一瞬息を止める!!
5) 「ん、なんじゃこりゃあ!!!」(と叫ぶ)
やりました?やりました?あはは。本当にやりましたねえ。
僕、そんな、あなたのことが好きですよ。
コツは、「なんじゃこりゃあ」の前にエネルギーを大きく溜めこんだ
「ん」が入るとこ。
え?なんでこんなばかばかしい真似をさせるのかって?
決まっているじゃないですか、健康にいいからですよ!
オモシロイ曲にびっくりするのは健康にいいんです。
驚くと、つい大きく呼吸しますよね。血行も良くなるし免疫力も高まる。
気分も晴れやかになる。いいことだらけってもんです!
前衛ばんざい!
さあ、今日の変な曲の名盤は、
「毎度お騒がせ」の作曲家、マイケル・ドアティの「フィラデルフィア物語/UFO」です。
http://ml.naxos.jp/album/8.559165
アメリカにはロズウェルというUFOの名所が知られていますが、
そこに由来する曲なんですが——
第1楽章:トラヴェリング・ミュージック
第2楽章:未確認(Unidentified)
第3楽章:飛行(Flying)
第4楽章:???
第5楽章:物体(Objects)
という、ほとんど冗談というかギャグみたい構成によっているのですが、
まさにキラキラと大空に光る未確認飛行物体が、目にもとまらぬ速さで、
妖しく飛び回る様子が描かれています。
「うお、あれは何だ!UFOだ〜!」
とつい叫びたくなるような金属的な異様な雰囲気が全編に漂っていて
(打楽器のキーンと共鳴する倍音が凄い)、まるで本当にUFOを
目撃したかのような気分になれます(笑)。
ドアティはいまやアメリカでも屈指の実力派作曲家で、ナクソスから
出ているCDはどれも本当に面白い。ユーモアがあって、音に個性があって、
スピードがあって、古い時代への憧れもある。
何よりも、パーカッションがかっこよく大活躍するし、分厚くて、迫力がある。
都会的な詩情もたっぷり。
そうそう、前半の「フィラデルフィア・ストーリー」の第3楽章は、
実はレオポルト・ストコフスキーとフィラデルフィア管弦楽団への
オマージュになっているんです。バッハの平均律からの引用もあったりして、
とても美しいところもあるのです。
早く日本のオーケストラもドアティの曲やらないかな〜。面白いのにー!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------
進化する音楽 音を楽しむって素晴らしい
第二回「応援する力 Part 1」森雄一
声優ってどんな仕事でしょうか。声によって演じる俳優のことですね。映画や
ドキュメンタリー、企業のPRビデオ、そしてアニメやラジオまで、声優の活躍
の幅は広がっています。私のようなラジオDJに依頼がくることもあります。
以前、とある企業のPRビデオで吹き替えをやりました。ロボットが、博士から
その企業の詳細を聞いていくもので、私は博士の役を演じました。台本に沿っ
てセリフを読んでいくのですが、練習したとはいえ、やってみるとなかなか難
しい。感情を込めてと簡単に言いますが、これほど難しいものとは思いません
でした。
現在、クール・ジャパンを代表するのがアニメやマンガ。マンガはともかく、
アニメは声優とキャラクターがマッチしていることが求められます。でも、
声優はトレーニングすることによって、いろんな声が出せる仕事でもあります。
アニメが人気になると、声優にも注目が集まります。逆に、人気声優が演じる
から視聴率が稼げるアニメもあります。声優がコンサートをやることもありま
すし、夏フェスの中にも声優に限定したものもあり、それこそチケットは即、
完売します。そう、声優は人気アイドルでもあるです。
ラブライブというプロジェクトがあります。雑誌やCDリリース、アニメ、コン
サート、ラジオ、さらにゲームなど、ラブライブのコンテンツにいろいろな
メディアがミックスすることにより、その声優たちが人気になり、いよいよ今
年は紅白歌合戦かという勢いになっています。
2010年にプロジェクトが発表され、2013年にアニメ化されたことにより人気が
決定づけられ、今年はアニメ第2期が放映されました。ラブライブの最も特徴
的なのは、9人のスクールアイドルが、PVやアニメ通りにコンサートで歌い、
踊ること。これだけではよくわかりませんね。
国立音ノ木坂学院に通う女子高生9人が、廃校寸前の自校を守るため、スクー
ルアイドルを結成。スクールアイドルの祭典、ラブライブに出場し、全国大会
で優勝、結果、学校の危機を救うというストーリー。要所に出てくる歌や踊り
のパフォーマンス。これを9人が実際のステージでも再現するのです。
このサクセスストーリーがとても感動的で、私もアニメオタクの友人から勧め
られ、一話見ただけでファンになりました。楽曲の良さはもちろん、廃校を
阻止するためにひたすら前進し、立ちはだかる壁を次々に突破していくところ
に勇気をもらい、共感するのです。
ラブライブがこれほどまでに人気なのは、応援するファンが多いからですが、
ファン層は10代から20代の男女が中心のようです。でも、おじさんだって虜に
なるラブライブは、コンテンツがしっかりしているので老若男女に愛されてい
るのだと思います。次回は、ラブライブの魅力をさらに深く掘り下げていきま
す。
----------------------------------------------------------------
********************************************
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」
by 本田聖嗣
第2回目 「G線上のありゃ?」
クラシック音楽の曲名や作曲家名は、オリジナルがヨーロッパの言語のものが
多いので、翻訳表示に迷う・・というのが前回のテーマでしたが、翻訳には、
誤訳もまたつきものです。
これは実際に、私の先生からうかがったエピソードですが、その先生は、
「G線上の空気」と書かれた楽譜を見たことがあるのだそうです。
もちろん、J.S.バッハの「G線上のアリア」が正解ですね。
イタリア語で「アリア(Aria)」は英語で、Airと表示するので、それを
「空気」と勘違いした、という単純な誤訳ですが、それにしても、
翻訳した人は、そのおかしさに気づかなかったのでしょうか・・それとも空気
を読んだつもりだったのか・・・はわかりませんが、今では、さすがにこんな
にひどい誤訳はなくなりました。
また、インターネットの発達によって、例えば、映画の字幕の有名翻訳家の方
の翻訳でも、一般視聴者によって「おかしい」と指摘されることも多くなって
います。映画「スターウォーズ」の字幕翻訳が、映画で指摘されてDVDで修正
された例や、最近では「アナと雪の女王」の「Let it go」の歌詞翻訳が、
原語と意味合いがかなり違っている・・と指摘された例などが、あります。
生物科学論文のコピペ疑惑も、インターネットの指摘から発覚したわけで、
インターネットの発達は、藝術や学術分野の翻訳の環境にも、大きく影響する
ようになってきた、といっていいでしょう。
クラシック音楽の「輸入」は明治時代に始まっているわけですから、
日本の近代翻訳の歴史とシンクロしていますが、それでも難しい点があります。
先日、こんなことがありました。NHKの放送でのことなのですが、曲の題名で
問題が起こったのです。もともと、国営放送局では、「宣伝になるから固有名
詞はダメ」ということで、山口百恵さんの歌の歌詞の中の
「真っ赤なポルシェ」というフレーズが「真っ赤な車」に変えさせられた、
というのは有名な話です。最近では、番組で矢沢永吉さんが
「翌年はポルシェに乗っていたからねえ」と発言しているぐらいですから、ず
いぶんと変わったな・・と思うのですが、ことクラシックの曲名に関しては、
「定款」というものがあり、例えば、「BWV」ではなく「バッハ作品番号」と
言わなくてはいけないとか、シューマンの「献呈」という作品は、必ず
「君に捧ぐ」と表現しなくてはいけないとか、それぞれ厳格に決められている
のです。これは、クラシック音楽の題名・作曲家名等の日本語での表記の幅が
ありすぎると、混乱が起こる、ということで、その昔に統一した、ということ
なんでしょう。その意義は理解できる一方、「バッハ作品番号」は、もう
「ビー・ダブリュー・ブイ(OTTAVAではこう表現しています)」と、現在では
表現しても良いのではないか・・と多少、古さも感じます。
「恋人よ、さあこの葉で」と書いてあったのです。これは、モーツアルトの
オペラ、「ドン・ジョヴァンニ」のツェルリーナのアリアで、どう考えても、
これは「さあ、この薬で」が正解、葉っぱで薬なら危険ドラックではない
か・・とツッコミを入れていたのですが、放送局の「定款」では確かに、そう
いう表記なんだそうです。ツェルリーナは、葉、とは決して歌っていないので、
現場のスタッフ一同の判断で、放送では、「薬」に直しましたが、定款は、ま
だ「葉」のママです。
おそらく、真相は、アリアの内容を知らない方が、登録するときに、漢字の
「薬」と「葉」が似ているので間違って打ち込んだのだと思います。驚くべき
は、放送局の長年の歴史の中で、そのことが「1度も」指摘されていなかった
ことで、オペラとしての「ドン・ジョヴァンニ」は、何回も演奏されていても、
このアリアだけが、単独で、曲名と共に放送されることがなかった・・という
ことなのではないか・・と推測しています。そんなのは、「序盤に」訂正して
おくれよ・・というのは私のダジャレです。
ちなみに、そのアリアを見事にお歌いになったのは、今度のOTTAVA「第2の開
局ガラ・コンサート」にも出演してくださる、ソプラノの鷲尾麻衣さんです。
コンサートでは、イタリアオペラの華、プッチーニや、ヴェルディを歌ってく
ださる予定になっているので(伴奏は支配人ならぬ司会の私が務めさせていた
だきます。)、ぜひ、彼女の生の歌声を聞きに、会場にいらっしゃってくださ
い!
クラシック音楽に関しての、翻訳・誤訳にまつわる珍騒動は、まだまだ続きま
す。
********************************************
==================================
「音楽キュレイターのアートなおしゃべり」
高野麻衣
美術館の展示室には、基本的にBGMがありません。
絵画や彫刻を愉しむときは静寂に浸りたい。思索したい。
あるいは作品から音楽をききとりたい、というひともいるでしょうから、
そうあってしかるべきだと思います。
それはそれとして、音楽好きのみなさまにオススメしたいのが
進化した「音声ガイド」。鑑賞のペースが乱れるから、と
利用しない人も多いとおもうのですが、いまのガイドは環境音楽と
アナウンサーの語りだった一昔前とはまるで違います。
これに気づかせてくれたのが、昨年夏、国立新美術館で開かれた
「貴婦人と一角獣」展。パリのクリュニー中世美術館からやってきた
タピスリーは、西暦1500頃、名門貴族ル・ヴィスト家のために制作されたもの。
6枚の巨大な装飾用織物が、高い天井のホールにずらりと並んでいました。
とある事情で音声ガイドを使用していた私は、ホールの入り口で、
目の前一面に広がった千花模様(ミル・フルール)と、耳元で流れ出した
デュファイのシャンソンに、鳥肌が立つほど感動したのです。(続く)
==================================
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
「人生、ほぼ音楽」 ゲレン大嶋
第1回「午後のギター」
音楽って不思議です。なぜ、聴く者に止め処ないきれいな涙を流させることが
できるのか?なぜ、固く閉じていた心を溶かし笑顔を誘うことができるのか?
なぜ、たった数分の音の波がその曲に魅入られた者の、人生を左右するほどの
影響力を持つことができるのか?
音楽という名の深遠なる海の彼方にあるその答えを見つけ出すことは難しいか
もしれません。でも、きっと、人生を限りなく豊かにしてくれる最高の友であ
ることは間違いありませんよね。
このコラムでは、素敵なクラシック音楽をセレクトしてみなさんにお届けする
OTTAVAプレゼンターであり、自ら作曲をし、三線を奏でるミュージシャンであ
る私、人生の大半の時間を音楽に捧げてきた私、ゲレン大嶋の視点で選んだ、
人生を豊かにしてくれるおススメ音楽情報をメインに、時には、大好きなお酒、
猫、演奏旅行などのお話も交えながらお送りしていこうと思います。どうぞお
付き合いください。
OTTAVAのコンピレーションCDの第2弾「午後のギター」についてです。
正直なところ、OTTAVAプレゼンターになる前は、クラシックのギター音楽につ
いて、それほど詳しいワケではありませんでした(今でもまだまだ探究中なん
ですけどね)。しかし、番組のための選曲をしながら、
ラテン・アメリカの作曲家たちの作品を中心にギターものを聴きあさるうちに
みるみるその素晴らしい音世界に魅せられていったのです。
ギターという楽器は、クラシック界ではけっして大きな注目を集める存在では
なく、むしろポピュラー・ミュージックの世界で高い人気を誇っていますが、
そのポップスのギター音楽、例えば、ジョアン・ジルベルトに代表される
弾き語りのボサノヴァ、優しい音の風を吹かすハワイアン・スラック・キー・
ギター、ゴンチチのおふたりの快適音楽などがお好きな方で、
でも、クラシック・ギターはあまり聴いたことがない、なんていう人にもぜひ
聴いて欲しいんですよね(もちろん、OTTAVAリスナーのみなさんはクラシック
がお好きですが)。
きっとより豊かな音楽ライフの新しい扉が開くと思うのです。ぜひクラシック
にはあまり触れていないけれど音楽はお好きというお友達にも聴かせてあげて
ください。
コンピレーションCD第2弾「午後のギター」には、様々な空間・時間を
心地よく演出してくれるBGMとしても最高で、それでいて、1曲1曲とじっくり
向き合うと、ギターの響きを存分に生かすコンポジションの機微、楽曲として
の奥深さを感じることができる、ギター音楽の名曲をたっぷり詰め込みました。
まさに「一家に一枚」なアルバムです。ぜひぜひ聴いてくださいね。よろしく
お願いします♪
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第1回「ナクソス名盤落穂拾い」
みなさん、どーも。
OTTAVA「変な曲大好き」推進委員会委員長の林田直樹です。
クラシック音楽というと、きっと多くの方々は、「真面目」で「ロマンティッ
ク」で「お上品」な音楽ばかりだというイメージを持たれていらっしゃるんじ
ゃないでしょうか?
でも…もうお分かりですよね…本当は、全然そうじゃないってことを!
さあ、これからは私、林田直樹が、このメルマガでは全くの別人格に変貌して、
妖しい変態的なクラシック音楽ばかりをご紹介し、善良なリスナーの皆さんを、
悪の道へと引きずり込みますので、覚悟してください!(あ、普段と変わらな
いか…)
トマ・ブロシュの「オンド・マルトノ作品集」。
http://ml.naxos.jp/album/8.555779
はっきり言って、このアルバムは、あなたの中の「変な」感覚をいっぱい刺激
してくれるという意味で、画期的な1枚。ナクソス・レーベル屈指の名盤とし
て、不動の評価を得ていると言っても過言ではありません。
私もこのアルバムで、ずいぶん洗脳され、元の身体には戻れなくなってしまい
ました。
フランス・アルザス地方のコルマールに1962年に生まれたトマ・ブロシュは、
オンド・マルトノという近代クラシック音楽が生んだ特殊な電子楽器の演奏家
であるのみならず、グラスハーモニカ、クリスタル・バスケット、ウォーター
フォンなど変わった楽器を得意とする、極めてユニークな音楽家です。作曲家
としても素晴らしい。
このアルバム、とにかく、すべての音が、イカれています。そして異様に美しい。
バラバラでは、たまにOTTAVAでもかかりますが、1枚丸ごと聴くことで、どん
どんアブナイ世界にはまっていく強烈な効果があります。
しかもわかりやすい。気持ちいい!
これがクラシック音楽なのだとしたら、これは様式化し形骸化したロックやジ
ャズよりも、よほど過激じゃないか!と誰しもが思うはず。
さあ、私と一緒にこのアルバムを聴いて、倒錯の音の世界へ一緒に旅立ちまし
ょう!
二度と元の身体には戻れませんよ、ウフフフフフ…。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------------------
進化する音楽 〜音を楽しむって素晴らしい〜
第一回「ミクとの出会い」 森雄一
かつて秋葉原にはいろんな部品を買いに行ってました。ラジオやトランシバー
といったものを組み立てるため、科学雑誌に載っている設計図を元に、ひとつ
ひとつパーツを買い求め、家に帰ってはんだ片手に基盤にパーツを埋め込む。
やがて求めるものが完成し、一喜一憂していたものでした。
いつのまにか秋葉原はオタクの街として発展するわけですが、街の様相も劇的
に変わりました。コスプレのお嬢さん、リュックを背負ったいかにもオタクの
人。カップルもここでしか似合わないようなコスチュームに身を包んで笑顔で
街を闊歩する。
私も今や電気の街としてここに通っているわけではありません。
初音ミクに会うために行ったこともあります。ええ、コンサートです。
初音ミクはしょせん音声合成ソフト。でも、その形は具現化され、
今や萌えキャラ以上の存在感を放っています。
私と初音ミクの出会いは4年前。ゲーマーである私は愛機のPSPで、
あるゲームの体験版をDLしました。「初音ミクProject DIVA 2nd」リズミカル
な音楽が流れ、それに合わせてボタンを押すという、いわゆる音ゲー。
音楽にノラなければなかなか成功せず、ただ「難しい」。
でも、一方で音楽がとてもユニークだということに気付きました。
「ぽっぴっぽー」、「愛言葉」。これは曲のタイトルです。
言葉をつなぎ合わせて歌わせる、だから言葉が聞き取りづらい。最初は何だこ
りゃ、でしたが、気付けばそのゲームを買っていました。それからです。
楽曲を通して、なぜ作者はこのような歌詞を書いたのか、どんなメッセージを
伝えたいのかが明確に分かるようになり、そこにはすべて初音ミクに対する深
い愛情があったのです。ゼロからスタートして、機械に歌を歌わせる。表現は
いびつでも、主張することは明確です。
「俺、曲を作ったよ。ミクに歌ってもらったよ。」
制作者は自身のことを「P」と呼んでいます。プロデューサーの「P」。
すべてパソコン上で作ることができ、ソフトウェアとしての初音ミクも性能が
向上しているので、動画サイトに次々にアップされる楽曲のレベルも上がって
います。
カラオケに行けば、人気曲の上位を占めるのは、ミクを筆頭としたボーカロイ
ドのナンバー。代表曲の「千本桜」は、メジャーアーティストもカバーしてい
ます。Pの多くは一般人。そこからメジャーになった人もいます。人生を一変
させることもできるボーカロイドはなんてすごいのでしょう。
まだ、一度も初音ミクの音楽に触れたことがない人は動画サイトで見てみて下
さい。決して色眼鏡で見ないこと。純粋に「音楽」として聞いてみて何を感じ
るか。私と同じ思いをするかもしれません。
----------------------------------------------------------------
=================================================================
第1回
「音楽キュレイターのアートなおしゃべり」 高野麻衣
いよいよはじまった新生OTTAVA。
時を同じくして、新国立劇場の2014/2015シーズンが、神聖にしてスペクタク
ルな祝典劇『パルジファル』で開幕しました。
番組でもお伝えすると思いますが、初日に劇場を訪れたわたしを包んだのは
「オペラほどの芸術があるだろうか」というため息のような喜びでした。
舞台に現れるまばゆい光。
人々の喜びや苦悩を包みこんでいく、ワーグナーの音楽。目にも耳にも——
あるいはホワイエに溢れる白粉の匂いやドレスの質感、そして幕間に楽しむシ
ャンパンも含めて——オペラはいつも、わたしに最上級のときめきを与えてく
れます。
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触角。人間の五感のうちどの感覚に敏感か、考えた
ことはありますか?
おそらくみなさま同様、わたしも聴覚派です。映画を観ていても、なにげない
音楽やセリフばかりが耳に残る。
反対に、たとえばマンガ家の友人などは完全なる視覚派。一緒に観た映画の、
私が気にも留めなった映像の一コマを切り取り微分解析するように説明してく
れるので、すごくトクした気分になります。
一般的に男性は視覚に、女性は聴覚に敏感であるとも言われていますよね。
鳥のメスが、オスの鳴き声でつがいを選ぶように、ガールズトークに
「あの男性の声、いいよね」という評価軸があるのもそのためだとか。
でも「声なんかより見た目でしょ!」という女子ももちろん多い。視覚だけ、
聴覚だけでは満足できない。
ぜんぶほしいのが女子(?)のサガ。それならば、音楽だってアートだって人
生だって、ぜんぶ一緒に楽しみたい!
——このコラムでも、そんなときめきと知への喜びを分かちあえたら幸いです。
================================================================
**********************************************************************
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 本田聖嗣
第1回目 「現地語のユウウツ」
旧ソビエトのグルジア共和国が、日本語での表記を現在のグルジアから、英語
での表記にあわせて、ジョージアという国名表記になりそうだというニュース
がありました。これは、日本側がそうしたわけではなく、
グルジア(と現在我々が呼称している国)の方から、度重なる要請があったか
らだそうで、日本政府も、ついに変更を検討し始めた、ということのようです。
グルジア、という呼び方は、ロシア語由来のものだそうです。しかし、ソビ
エト連邦解体以来、外国となり、さらには、元のソビエト連邦の盟主ロシアに
対して、2008年のオリンピック期間中の軍事衝突などで、対立感情が高まって
いるなかで「グルジア」と呼ばれることに、現在の国は、違和感を感じている
から、とのことだそうです。
一方、ジョージア、というのは、グルジアのいわば英語読み(もともと聖人ゲ
オルギウスが守護聖人の国、というぐらいの意味)で、確かに英語圏諸国は、
かの国のことを、ジョージア、フランス語でも、ジェオロジーと「ジョージ
ア」系統の呼び方をしていますが、これは、西欧語寄り、の呼び方で、本来の
地元の言葉、グルジア語(現在は我々はこう言うしかありません)では、
「サカルトベロ」という国名になるのだそうです。
日本語における外来語・外国語名は、現地の土着の言葉に準じる場合が多い
ので、サカルトベロ共和国、となるべきなのでしょうが、現・グルジア共和国
自身が「ジョージアと呼んでくれ」と言ってきているのですから、ちょっと話
は複雑です。
音楽の父のことを、彼の母国語であるドイツ語で「バッハ」と呼んでいますが、
彼は、英語でもフランス語でも「バック」と呼ばれていて、同じ綴りの米国の
管楽器メーカーなどは、日本でも「バック」と呼ばれています。でも、今、
「バックのミサ曲」などとOTTAVAでご紹介しても、「後ろの典礼曲?」
と勘違いされるのがオチです。そして、ドイツ語では、彼のファーストネーム
を、ヨハン・セバスチャンという場合より、ヨハン・ゼバスチャンと読む場合
が多い地域もありますが、これも、なぜか、ヨハン・セバスチャンに統一され
ています。
ヘンデルだって、有名なのは、人生の後半の「メサイア」のようなオラトリオ
作品ですが、彼がこれを書いたときは、既に、「イギリス人」になっていまし
た。移住するだけでなく、帰化しちゃったんですね。だから、「ゲオルグ・フ
リードリヒ・ヘンデル」ではなく、「ジョージ・フレデリク・ハンデル」と呼
ぶのが、現地語=英語、主義、ということになるはずですが、ドイツ語読み、
ということは、ここでは、「生国主義」が貫かれています。
一方で、ポーランド生まれの、ショパン。CHOPINというスペルを「本当のポー
ランド語読み」にすると「フオピン」に近くなるそうですが、フランス移民で
あったショパン家は、ポーランドでも、外来の一族として「ショピン」と若干
フランス語寄りの発音で呼ばれていたらしく、こうなると、「生国主義」でも
なくなります。
中には、リストのように、ハンガリー生まれではあるのだが、LISTと書いてし
まうと、ハンガリー語では「リシュト」と読まれてしまうので、ドイツ系のフ
ァミリーであることを誇示するために、ハンガリーでも「リスト」と読まれる
ように「LISZT」とわざわざZを入れた、などという「読まれ方確信犯」・・
まあこれは日本語でも問題は無いわけですが・・・の人もいます。
**********************************************************************
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 本田聖嗣
第1回目 「現地語のユウウツ」
旧ソビエトのグルジア共和国が、日本語での表記を現在のグルジアから、英語
での表記にあわせて、ジョージアという国名表記になりそうだというニュース
がありました。これは、日本側がそうしたわけではなく、
グルジア(と現在我々が呼称している国)の方から、度重なる要請があったか
らだそうで、日本政府も、ついに変更を検討し始めた、ということのようです。
グルジア、という呼び方は、ロシア語由来のものだそうです。しかし、ソビ
エト連邦解体以来、外国となり、さらには、元のソビエト連邦の盟主ロシアに
対して、2008年のオリンピック期間中の軍事衝突などで、対立感情が高まって
いるなかで「グルジア」と呼ばれることに、現在の国は、違和感を感じている
から、とのことだそうです。
一方、ジョージア、というのは、グルジアのいわば英語読み(もともと聖人ゲ
オルギウスが守護聖人の国、というぐらいの意味)で、確かに英語圏諸国は、
かの国のことを、ジョージア、フランス語でも、ジェオロジーと「ジョージ
ア」系統の呼び方をしていますが、これは、西欧語寄り、の呼び方で、本来の
地元の言葉、グルジア語(現在は我々はこう言うしかありません)では、
「サカルトベロ」という国名になるのだそうです。
日本語における外来語・外国語名は、現地の土着の言葉に準じる場合が多い
ので、サカルトベロ共和国、となるべきなのでしょうが、現・グルジア共和国
自身が「ジョージアと呼んでくれ」と言ってきているのですから、ちょっと話
は複雑です。
つづく
音楽の父のことを、彼の母国語であるドイツ語で「バッハ」と呼んでいますが、
彼は、英語でもフランス語でも「バック」と呼ばれていて、同じ綴りの米国の
管楽器メーカーなどは、日本でも「バック」と呼ばれています。でも、今、
「バックのミサ曲」などとOTTAVAでご紹介しても、「後ろの典礼曲?」
と勘違いされるのがオチです。そして、ドイツ語では、彼のファーストネーム
を、ヨハン・セバスチャンという場合より、ヨハン・ゼバスチャンと読む場合
が多い地域もありますが、これも、なぜか、ヨハン・セバスチャンに統一され
ています。
ヘンデルだって、有名なのは、人生の後半の「メサイア」のようなオラトリオ
作品ですが、彼がこれを書いたときは、既に、「イギリス人」になっていまし
た。移住するだけでなく、帰化しちゃったんですね。だから、「ゲオルグ・フ
リードリヒ・ヘンデル」ではなく、「ジョージ・フレデリク・ハンデル」と呼
ぶのが、現地語=英語、主義、ということになるはずですが、ドイツ語読み、
ということは、ここでは、「生国主義」が貫かれています。
一方で、ポーランド生まれの、ショパン。CHOPINというスペルを「本当のポー
ランド語読み」にすると「フオピン」に近くなるそうですが、フランス移民で
あったショパン家は、ポーランドでも、外来の一族として「ショピン」と若干
フランス語寄りの発音で呼ばれていたらしく、こうなると、「生国主義」でも
なくなります。
中には、リストのように、ハンガリー生まれではあるのだが、LISTと書いてし
まうと、ハンガリー語では「リシュト」と読まれてしまうので、ドイツ系のフ
ァミリーであることを誇示するために、ハンガリーでも「リスト」と読まれる
ように「LISZT」とわざわざZを入れた、などという「読まれ方確信犯」・・
まあこれは日本語でも問題は無いわけですが・・・の人もいます。
つづく
日本語でご紹介するときは、こうやって常に「何語で読もう?」という問題が
ついてまわるわけで、有名作曲家や作品なら、ある程度日本での習慣的な読み
方ができあがっているものの、厳密に考えると「?」がつくことも多いのです。
OTTAVAは特に、生放送なので、お話ししながら、「ハンデルって言いたい
な・・・バックって言ってみようかな・・・」などと、日夜悩んでおります。
ちょっと大袈裟ですが。
でも、グルジア共和国の表記が、ジョージア共和国、になったら、やっぱり、
日本の多くの人は、一旦、アメリカのジョージア州や、缶コーヒーを思い浮か
べながら、「いや違う違う、ロシアの南にあって、コーカサスの国」・・・と
思い直す、ことになるような気がします。
外国の名前の呼び方には、悩みはつきません。
**********************************************************************
音楽の父のことを、彼の母国語であるドイツ語で「バッハ」と呼んでいますが、
彼は、英語でもフランス語でも「バック」と呼ばれていて、同じ綴りの米国の
管楽器メーカーなどは、日本でも「バック」と呼ばれています。でも、今、
「バックのミサ曲」などとOTTAVAでご紹介しても、「後ろの典礼曲?」
と勘違いされるのがオチです。そして、ドイツ語では、彼のファーストネーム
を、ヨハン・セバスチャンという場合より、ヨハン・ゼバスチャンと読む場合
が多い地域もありますが、これも、なぜか、ヨハン・セバスチャンに統一され
ています。
ヘンデルだって、有名なのは、人生の後半の「メサイア」のようなオラトリオ
作品ですが、彼がこれを書いたときは、既に、「イギリス人」になっていまし
た。移住するだけでなく、帰化しちゃったんですね。だから、「ゲオルグ・フ
リードリヒ・ヘンデル」ではなく、「ジョージ・フレデリク・ハンデル」と呼
ぶのが、現地語=英語、主義、ということになるはずですが、ドイツ語読み、
ということは、ここでは、「生国主義」が貫かれています。
一方で、ポーランド生まれの、ショパン。CHOPINというスペルを「本当のポー
ランド語読み」にすると「フオピン」に近くなるそうですが、フランス移民で
あったショパン家は、ポーランドでも、外来の一族として「ショピン」と若干
フランス語寄りの発音で呼ばれていたらしく、こうなると、「生国主義」でも
なくなります。
中には、リストのように、ハンガリー生まれではあるのだが、LISTと書いてし
まうと、ハンガリー語では「リシュト」と読まれてしまうので、ドイツ系のフ
ァミリーであることを誇示するために、ハンガリーでも「リスト」と読まれる
ように「LISZT」とわざわざZを入れた、などという「読まれ方確信犯」・・
まあこれは日本語でも問題は無いわけですが・・・の人もいます。
つづく
**********************************************************************
「音楽とユーモア、もしくはドタバタ協奏曲。」 本田聖嗣
第1回目 「現地語のユウウツ」
旧ソビエトのグルジア共和国が、日本語での表記を現在のグルジアから、英語
での表記にあわせて、ジョージアという国名表記になりそうだというニュース
がありました。これは、日本側がそうしたわけではなく、
グルジア(と現在我々が呼称している国)の方から、度重なる要請があったか
らだそうで、日本政府も、ついに変更を検討し始めた、ということのようです。
グルジア、という呼び方は、ロシア語由来のものだそうです。しかし、ソビ
エト連邦解体以来、外国となり、さらには、元のソビエト連邦の盟主ロシアに
対して、2008年のオリンピック期間中の軍事衝突などで、対立感情が高まって
いるなかで「グルジア」と呼ばれることに、現在の国は、違和感を感じている
から、とのことだそうです。
一方、ジョージア、というのは、グルジアのいわば英語読み(もともと聖人ゲ
オルギウスが守護聖人の国、というぐらいの意味)で、確かに英語圏諸国は、
かの国のことを、ジョージア、フランス語でも、ジェオロジーと「ジョージ
ア」系統の呼び方をしていますが、これは、西欧語寄り、の呼び方で、本来の
地元の言葉、グルジア語(現在は我々はこう言うしかありません)では、
「サカルトベロ」という国名になるのだそうです。
日本語における外来語・外国語名は、現地の土着の言葉に準じる場合が多い
ので、サカルトベロ共和国、となるべきなのでしょうが、現・グルジア共和国
自身が「ジョージアと呼んでくれ」と言ってきているのですから、ちょっと話
は複雑です。
つづく