『ブリキの太鼓』
- カテゴリ:小説/詩
- 2009/12/10 12:21:54
ドイツの作家ギュンター・グラスの1959年の長編小説。主人公オスカルは生まれながらにして明晰な頭脳を得るが、それと引き換えにか、3歳の誕生日に家の地下倉庫に転落することを選び、自ら肉体的成長を止めてしまう。そんな永遠の3歳児オスカルが、誕生日に買い与えられたブリキの太鼓を打ち続けながら、第二次世界大戦期のポーランド、戦後に移住するドイツを舞台に、次々と事件を引き起こしながらも孤独に生きていく物語。
この小説は相当長いが、とにかく圧倒されるのは、主人公がいろんな人に出会い、そこで繰り広げる奇奇怪怪でグロテスクでナンセンスなエピソードの数々と、それに費やされるあまりに膨大で細く具体的な記述や描写だ。例えば、オスカルは母と父(オスカル本人は本当の父とは思っていないのだが)とともにバルト海の海岸へ出かける。そこにいた港湾労働者が釣りに仕掛けた死んだ馬の頭部を引き上げる。馬の頭からは細長い鰻が
ひょろひょろと這い出て、たまらず母は嘔吐する中、オスカルは歓喜の太鼓を叩き続ける…。
また、オスカルには、声でガラスを割ることのできる特殊な能力が備わっていて、人々を魅了する太鼓のリズムという特技とともに、様々な仕事をして戦中戦後を生き延びていく。石工、ヌードのデッサンモデル、ジャズバンド…。そのどれもが詳細で、かつなぜか嫌味が無い。
そのように微に入り細を穿つような記述が蓄積されている一方で、それらを貫く歴史、特にナチツドイツの台頭とそれに急速に近付いていく市民たち、自由都市ダンツィヒ(第一次大戦後ポーランドが経済権を保持したが、政治的にはナチスが支配的だった)の矛盾、ポーランド郵便局の抵抗、戦後、今度は急速にソ連に擦り寄ってゆく人々など、1930~1950年代のポーランドやドイツの時代状況をも記述していく。
だからといって社会派的な作品かというと決してそうではなく、物語の主軸はあくまでオスカルの個人史であり、その歴史も単なる英雄伝だけにとどまらず、人間臭い失敗や恋愛における挫折も書かれている。
大河のような歴史の流れと、その大河に敷かれた小石の一つ一つまで描写する執拗な細かさ、これが圧倒的な描写力と分量で同居して、読めば読むほど現実と非現実が入り乱れて混乱し、わかったようでいた我々の世界が全く分からなくなる…、まさに小説の魅力を凝縮した作品。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%81%AE%E5%A4%AA%E9%BC%93-%E7%AC%AC1%E9%83%A8-%E9%9B%86%E8%8B%B1%E7%A4%BE%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%82%AF-2-2/dp/4087600378



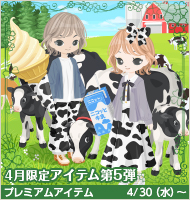











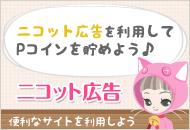


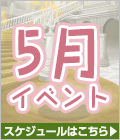








ブリキの太鼓は高校のときに、映画のヴィデオを見たことがあります。
かなり後で気が暗くなった記憶があります。
その後、強制収用所やアンネの家を見学したり、ナチスや当時のドイツについていろいろ読んだりした大人になった今、もう一度このブリキの太鼓を読んだり見たりすると、また違った角度から鑑賞できるのではと思っています。
ナチスの集まりで、兵隊の行進場面、あそこでオスカーが行進曲からワルツに変えていき、みんなが美しき青きドナウを踊るシーンは傑作の皮肉でしたね。