学校襲撃から一夜明けて
- カテゴリ:コーデ広場
- 2025/05/09 11:59:49
大切な人と場所を守ります♡
もらったステキコーデ♪:17
一夜明けて、各社の論調は、「学校防犯のむつかしさ」を述べる記事が目立った。
例えば 毎日新聞
・「防ぎようがない」 小学校侵入・暴行事件で浮かぶ学校防犯の難しさ
https://news.yahoo.co.jp/articles/33f669d65d33db998dfab30f58bd3ee719c2a312
5/9(金) 6:15配信
東京都立川市の市立第三小学校で教職員5人が負傷した事件で、暴行容疑で逮捕された容疑者2人は、この小学校に在籍する2年生の母親の知人らだった
2人は母親から連絡を受けて無施錠の門と出入り口から校舎内に入ったとみられる。
出入り口を全て施錠すれば外部からの侵入は防ぐことができるが、施錠の徹底が難しい側面がある上、保護者の訪問は拒めない。
事件は学校現場に難しい問題を突きつけている。
「同じような手法で来られたら、いくら施錠を強化しても事件は防げないと思う」。事件後、都内のある公立小の校長はこう漏らした。
立川市教育委員会によると、事件が起きた小学校では、通常児童が出入りする門には門扉があり、かんぬきで固定されていたが施錠はしていなかった。
児童間のトラブルを巡って保護者が学校側と話し合いをし、終了後しばらくしてから母親が男性2人を連れて来校。無施錠の門から敷地に入り、無施錠の出入り口から校舎内に入った可能性が高い。
◇ガイドライン「施錠すべき」明示せず
文部科学省は、各学校が作成する「危機管理マニュアル」の「評価・見直しガイドライン」で不審者対策として校門や出入り口の施錠を例に挙げているものの、施錠すべきとは明示していない。
校門に鍵を付けた上で登下校時のみ解錠し他の時間帯はインターホンで来校者を確認するケースや、かんぬきや門落としで門を固定しつつ来校者が自ら開門できるケースなど、実態はさまざまだ。
立川市でも一部の小学校では門に電子錠を付けていたが、施錠に関するルールは定めていなかったという。
遅刻・早退する児童、給食や教材の配送への対応など、校門を開ける機会は登下校時間帯以外にも多いことが要因といい、来校者が来るたびに解錠すると教職員の負担は増す。
冒頭の校長は「遅刻する子は近年増えていると感じるが、簡易な鍵でも閉めた門の前で開け方が分からず泣いている子もいる。かといって、教職員が張り付いて解錠している余裕はない」と話す。
その上で「保護者を名乗られたら入校は拒めない。入校証を貸し借りされたら第三者の侵入は防ぎようがない」と話した。
◇警備員の配置は8%
校舎への出入りをどのように制限するかも課題がありそうだ。
玄関近くに事務室や職員室がある学校の場合は、出入りする来校者に入校証を渡し、不審な言動がないかを確認することも可能だ。
ただ、校舎にはさまざまな出入り口がある。今回の事件について市教委は、容疑者側が教室棟と体育館をつなぐ渡り廊下の出入り口から校舎に入ったとみている。
児童が頻繁に使う通路で施錠はされていなかったといい、校舎の構造を知っていた容疑者が常時開放されている出入り口を狙った可能性もありそうだ。
文科省が実施している学校の安全管理の取り組み状況調査によると、最新の2023年度時点で、不審者侵入防止対策として玄関にインターホンを設置している学校は60・2%、防犯カメラを設置している学校は64・6%だった。
立川市でも防犯カメラは設置していたが、モニターに容疑者らが映っていたかどうかについて市教委は「確認しているかどうか含めて不明」としている。
警備員を配置している学校は8・0%にとどまっており、9割超の学校では不審者対応を教職員が担っている状況だ。
(以下略)【斎藤文太郎】
・・・
①学校防犯
大阪では教育大付属池田小学校襲撃事件以後、各校の出入りが大変厳しくなった。
名古屋に比べれば大阪の学校はガバガバ、私立に比べて公立校の警備やゆるゆるであることは、今も昔も変わらず、
幼稚園や中学以上の学校に比べても なんで小学校はあんなに開放的なんだろう??と感じることは多いが、
それがまあ 小学校は小学校である由縁なんだろう。
というか 明治時代に地元民の拠出金によって建てられた小学校というのは、地域の共有財産としてコミュニティの中心にあったからこそ、敷地を縁取る木々の外を、時代の要請にあわせて塀でかこったとしても、校舎からこぼれ落ちる子供達の声や時には教師たちの声・音楽などが、親しみやすい雰囲気を醸し出しているのではないだろうか?
実際には、新設校はもちろん 創立100年以上の小学校も今では警備は厳重で そんな簡単に部外者が入れるものではないシステムをとっている市も珍しくない。
私も仕事柄 何年も複数の自治体の幾多の学校訪問を重ねてきたが、基本的には 毎回インターホンで呼び出してオートロックを外してもらっての入校があたりまえであった。
登下校時間や食材などの搬入時間も厳しく決められ、常時解放の出入り口はないのが当たり前、そういう市も珍しくない。
(このあたりは 市によって 案外ルールが違う。
平たく言えば 安全対策も市教委の定めたルールと議会の承認を経た予算措置によって決まるのである)
・公立校の場合、一部住民の感情とか 議員の思惑によって、
警備上の運用方針がブレやすいのが欠点である。
だから文科省も「広い視野で」取材には答えざるを得ないのだけど・・
私学だったら、児童・生徒・学生(制服を着てる人)以外の入校者に対しては、
門脇のボックス常在の警備員が身分証の提示をもとめ、入校目的を訪ね、職員室に連絡を取って、面会予定者が校門まで迎えに来るシステムをとっている所が 当たり前に存在している。
だから、銀行・百貨店なみの侵入者防止策をとることは実は容易なのである。というか現実にはそれを行っている学校だって珍しくないのである。
・それを阻むのは 一部特定集団が唱えるイデオロギーであり、一部地域では、今も残る学校に対する愛着というか地域の郷愁(明治時代 自分たちが建てた学校・オラのモノ意識)かもしれない。
・令和の時代 子供達・児童生徒の安全を第一に考えて、日本全国に一律に学校警備の厳格化を実施するように文科省が動いてもよいと思うのだが。
そして地方自治体も必要な安全設備維持費をきちんと負担すべきである。(予算の優先配分を!)
国も整備費の半額負担くらいの補助金は出せ!
・そもそも 保育所・中学校に比べても 小学校の警備がカバカバであることそのものが、運営者のためらい、一部特定集団への忖度優先であることの証明みたいなものだと思いませんか?
②保護者による襲撃・保護者が襲撃を手引きするケース
従来型の日本では これはあり得ない話だった。
まあ スローガンを書いた赤や青の登りが林立していた時代には 糾弾と称して集団で学校に押し掛け教師をつるし上げていた人たちもいたが、それでも あれは 児童生徒が下校した後でやっていたのではないかなぁ・・。
それに 基本は話し合いであって(実際には監禁恫喝に近いものであったとも聞くが)肉体的暴力はなかったと聞いている
つまり あれは「襲撃」ではない。
しかも 21世紀になってあれをやる人はいない
というかやれば警察が動くことがすでに公になっている。



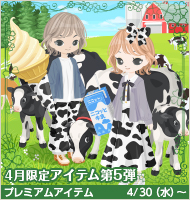











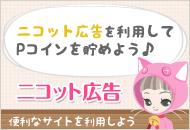


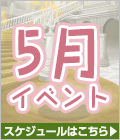








その試験は毎年実施され、その設問と回答と「記述式の場合の採点の基準」は毎回全国紙と広報で公開され、
議員立候補者は その選挙の投票日よりさかのぼって1年以内に実施された 立候補者呼びテストの受験成績と記述式回答内容を選挙公報に記載しなければならない、そういう規定を設ければいいのにと思う。
そして 議員在職中は、在職初日から起算して3回目の試験を必ず受験してその成績を発表することを義務付けたらいい。
そうやって 議員の資質を高めるとともに、有権者が立候補者を選ぶ目安づくりにすべきだ。
つまり 受験して0点でも立候補はできる、ただし その記述式回答内容や評点を見て 投票するか否かは有権者が決めるという形式にすればいいのである。
有権者だって アホが嫌いな人もいれば、点数とは関係なくその立候補者に魅力を感じる人もいるだろうから。
それに議会でも 同じ議員仲間の知識・思想傾向を明確に示す指標があったほうが、お互いに討論しやすく有益な話し合いができるのではなかろうか?
(注:念のために書き添えると・・)
・人間の感情は 理屈や イデオロギーがらみの理想で押さえこめるものではない
「『イデオロギー・建前・理想による感情の抑圧』からの解放」を叫ぶカウンセラーたちが
なんで 学校カウンセラーの仮面をかぶったとたんに
感情の抑圧を 子供達に強いる先兵となるのかなぁ・・
このことに矛盾を感じない感性の持ち主たちが跋扈する 日本の各業界そのものが 怖いわ!
・さらに言えば 公立の保育所においても、基本的には転居を伴わない転園はナシ(だって 保護者のわがままに応じていては 運営が不可能になるから)だが、
特殊な状況においては、「保育者と保護者との関係修復が不可能であるため、入所児への適切な保護を実現するために転園を認める」という所長判断による転園が実行されることもある
これは 学級編成の決定権は学校側にあって、保護者の希望への忖度があってはならない公立義務教育諸学校においても、校長判断により、「当該児童と担任との関係修復が不可能であるため 児童の学習権の保証と学校生活の安全のためにクラス替えを行う」ことがあるのと同じである。
・条理を尽くして審査したうえで 人間の感情のもつれはいかんともしがたく 該当する児童・生徒・子供たちの健全な発育・成長の機会を奪う・損ねる場合においては、配置換えもやむなしという判断も
制度的にはありなのである。
かつて この規定を恣意的に乱用する教職員が氾濫していたので、それを 大っぴらに言えなくなってしまっただけで。
(なのでこの投稿を読んで 感情的に利己的に 学校に物言いしないでくださいね!
個人の感情と 大局的視野にたった子供の健やかな成長を確保するための非常手段とは、別なんだから!)
要は 学校長の指導力の問題であり 各市の教育委員会メンバーの資質の問題であるけれど
議員・団体・メディアを怖がる人間が増えると・・
学校・教育・保育の場の崩壊と危険が増すのである
そして アホ議員とメディアが 文科省の指導力を削りまくっているこの現状><
・議員立候補者には 一律に 「法とはなにか?日本国における立法精神とその役割」といった 法学の専門教養程度のテストに合格することを義務づけるべきではないかと思う
(注:念のために書き添えると・・)
・人間の感情は 理屈や イデオロギーがらみの理想で押さえこめるものではない
「イデオロギー・建前・理想による感情の抑圧」からの解放を叫ぶカウンセラーたちが
なんで 学校カウンセラーの仮面をかぶったとたんに
感情の抑圧を 子供達に強いる先兵となるのかなぁ・・
このことに矛盾を感じない感性の持ち主たちが跋扈する 日本の各業界そのものが 怖いわ!
・さらに言えば 公立の保育所においても、基本的には転居を伴わない転園はナシ(だって 保護者のわがままに応じていては 運営が不可能になるから)だが、
特殊な状況においては、「保育者と保護者との関係修復が不可能であるため、入所児への適切な保護を実現するために転園を認める」という所長判断による転園が実行されることもある
これは 学級編成の決定権は学校側にあって、保護者の希望への忖度があてはならに公立義務教育諸学校においても、校長判断により、「当該児童と担任との関係修復が不可能であるため 児童の学習権の保証と学校生活完全のためにクラス替えを行う」ことがあるのと同じである。
・条理を尽くして審査したうえで 人間の感情のもつれはいかんともしがたく 該当する児童・生徒・子供たちの健全な発育・成長の機会を奪う・損ねる場合においては、配置換えもやむなしという判断も
制度的にはありなのである。
かつて この規定を恣意的に乱用する教職員が氾濫していたので、それを 大っぴらに言えなくなってしまっただけで。
(なのでこの投稿を読んで 感情的に利己的に 学校に物言いしないでくださいね!
個人の感情と 大局的視野にたった子供の健やかな成長を確保するための非常手段とは別なんだから!)
要は 学校長の指導力の問題であり 各市の教育委員会メンバーの資質の問題であるけれど
議員・団体・メディアを怖がる人間が増えると・・
学校・教育・保育の場の崩壊と危険が増すのである
そして アホ議員とメディアが 文科省の指導力を削りまくっているこの現状><
監護権のはく奪とは、親への懲罰目的ではなく
あくまでも 子供の健やかな成長を保証するための施策であるという根本を忘れてはならない。
だからこそ 今回のように 保護者が手引きした襲撃犯が、児童の名前を叫びながら乱入し、担任の顔を殴打し首を切ったというケースでは、「罪を憎んで人を憎まず」などという建前を小2の子供に押し付けるのではなく、襲撃犯一味の子と 襲撃された子たちとの生活権を切り離すことの方が、お互いが 時間の経過により心を落ち着け 年齢的成長とともに 事件を客観的に考える力が身につくことを助けることになると考える。
つまりそういう観点で 犯罪者と目される人達の子どもを守り育てるとともに、被害者グループに属する子供達の成長を促すための、別離の促進を政策的に行う必要があると考える。
そして 親の偏った考え方・己が所属するコミュニティを害する行動パターンに 子供がこれ以上苦しめられないように(or染まらないように)、子供を保護することも 児童福祉の観点から重要と考える。
中途半端な忖度や 変なイデオロギー縛りは 当事者たる子供に不幸(健やかに育つ機会を奪うこと)しかもたらさない!
・そういう意味では、本文中割愛した毎日新聞の残り部分の見解
=『は保護者対応は教員の多忙化の要因の一つとも指摘されており、文科省や自治体は負担軽減の観点から弁護士やカウンセラーなど専門職の積極的な介入を促すなど、対策を強化している。
事件を受け、ある文科省幹部は「学校との話し合いが突発的なものだったのか継続的になされていたものだったのか、どのような内容だったのかについても注視していきたい」と話した。』は、
いかにも 今風の 隔靴掻痒どころか 為政者の保身のために無難さを追い求めて本質を外すコメントであり政策だなと思った。
・なので 保護者が 教師に暴力をふるったら、理由のいかんを問わず 厳しく処罰すべきである。
それまでの経緯云々にとらわれる必要はない
教師が 児童生徒や暴力をふるえば即逮捕・失職
保護者が 教師に暴力をふるえば即逮捕
それでよいではないか。
・さらに、親が教師に暴力をふるえば、その親の子にとってもその後の生活がやりにくくなるから、そこはもう、隣の校区への転校なり、児相が動いて一時保護から 保護者が速やかに円滑に転居できるように行政が援助することも必要だろう。
子どもにとって 「学校・担任」の存在感は大きい
「家庭・家族」に匹敵する重みがある
だからこそ、クラスメートの親が担任に暴力をふるったとなれば、その後の学校生活は お互いが気まずい思いをするのがあたりまえ。
まして情緒の発達途上・社会的感情の形成過程にある小中学生に 「自分や自分の家族を傷つけた人と今後も友好的に付き合いましょう」と強要(教育的指導ともいう)することは、公教育の名を借りた精神的に拷問に等しい
だからこそ 両者の健全な発達保障のためには、学校・教員を襲撃した一家には 別の校区に転出してもらい、そこで新しい人間関係を築くチャンスを提供することこそが、襲撃犯の子供の健やかな成長のためにも、襲撃された側の子供達の精神的健康回復のためにも 必要なことと考える。
そういう意味で 子供達の健やかな人間関係を再構築するための必要経費として、公務として 襲撃犯一家の転居費用の半額補助・転居先のあっせんと転居先の秘匿協力くらいは やってもいいと思う。
学校カウンセラーなどにお金を使うよりも そのほうがよっぽど有益なお金の使い方だと考える。
・さらに 保護者が自分の知人を引き連れて学校襲撃した今回のようなケースに関しては、保護者から監護権を取り上げるのが その襲撃犯の子供の健全育成環境を守るために必要な措置と考える。
・そもそも 親が地域で大きな事件を起こした場合、その子供達が地域住民からの白い眼を向けられて育つことほど理不尽な話はないのである。
和歌山の毒入りカレー事件の犯人と目された夫婦の子供達は悲惨な人生を送り、とうとう娘さんの一人はわが子とともに関空連絡橋から海に飛び込んで亡くなった痛ましい出来事を、私たちは決して忘れてはいけない