『ぺらぼう 第13回目』日ハム首位の夜、書きます
- カテゴリ:テレビ
- 2025/03/30 22:14:55
♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡
なんと60何年ぶりの開幕3連勝で、我が北海道日本ハムファイターズは首位で開幕カードを終了!!!
ドラマ端境期に夢を魅させてもらいましたっ!!!栗山元監督の名言「夢は正夢」になりますように。
では、今回日曜ドラマナイト唯一の大河考察をして明日の決算日を迎えます。
・松平定信は先週、数分、青本?立ち読みしてお終いかい・・・。
・鱗形屋はしぶとい。罰金20貫文って何両??再犯は重罪じゃないの??
・あの取立ては映画「闇金のウシジマくん」と全く同じやり方。進歩してないんだあ。
・長谷川平蔵の「みてくれ」売りを自称するのはうざい。
・何度か出て来る「主殿」とは?
・徳川家基は当初からの「爪噛み」は愚君の伏線か?
・以前、小芝風花の吉原ラストで絶賛しましたが、その後もずっと出てるなあ。そして今回、別番組予告で来月からのNHKBS時代劇の主役だってええーー。すると同時併行での主役級はきつい。→ 大河からは消えるフラグか!!!
・赤本の裏の「からまる」はかつての自分が名を書いたものを瀬川にあげたものということ。先週の予告編の出し方、ひっかけすぎ。
なんだか「視覚障がい者」ばかりクローズアップされて、いいも悪いもあまりスッキリはしません。他の障がい者はどうしてたんだろう。家康のたまたまの思い付きでこうなったのかなあ。
それよりもっと現政権につながる風刺をグサグサ入れてやればいいのに。
かな?
♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*・・♡・・*


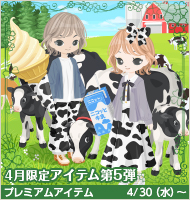












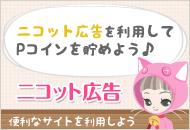












了解いたしましたあーー。
遅くまで、どうもありがとうございました。
今夜は敗戦かみしめて寝まーす。
おやすみなさーい。
田沼意次が「主殿」と呼ばれていたのなら、意次の官職名「主殿頭(とものかみ)」の事ですね。
本来は天皇の日用品や住まいを管理する総責任者の事ですが{「光る君へ」の時代なら本来の役目を果たしていたと思います)、江戸時代だと職務の実態が無い名誉職でしょうね。
主殿は今夜も将軍が「田沼意次を呼ぶ時に使ってました。
予告編ではまだ「家基」のことは出てませんでしたね。
次回は幕府編を厚くして、検校処分、いよいよ再来週に家基没ってことなんでしょうかーー。
20時にも間に合いませんでした・・・。
我が北海道日本ハムファイターズ、惨敗で寄り道して荒れてきました。
これから「追っかけ視聴」で追いつきます。
ドラマでもいるようですね? 怪しげな動きをしている人物が。
赤本に書かれた「からまる」の名ですが、「からまる」は蔦重の幼名ですし、如何にも拙い書き方ですし、特に引っ掛けだった訳ではないと思いますが。
宝物の根付を無くした禿時代の瀬川に、幼い「からまる」時代の蔦重が自分の宝物である赤本を渡すシーンがあった筈ですし、行方不明になった「からまる」よりこちらの方が連想しやすいのでは?
視覚障碍者の優遇は、多分室町時代からです。
足利尊氏の従兄弟で明石覚一という人が自分の邸に当道座を設立して、自らが惣検校となったのが江戸時代まで続く検校制度の始まりだと言われています。
家康はその流れを追認した形ですね。駿府での人質時代に親しくしていた検校がいたり、側室の西郷局(お愛の方/秀忠生母)が弱視だったことから視覚障碍者を支援していた(「どうする~」でも描かれてました)という事も関係していたかもしれない、とは思います。
たまたまの思い付きではない筈。
現代の様な社会福祉の概念が無い時代ですので、視覚障害以外の障碍者には厳しい社会だったのではないか、と思われます。
また、視覚障碍者でも当道座に所属していない者も他の障碍者同様に厳しかったのではないでしょうか。
松平定信は、老中として幕政に関与するようになってからが本番でしょう。
具体的には天明の大飢饉が起きてから。
飢饉の際、白河藩に餓死者を出さなかった手腕を買われての起用の筈。
鱗形屋に関しては最初は重版をした本の売れ残り分と版木の没収で、その後に手代の徳兵衛が江戸十里四方追放で鱗形屋には二十貫文の罰金になった模様です。
1貫文が銭(寛永通宝)1000枚だったので20貫文は銭2万枚。
ただ寛永通宝には1文銭と4文銭があったので、どちらで計算すべきなんでしょう?
1両=4000文なので、1文銭なら20貫文は5両。4文銭の場合は4倍の20両、といったところ?
どう計算するべきなのか、あやふやで良く分かりません。
5両でも20両でも、鱗形屋にとっては本来端金と言って良い筈ですが、ドラマの鱗形屋は店の経営が非常に厳しいので、罰金はかなり手痛いでしょうね。
ただし、鱗形屋に座頭金を絡ませたのはドラマオリジナルで、史実ではそのような形跡は無いと思われます。
当道座の借金の取り立ては、実にえげつなかったそうです。
暴利と言って良い高利の貸し付けで取り立てもえげつないほど厳しいとなれば、方々で恨みを買ったとしても不思議ではないですね。
取り立て方法が現代も変わらないのだとしたら、人間に進歩が無い、という事なんでしょう。
長谷川平蔵の役職は、ドラマの時点では進物番です。
各方面からの江戸城への御進物要するに贈り物の管理を担当していましたが、この役職は容姿端麗な者が選抜されたそうです。進物を披露する儀式がありましたので、披露する者の容姿も重視されました。
同じ料理でも、盛り付けた器の差で3割増しくらい上等に見えたりしますが、それと似た様なものです。
「主殿」は多分「主殿造」から来たものだと思います。
屋敷内の中心となる建物を意味したり、会合場所を意味したりしていると思うのですが…
爪噛みは、物事が自分の思い通りに進まなかった際の苛つきをしめすものでしょうか。
徳川家康にも爪噛みの癖があったそうですし、何度か家康を演じた津川雅彦さんも爪を噛む演技をされていた気がします。
ただ、愚君の伏線にはならないと思います。
家基は若死にしますので。幻の十一代と呼ばれる所以です。
鳥山検校の摘発が1778年で、家基の死はその翌年なのでもうすぐですね。