フィアット500
- カテゴリ:日記
- 2015/10/24 15:39:38
2代目 NUOVA 500(1957 - 1977年)[編集]
1957年に発売、以後1977年まで20年間の長期に渡り生産された4人乗りの小型自動車である。主任技術者は初代にも関わっていたダンテ・ジアコーサ。
空冷エンジン、RRを採用し、全長×全幅×全高は2970×1320×1325mmとなっている。正式名称はFIAT NUOVA 500(新フィアット500)であるが、一般にはイタリア語で500を意味するチンクェチェント(Cinquecento)の呼称で知られている。旧500のトポリーノと区別するため、NUOVA 500(新500)と称される。初代500の直接後継モデルではなく、異なるコンセプトで新規設計された同クラス・別系統車種である。
先行して発売されていた600(1955年発表)のメカニズムが多くの点で流用されており、同様にモノコックボディのリアエンジン・リアドライブ車となった。
開発経緯[編集]
NUOVA 500の登場に先行し、新型車600(セイチェント)が、1955年に製造終了した初代500の後継車としてジアコーサの手で開発されていた。600は500とほぼ同等の全長ながら、リアエンジン・リアドライブ方式の採用などでスペース効率を大幅改善し、完全な4人乗り乗用車として設計されていた。
ジアコーサは600の開発にあたり「4人乗り車の半分の費用で2人乗り車を作ることはできない(従って4人乗り車の方がユーザーの便益が大きい)」という信念のもと4座化を図った。この実現のためにスペース効率や軽量化の見地からドライブシャフトを廃した駆動方式を探り、当時前輪駆動車実現には等速ジョイントの実用性が不十分だったことから、より現実的なリアエンジン方式を採用した。
600は500にも劣らぬ人気車種となったが、フィアットはこの成功に満足していなかった。1950年代当時のイタリアでは、軍需を失った戦後の代替生産として、航空機メーカーや鋼管メーカこぞってスクーター市場に進出しており、自動車を買えない大衆の足として大きな成功を収めていた。フィアットではこれらスクーターを代替する乗り物として、600よりさらに安価な乗用車を投入することが次なる需要につながると判断したのである。
このような背景から、NUOVA 500は基本的に600を一回り縮小したモデルとして設計された。600と比較してスペース的に窮屈ではあるが4人乗りとしていた。2人乗りだったことで競合車種に顧客を取られてしまったトポリーノ時代の反省点と、スクーターとの大きな差別化を図るという点から重要視され、実現されたものである。
ジアコーサはこれを理解しながらも、さらなる小型車の開発にはあまり気乗りはしていなかった。600こそが自身最良の回答であり、それ以下の構成では従来車種に対して走行性能での進化が見込めないと考えていたからである。それでも度重なるフィアット側の説得に折れる形で設計に着手したが、エンジンを空冷直列2気筒とすることには最後まで抵抗し続けた。実際にはコストや開発期間の関係から、それに変わるエンジンの調達は難しく、最終的にはジアコーサもこの条件を飲まざるを得なかった。
大々的なキャンペーンや廉価な価格設定などの効果もあり、ふたを開けると販売が非常に好調であったことから、いつしかエンジン形式の変更の話は立ち消えとなった。そればかりか、その拡大版が126やパンダにまで使われ続ける大変な長寿エンジンとなった。だだしジアコーサは生前日本の自動車趣味誌のインタビューに対し、NUOVA 500が多くの人々に愛されたことに感謝しながらも、「あのエンジンを許したことだけには悔いが残る」と語っている。
メカニズム・デザイン[編集]
600同様の水冷直列4気筒エンジンは最廉価クラス用としては高コストになるため、500には前述のとおり、簡素でコンパクトなパワーユニットとして開発された479cc・15PSの空冷直列2気筒OHVが縦置で搭載されていた。オイルフィルターは遠心分離式。最高速度は軽量なボディと相まって95km/hに達した。マウントにスプリングを利用するなど配慮は見られるが、音が大きく振動が激しいため乗り心地には悪影響を及ぼしており、NUOVA 500シリーズ最大の欠点になっている。
車体は全鋼製モノコックとされたが、エンジンの騒音が屋根板のせいで車内にこもってしまうため、対策として屋根をオープンにできるキャンバストップを標準装備した。これにより騒音は車外に発散され、居住性を改善できた。キャンバストップは機能的に必須とされたものである。
サスペンションは600の縮小コピーで、フロントが横置きリーフスプリングをアーム兼用としたシングルウィッシュボーン、リアがダイアゴナルスイングアクスルとコイルスプリングという組み合わせとなる。
2ドアモノコックボディの、丸みのあるユーモラスなフォルムは、設計者のジアコーサ自身が手掛けたものである。元々愛嬌のあった600のデザインをさらに縮小して仕上げたような雰囲気を持っている。ジアコーサが晩年『カーグラフィックTV』のインタビューで述べたところでは、自らクレイモデル(新しいスタイリングを試すために作られる粘土模型)を毎日撫で回すように手作業で削り出していたら、自然に出来てしまったのだという。独特の丸みを帯びた形状は、少しでも軽く仕上げるために使用する鉄板を減らすべく表面積を減らす意図もあったとも語っている。
同時代の日本の軽自動車スバル・360でも見られる傾向であるが、これらの小型車では、ボディの表面積を減らしつつ丸みを持たせることで軽量化と強度を両立させるデザインがしばしば用いられた。薄い鋼板でも丸みを帯びたプレス加工を行うことで、補強や工程の追加なしに必要な剛性を確保したのである。
運転席[編集]運転席[編集]
旧世代の自動車ということもあり、現代の車とは使い勝手が異なる部分が多数ある。
- キー - オンオフ・パーキング。セルモーターはワイヤー式でレバーを引いて動作させる。シフトノブ後方に設置されている。
- ワイパー - オンオフのみ。動力はエンジンのバキュームやスピードメータケーブルではなく、電気モーターにて駆動される。初期型から最終型まで同じ仕様である。電気モーターなので簡単な回路の追加で速度調整や間欠動作が可能である。
- ウインカー - 最初期型以外はハンドルのコラムスイッチにて操作する。
- ガソリンタンク - 容量は21Lでフロントフード内に設置されており、給油時にはフードを開ける必要がある。フロントフード下はトランクだがガソリンタンクとスペアタイヤで占領されており物を入れるスペースはほとんどない。
- 燃料計 - 残量5リットルで警告灯が点灯。Lタイプには残量計が付く。
- チョークレバー - エンジン始動時に使用する。セルモーターレバーの横にある。
- ハンドスロットル - エンジン暖気のための装備。












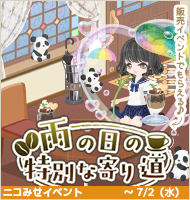


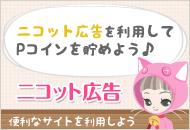














長文^^