防災の日と関東大震災
- カテゴリ:日記
- 2015/09/01 13:05:02
関東大震災(かんとうだいしんさい)は、1923年(大正12年)9月1日11時58分32秒(日本時間、以下同様)、神奈川県相模湾北西沖80km(北緯35.1度、東経139.5度)を震源として発生したマグニチュード7.9の大正関東地震による地震災害である。
神奈川県・東京府を中心に千葉県・茨城県から静岡県東部までの内陸と沿岸に広い範囲に甚大な被害をもたらし、日本災害史上最大級の被害を与えた。
被害[編集]
190万人が被災、10万5千人余が死亡あるいは行方不明になったとされる(犠牲者のほとんどは東京府と神奈川県が占めている)[注釈 1]。建物被害においては全壊が10万9千余棟、全焼が21万2000余棟である。東京の火災被害が中心に報じられているが、被害の中心は震源断層のある神奈川県内で、振動による建物の倒壊のほか、液状化による地盤沈下、崖崩れ、沿岸部では津波による被害が発生した。
人的被害[編集]
2004年(平成16年)頃までは、死者・行方不明者は約14万人とされていた。この数字は、震災から2年後にまとめられた「震災予防調査会報告」に基づいた数値である。しかし、近年になり武村雅之らの調べによって、14万人の数字には重複して数えられているデータがかなり多い可能性が指摘され、その説が学界にも定着したため、理科年表では、2006年(平成18年)版から修正され、数字を丸めて「死者・行方不明 10万5千余」としている[2]。
地震の揺れによる建物倒壊などの圧死があるものの、強風を伴った火災による死傷者が多くを占めた。津波の発生による被害は太平洋沿岸の相模湾沿岸部と房総半島沿岸部で発生し、高さ10m以上の津波が記録された。山崩れや崖崩れ、それに伴う土石流による家屋の流失・埋没の被害は神奈川県の山間部から西部下流域にかけて発生した。特に神奈川県足柄下郡片浦村(現、小田原市の一部)の根府川駅ではその時ちょうど通りかかっていた列車が駅舎・ホームもろとも土石流により海中に転落し、100人以上の死者を出し、さらにその後に発生した別の土石流で村の大半が埋没、数百名の犠牲者を出した。
この関東大震災については、私は祖父にリアで聴いたのと、その時の新聞を祖父が手元に保存していたので、読んだことを思い出す















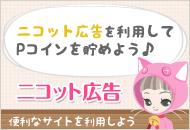













関東住まいのみかんです。
今日は多くの学校で始業式だと思いますが、
この関東大震災を忘れないために、避難訓練を9月1日に
実施する学校も多いんですよ。
関東はほんとに、地震が多いなぁ・・・と思います><;