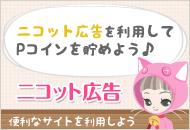浴衣
- カテゴリ:日記
- 2015/08/21 15:12:37
平安時代の湯帷子(ゆかたびら)がその原型とされる。湯帷子は平安中期に成立した倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)によると、内衣布で沐浴するための衣とされている。この時代、複数の人と入浴する機会があったため汗取りと裸を隠す目的で使用されたものと思われる。素材は、水に強く水切れの良い麻が使われていたという説がある。
安土桃山時代頃から湯上りに着て肌の水分を吸い取らせる目的で広く用いられるようになり、これが江戸時代に入って庶民の愛好する衣類の一種となった。
「ゆかた」の名は「ゆかたびら」の略である。
概要[編集]
生地は木綿地で通常の単物よりもやや隙間をあけて織った平織りのものが多い。特に夏場の湯上り、または寝巻きとしての用途が主である。日本舞踊などでは稽古着として使用される。家庭でも手軽に洗濯が可能であり、清潔を保ちやすいことも重宝される一因である。
和服の中でも最も単純かつ基本的な構造である。また反物も比較的安価であることから、家庭科の授業で和裁の基礎を学ぶ際に、浴衣を縫うことが多い。
本来は素肌の上に直接着るものである。近年は、お洒落着としての需要も多く、浴衣を着用して外出する場合もあるため下着を着用することが多くなった。浴衣仕様に軽量化されたり吸汗性に優れた肌襦袢を併用する場合が多い。 女性は一般的に和服を着用する際はバストのふくらみは目立たないようにさらしや和装用ブラジャーなどで押さえることがあるが、浴衣の場合は更に簡素な和装用の簡易スリップなどの肌着を使用することも多い[1]。
男子は三尺帯、女子は半幅帯で着用することが通例とされていたが、着付けの簡略性もあり、兵児帯(へこおび)を用いることもある。さらに最近では男子は角帯を用いることも多い。角帯は元来は浴衣には合わせないものとされていたが、この意識は薄れつつある。事実、服飾メーカーでは新作発表の際に浴衣と角帯の組み合わせを提案することも増えている。同時に、セット販売されることも珍しくない。男子の帯は一般的なウエストラインではなく臍よりもやや下、骨盤の当たりに締めて下腹部部位を心もち下げる様に着付ける。
和服に親しむ人が減少していることもあり、一人で帯結びが出来ない人も多い。そのため、一部のメーカーは「作り帯」(すでに結び目を仕上げた状態で固定したものと、胴囲部分の組み合わせ。胴囲に帯を巻きつけ、結びを差し入れた後に紐やクリップで固定する形態のものが多い)を製作・販売している。また身頃本体も一枚繋ぎではなく、上下を分けて着用する二部式のものも存在する。
浴衣に合わせる履物は、素足に下駄が一般的である。穿き慣れない下駄で足捌きが悪く転んだり、また、鼻緒で足指や足の甲を擦って怪我をする人も少なくない。薄手の足袋を併用したり、洋服用のサンダルを合わせる人もいる。男性の場合も同様であるが、雪駄の選択肢もある。
和服の項目にもあるように、一般的な和服の着付けと同様に身に纏う。男女共に右前(右の衿(右半身の身頃)を下にして、左の衽を上に重ねる)にして着るのが正しい(相手方からみるとアルファベットのYの小文字「y」になるように、自分の右手が衿に差し入れやすいように…と念頭において着付けると間違えにくい)。また、裾は訪問着や小紋よりも、心もち上にあげ、くるぶしが見え隠れする程度に着付ける。